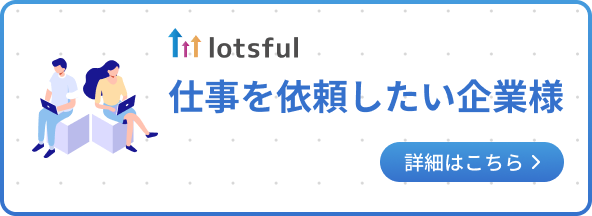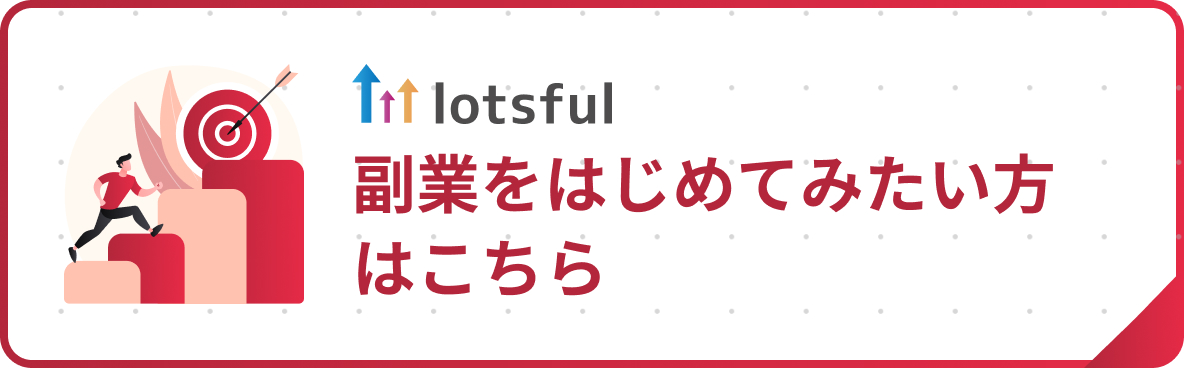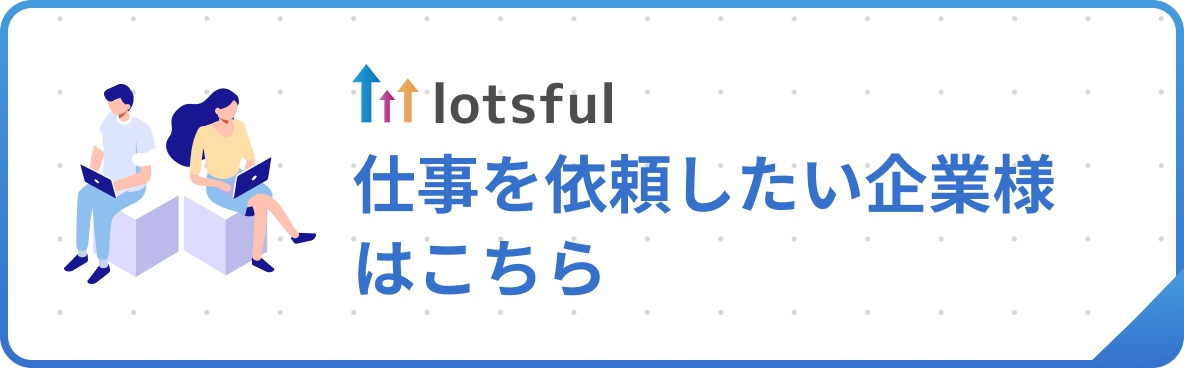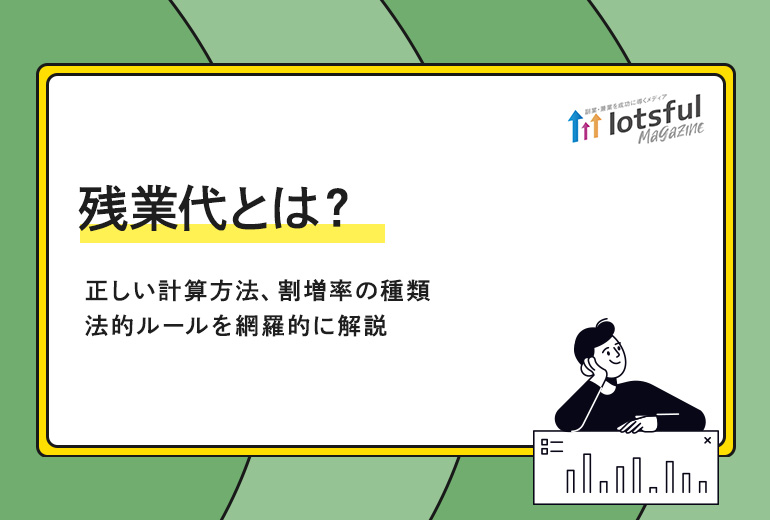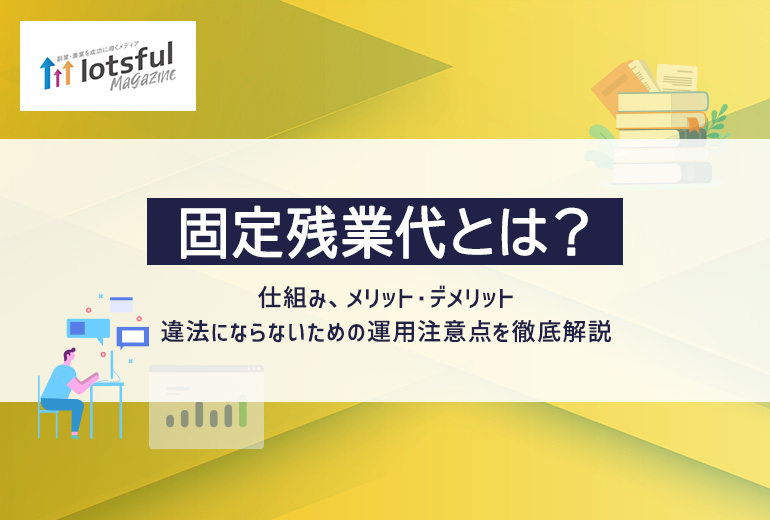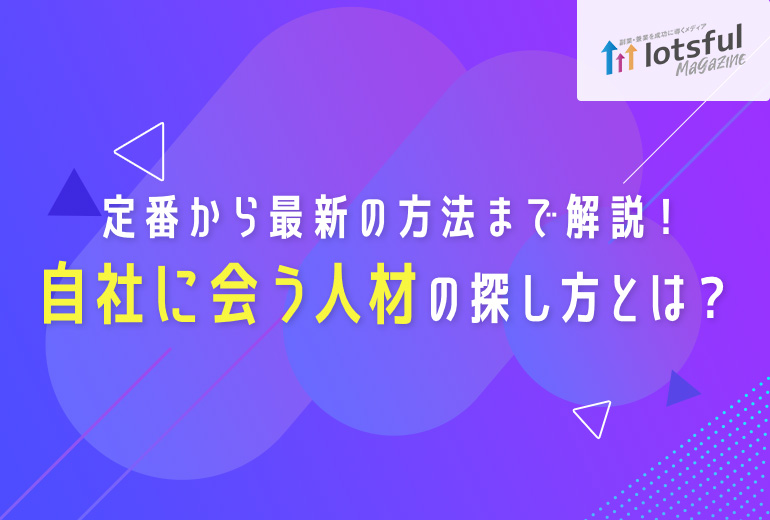
自社に合う人材の探し方とは?定番から最新の方法まで解説
正社員から副業人材を含めた採用活動を行う際に、「自社に合う人材であるかどうか」は、極めて重要な要素といえるでしょう。
また、適切な人材の探し方には、定番から最新まで多様な方法があります。本記事では、自社に合う人材の探し方に加え、採用時に留意すべき注意点についても詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
自社に合った人材の探し方
“自社に合った人材”とは、募集職種やポジションにおいて経験やスキルが豊富であるだけでなく、自社の文化や組織の方向性にもフィットする人材を指します。
自社に合う人材の探し方として、以下に挙げる6つの方法を実践してみましょう。
採用ペルソナを明確にする
自社に合う人材探しの第一歩は、活躍が期待できる具体的な人物像を、あらかじめ定義しておくことです。
採用ペルソナを明確にすることで、「スキルや経験は十分だが、自社カルチャーと合わない」「意欲はあるが、即戦力にはならない」といったミスマッチを減らせます。
活躍社員の共通点(スキル・性格・志向)を分析する
自社に合う人材を探す方法としては、自社で成果を上げている社員の共通点を把握することが、最も効率的かつ実践的な方法といえるでしょう。
活躍している社員のスキルや性格、志向を分析すれば、採用基準が明確になります。これにより採用時のミスマッチ防止に加え、入社後の定着率向上にもつながります。
自社の価値観・カルチャーにマッチする人物像を可視化する
「自社に合う人材=自社の価値観やカルチャーにマッチする人材」と位置づけられます。この観点を可視化すれば、精度の高いマッチングが実現します。
さらに、共通の価値観を持つ人材が集まることで、意思決定やコミュニケーションもスムーズになります。
部門ごとのニーズをヒアリングし、必要な要素を整理する
自社に合う人材といっても、求めるスキルや人物像は部門ごとに異なります。採用活動は人事や経営層だけでなく、現場の意見も踏まえて必要要素を整理することが重要です。
現場のニーズは、「業務内容の現状と課題」「必要なスキルや経験」「応募者の行動特性や価値観」などです。これらを必須条件と歓迎条件に分けて整理すれば、採用要件の明確化につながります。
面接でスキルだけでなく「カルチャーフィット」も重視する
応募者のスキルばかりを重視すると、自社カルチャーとマッチしない人材を採用するおそれがあります。カルチャーフィットを軽視した採用は早期離職の要因となり、結果として定着率の低下につながるでしょう。
面接ではスキルに加え、「過去に何を行い、どのような成果を得たか」を問うことが有効です。さらに、評価基準をスキルとカルチャーの二軸に設定すれば、バランスの取れた判断が可能になります。
採用データをもとに、どのチャネルが相性が良いか検証する
自社に合う人材を探す際には、採用担当者の感覚や主観に頼らず、これまでの採用データを有効に活用することが重要です。過去の採用データをもとに、効果の高い採用チャネルを検証しましょう。
検証の際は応募数だけでなく、「活躍が期待できる人材から応募があったかどうか」も基準に加える必要があります。自社と相性の良い採用チャネルを見極めれば、質の高い人材の確保に加え、コストの最適化も実現できます。
定番の人材募集方法
人材募集方法の中でも、定番とされるのは以下の6つです。
求人媒体への掲載
人材募集方法として最も定番なのが、求人媒体への掲載です。幅広い候補者にリーチでき、効率的に母集団を形成できる点がメリットです。
「新卒・第二新卒向け」「中途採用向け」「専門職向け」などの特徴があるため、自社のニーズに適した求人媒体を選べば、費用対効果の高い採用が可能です。
ハローワークでの求人票提出
公的な職業紹介機関であるハローワークの活用も、定番の方法の一つです。求人掲載は無料で、地域に根差した採用に強い点も魅力といえます。
採用コストを抑えたい中小企業にとって利用しやすい方法ですが、応募者のスキルや経験が要件に合わない場合もあるため、他の求人媒体や自社採用サイトとの併用が望ましいでしょう。
転職エージェント(人材紹介会社)利用
転職エージェントや人材紹介会社を利用すれば、自社が求める条件に合った候補者をピンポイントで探せるというメリットがあります。
候補者の「スキル」「志向」「カルチャーフィット」を確認したうえで紹介されるため、ミスマッチの少ない採用が可能です。ただし紹介手数料が発生し、特に専門職採用においてはコストが高くなる傾向があります。
関連記事
・転職エージェントの費用相場はいくら?企業が使うメリットデメリット
・人材紹介とは?人材派遣との違いや活用のコツ、会社選定のポイントまで解説
自社コーポレートサイトの採用ページ
自社サイトの採用ページを活用するのも定番の方法です。「自社カルチャー」「価値観」「はたらき方」「社員の声」といった情報を自由に発信できる点が大きなメリットです。
採用ページを通じて自社の魅力や独自性を直接アピールでき、サイトからの応募も可能となります。さらに、コンテンツの改善やターゲット層への訴求にも役立ちます。
社員紹介
社員から知人や友人を紹介してもらうリファラル採用は、「カルチャーフィットの高さ」「コスト効率」「スピード感」「信頼性」といった面で優れています。
求人媒体や転職エージェントを利用する場合と比べ、コストを大幅に抑えられるうえ、紹介された候補者は社風やチームに馴染みやすい傾向があります。
関連記事:リファラル採用とは?メリットデメリットや注意点まとめ
合同企業説明会や採用イベントへの出展
合同企業説明会や採用イベントへの出展は、一度に多くの求職者へリーチできるため、認知度の向上や母集団形成において非常に効果的な人材募集方法です。
費用と労力はかかりますが、自社単独での採用活動より効率的に求職者の関心を引くことが可能です。また、求人媒体では出会えない層と接点を持てる点も大きなメリットです。
最新の人材募集方法
以下では、数ある採用手法の中でも、近年注目されている4つの方法をご紹介します。
スカウト型採用
スカウト型採用は、企業がカルチャーフィットする人材に直接アプローチする”攻めの人材募集方法”です。
従来のように求人情報を掲載して応募を待つのではなく、積極的にアプローチできるため、競合に先んじて人材を獲得できます。
関連記事:スカウト型採用とは?メリットデメリットや向いている企業を解説
SNS採用
SNS採用は、従来の求人媒体や転職エージェントだけでは届きにくい人材に直接アプローチできる新しい方法です。
X(旧Twitter)、Instagram、LinkedInなどを活用し、求職者の興味や関心に沿った情報を発信します。自社への興味を引ければ、転職潜在層にもリーチできる点が魅力です。
関連記事:SNSを活用した求人方法とは?メリットデメリットや成功のコツまで
採用広報
求職者の情報収集行動が変化する中で、採用広報も注目を集めています。近年の求職者は、求人票だけでなく、SNSや口コミサイトなど複数の情報源を参考にして企業を判断しています。
企業自らがストーリーや魅力を発信する採用広報は、求職者の動向にフィットするだけでなく、顧客からの印象も高めるため、ブランディング強化にもつながります。
ダイレクトリクルーティングツール
ダイレクトリクルーティングツールは、企業が求職者へ直接アプローチできる採用支援サービスです。最新の人材獲得方法として、競合との差別化要素にもなります。
理想的な候補者へ直接オファーできるため、採用スピードが向上し、ミスマッチの少ない人材確保が可能です。特に専門職やエンジニアなど、売り手市場の職種で効果を発揮します。
関連記事:ダイレクトリクルーティングにデメリットはある?成功させるにはどうする?
人材探しの注意点
人材探しを行う際の注意点として、以下の6点を挙げておきます。
求人内容と実際の業務が乖離しないように正確に記載する
自社に合う人材を探す際に、求人内容と実際の業務が乖離していると、ミスマッチによる早期離職や、入社後のギャップによるエンゲージメント低下を招きかねません。
正確な求人情報を記載することで、自社にマッチしない人材からの応募を回避できます。さらに、応募者に対して誠実な企業であるという印象を与えられるため、定着率向上にもつながります。
必要以上に条件を絞りすぎて母集団が集まらなくならないようにする
条件を過度に絞り込むと、本来であれば活躍できる潜在的な人材が候補から外れてしまい、母集団形成が難しくなります。
「応募者が集まらない」「優秀な人材を取りこぼす」といった事態を避けるためには、ポテンシャル人材も取り込める柔軟な条件設定が重要です。
採用チャネルごとに適した伝え方・言葉選びを意識する
採用チャネルごとに応募者層は異なるため、情報の伝え方や言葉選びを工夫する必要があります。SNS採用であれば若年層の利用が多いため、短文やビジュアル、ストーリー性を取り入れた内容が効果的です。
チャネルに適した言葉で伝えることで、自社カルチャーとのフィット感だけでなく、仕事内容への理解も深まります。
面接官の評価基準を統一し、主観による判断を避ける
評価基準が統一されていない場合、面接官の主観や印象に左右され、採用精度が低下するおそれがあります。
公平な判断ができるよう、「スキル」「カルチャーフィット」「志向・行動特性」といった評価軸を定義し、面接官全員に共有しておきましょう。
法令(職安法・雇用機会均等法など)に抵触しないよう注意する
採用活動においては、職安法や雇用機会均等法などの法令を遵守することが大前提です。違反すれば行政指導や罰則の対象となるだけでなく、自社の信頼を大きく損ねます。
「求人情報に不適切な内容や表現がないか」「勤務条件が法令に沿っているか」をチェックするガイドラインを作成し、求人票や面接の質問事項を整理しましょう。採用担当者への研修も欠かせません。
採用ブランディングに一貫性を持たせ、イメージの乖離を防ぐ
採用ブランディングにばらつきがあると、実際の社風や業務内容とのギャップが生じ、ミスマッチや定着率低下につながります。
「自社カルチャー」「ミッション・価値観」「はたらき方」など、メッセージに一貫性を持たせましょう。統一感のあるブランディングにより、自社に合う人材を効率的に確保できます。
早期離職を防ぐため、選考時に「志向・相性・期待値」をしっかり確認する
スキルのみに注目すると、入社後にギャップが生じて早期離職につながりかねません。
応募者が何を重視し、自社でどのように活躍したいかを把握するために、「志向」「相性」「期待値」を選考時に確認しておきましょう。これにより入社後のギャップを減らせます。
御社の業務に副業社員を検討してみませんか?
今回は、自社に合う人材探しについて、定番から最新の方法の紹介に加え、注意点も交えて解説しました。
人材の確保だけでなく、業務上の課題を抱えている場合には、さまざまなスキルや経験を持つ副業社員の力を借りることも、有効な解決手段です。即戦力としての活躍が期待できる人材をお探しであれば、副業人材マッチングサービス「lotsful」の活用をご検討ください。
スピーディーな副業人材の獲得をローコストで実現できる「lotsful」であれば、工数負担を軽減できるため、御社のご担当者がよりコア業務に専念できるメリットがあります。
業務に関するお悩みを早期に解決したいなら、新たな採用チャネルとして利用価値の高い「lotsful」へ、まずはご相談ください。