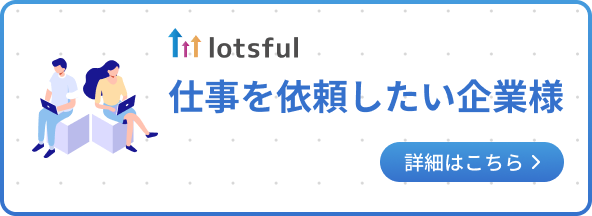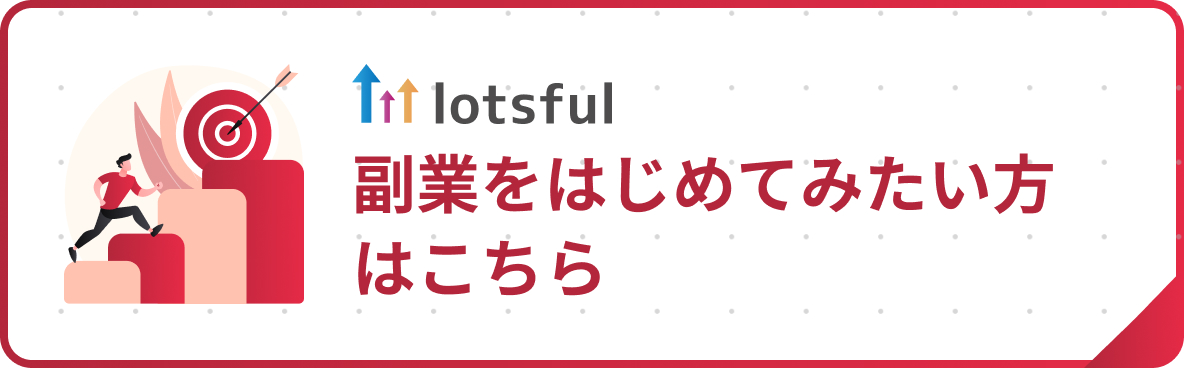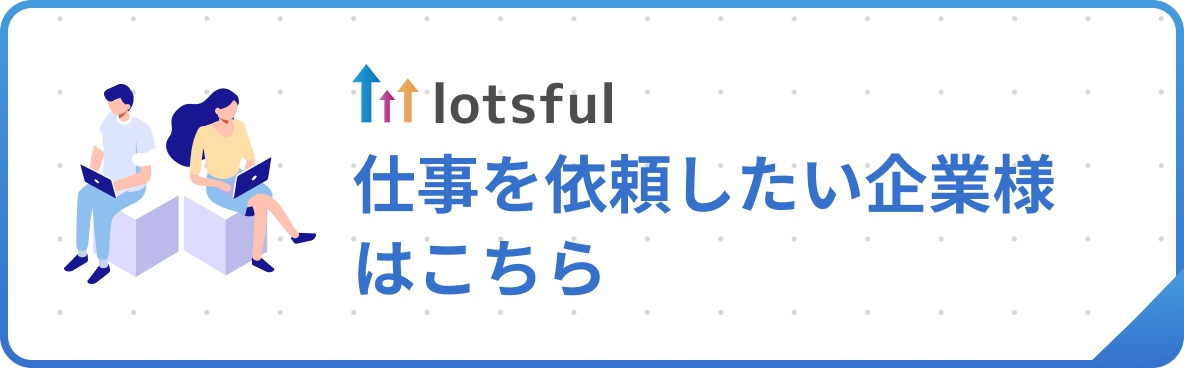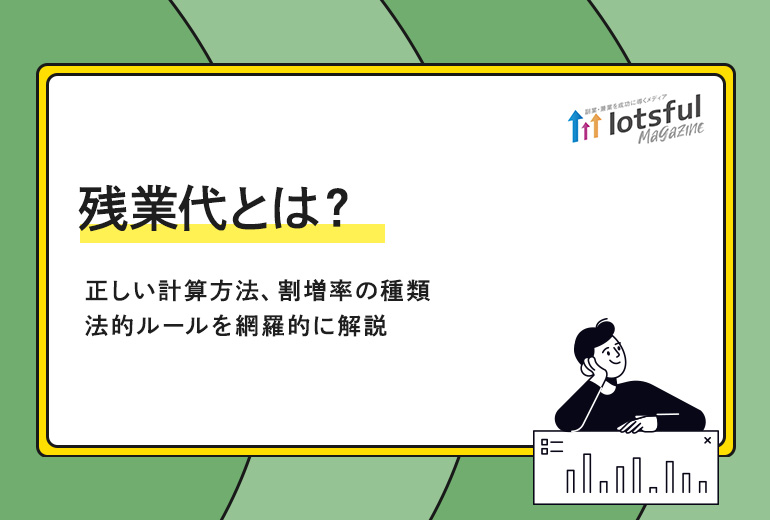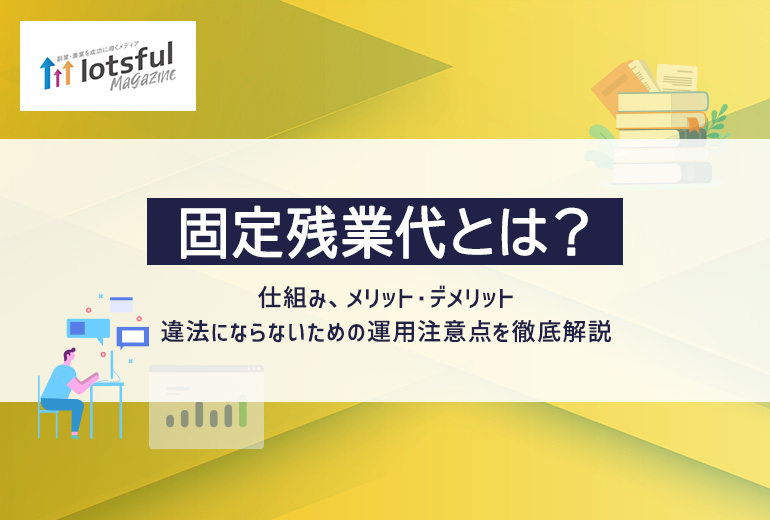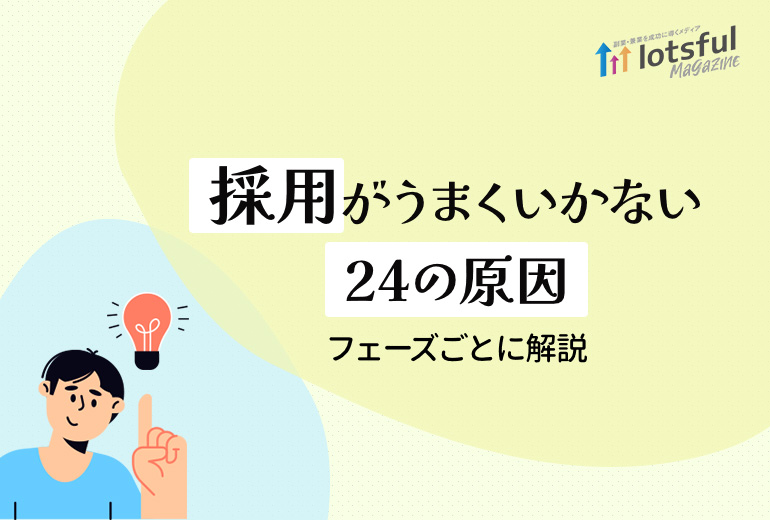
採用がうまくいかない24の原因をフェーズごとに解説
採用活動が思うように進まず、悩んでいる採用担当者の方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、採用計画、採用スタート、採用手法、選考、内定フォローの5つのフェーズに分けて、採用がうまくいかない24の原因を解説します。
また、採用業務には副業人材を活用する選択肢もあります。詳しくは記事の最後をご覧ください。
- マーケティング部長クラスに副業人材を抜擢!リード獲得数が倍に
- 副業人材に「フルコミットしたい」と思わせる関係性を約1年半で構築
- 「事業の成長性」や「組織の魅力」で勝負できる。ミスマッチの少ない副業採用
採用がうまくいかない原因:採用計画編
まず、採用計画段階での採用がうまくいかない原因を5つ解説します。
求める人物像が不明確
採用計画を立案する際には、どのような人物を採用したいのかを明確に定義することが欠かせません。経営方針と照らし合わせ、採用担当者が採用部門からニーズをヒアリングしますが、ここで求める人物像を言語化できなかったり、部門間の調整が不十分だったりすると、採用後にミスマッチが発生しやすくなります。
経営層や採用部門と連携し、必要な人材への理解を深めるとともに、「主体性がある」「コミュニケーション能力が高い」といった抽象的な表現を、自社の業務に落とし込んで具体的に定義しておくことが重要です。
採用目標が現実的でない
採用目標として「いつまでに、何人を、どのような手法で、どの程度の予算をかけて採用するか」を設定したものの、それが現実的でない場合も採用がうまくいかない理由の一つです。
採用したいポジションにより適切な採用手法は異なります。まずは経営層や採用部門と連携し、その声をもとに目標設定することを大切にしましょう。
競合他社との差別化ができていない
さまざまな企業が採用活動を行うなか、採用計画段階で競合他社と差別化できていないことも、採用がうまくいかない要因となります。
候補者にとって自社の魅力や強みは何かを分析し、それを自社の採用サイトや求人媒体の募集ページ、採用広告などで適切に打ち出せているかどうかを見直しましょう。
採用コストの見積もりが甘い
採用コストの見積もりが甘く、思うように採用活動を進められないケースもあるでしょう。
採用活動には、求人広告費や求人媒体への成功報酬のほか、選考にかかわる人件費、内定者フォローのコストなど、さまざまな費用が発生します。求める人物像を明確にし、無駄な採用コストを削減するとともに、見えないコストも含めて余裕を持った予算計画を立てることが求められます。
社内の合意形成が不十分
ここまで述べたように、採用活動において社内の合意形成は不可欠です。そのため、社内調整がうまくいっていない場合、効果的な採用活動が難しくなる可能性があります。
人事部門だけでなく、現場の管理職や経営層を含め、全社的に採用活動を進めるという共通認識を持つようにしましょう。
採用がうまくいかない原因:採用スタート編
採用活動がスタートした後も、さまざまなことが原因で採用活動がうまくいかないことがあります。ここでは代表的な例を5つ紹介します。
採用スケジュールが曖昧
採用スケジュールが曖昧だと、優秀な候補者の内定辞退や採用目標の未達成につながります。
採用目標から逆算し、どのようなスケジュールで、どのような戦略を打つかを、計画段階で明確にしておくことが重要です。また、募集開始から候補者の入社までの詳細なスケジュールについて、関係者間で合意を取り、連携を強化することが求められます。
採用担当者の役割分担が不明確
採用活動をチームで行う場合、担当者間の役割が不明確だとスムーズに採用活動を進行できないことがあるでしょう。
新卒採用と中途採用の担当者を分けたり、応募者管理の担当者や候補者とのコミュニケーションを通じて志望度を高めるリクルーターを設けたりするなど、人事部門だけでなく社内の協力を得られる体制を構築することが必要です。
採用ブランディングが弱い
質の良い優秀な候補者を募るためには、企業の魅力や独自性を明確に伝える採用ブランディングに日ごろから注力しなければなりません。
自社の強みや価値観を整理し、ターゲット人材に向けた採用コンセプトを明確に打ち出し、候補者の視点に立ったコンテンツを設計することが重要です。
求人票の内容が魅力に欠ける
採用がうまくいかない場合、そもそも求人票に記載されている内容が魅力的でない可能性があります。「営業業務全般をお任せします」など業務内容が曖昧で具体性がなかったり、勤務時間や給与、福利厚生などの労働条件が不明確だったり、そもそも誤字脱字があったり、掲載写真が暗かったりすると、自社の魅力が十分に伝わらないでしょう。
魅力的な求人票にするためには、具体的な業務内容や成長機会、企業文化を明記するとともに、ターゲット層に響く言葉選びや、応募者目線での情報提供を心がけることが重要です。
応募者の母集団形成ができない
そもそも応募者数が少ない、面接に進む候補者が少ないなど、母集団形成ができていない場合も採用担当者の頭を悩ませる原因になるでしょう。
求人票を掲載するだけでは母集団形成には不十分です。中長期的な視点で日ごろから自社の魅力やビジョンを継続的に発信する戦略が求められます。
採用がうまくいかない原因:採用手法編
ここからは、採用手法により採用がうまくいかない原因を5つ紹介します。
採用手法がターゲット層と合っていない
そもそも採用手法が自社の採用ターゲットに合っていない場合、採用がうまくいかないことは十分に考えられます。第二新卒や若手人材を採用したいにもかかわらず紙媒体のみでアプローチしたり、地方での採用を目指しているのに都市部のみで対面説明会を実施したりしていては、効果的な採用活動は実現できません。
ターゲット層の属性や行動特性を分析し、最適な採用チャネルを選択しましょう。
複数の手法を組み合わせていない
単一の採用手法のみを使用している場合、その手法の限界や環境変化の影響を受けやすくなります。一つの求人サイトにのみ求人を掲載しているだけでは、そこに登録していない人材には出会えませんし、リファラル採用のみに頼っている場合、多様な人材の採用が難しくなります。
求人広告、エージェント、社員紹介、ダイレクトリクルーティングなど、複数の手法を戦略的に組み合わせることで、多様な人材にアプローチできるでしょう。
SNSやダイレクトリクルーティングを活用していない
認知度が限られている企業では特に、企業からの能動的な採用活動が成功の鍵となります。そのため、従来型の採用手法のみに頼り、SNSでのスカウトやダイレクトリクルーティングを活用していない場合、転職サイトを利用していない優秀層にアプローチできない可能性が高まります。
特に競争が激しい職種や専門性の高いポジションでは、能動的な採用活動へのアプローチが功を奏することも少なくありません。
採用管理システムの導入が遅れている
小規模採用を想定して手動管理を続けていたり、コスト意識から投資を控えていたりすることで、採用管理システムの導入が遅れている場合があります。しかし、これが実は採用がうまくいかない原因となっている可能性があります。
会社のフェーズは常に変化しているため、自社の規模や採用ニーズを見直し、プロセスの一部を自動化・効率化することも、有効な選択肢の一つです。
過去の採用データを活用していない
採用活動には多くのデータが蓄積されますが、これらを分析し、次の採用活動に活かせていないケースが見られます。そもそも採用活動の記録を体系的に残しておらず、過去の採用実績や成功・失敗事例の分析ができない企業もあり、この場合、応募者数や選考通過率、採用コストなど基本的な指標すらも把握するのが困難です。
継続的なデータ収集と分析を行うことで、感覚や経験則だけに頼らない科学的根拠に基づいた採用活動が可能となり、長期的には採用成功につながります。
採用がうまくいかない原因:選考編
ここからは、選考段階で採用がうまくいかなくなる5つの原因を解説します。
面接官のスキル不足
まず、面接官のスキルや経験が不足しているケースです。質問力だけでなく、限られた時間内で面接の流れをコントロールする運営スキルや、逆質問の機会を通じて自社の魅力を伝える力、さらに選考基準に対する理解が不足している場合も含まれます。
面接官へのトレーニングやガイドラインの整備、定期的なフィードバック、面接官同士の情報共有などを通じて、スキルの向上を図ることが求められます。
面接や選考の基準が統一されていない
選考基準が定められていなかったり、面接官によって選考基準の理解に差があったりする場合、公平で一貫性のある評価が難しくなります。
職種・職位ごとに求められるコンピテンシーやスキルセットを明確に定義し、構造化された評価シートを作成することで、各評価項目の定義と評価基準が明確になり、一貫性のある選考につながるでしょう。
応募者へのフィードバックが遅い
応募者へのフィードバックや次のステップの案内が遅れると、応募者は不安を感じたり、他社の選考を優先したりする可能性があります。その結果、自社の選考辞退や内定辞退につながり、思うように優秀な人材を確保できないことがあるでしょう。
スムーズな選考が進められているかを見直し、そのうえで各選考段階での通過連絡やフィードバックのタイミングを明確に設定し、迅速に対応することが重要です。
選考プロセスが長すぎる
応募から内定までに2ヶ月以上かかったり、書類選考の結果連絡に2週間以上かかったりと、選考プロセスが長すぎると応募者のモチベーション低下や途中離脱のリスクが高まります。
特に優秀な人材ほど複数社から内定を得やすいため、選考プロセスの長さは採用競争力に直結します。応募から内定までの全プロセスを1ヶ月以内に収める、各選考段階の結果連絡は3〜5営業日以内に行うなど、具体的な目標を設定することで、応募者のモチベーションを維持し、競合他社に先んじた採用を目指しましょう。
求職者の志望度を上げる工夫がない
選考は企業が応募者を評価するプロセスであると同時に、応募者が企業を評価するプロセスでもあります。
そのため、応募者の質問に丁寧に答える、前回の面接のフィードバックを伝える、面接官自身のキャリアや経験を共有するなど、応募者の入社意欲を高めてもらえるように工夫しましょう。
採用がうまくいかない原因:内定フォロー編
採用活動の最終段階である内定フォローにおいて、採用がうまくいかなくなる4つの原因を解説します。
内定者とのコミュニケーションが不足している
場合によっては、内定を出してから入社までに数ヶ月の期間が空くことがあるでしょう。その間に内定者とのコミュニケーションが不足すると、入社にあたっての不安や疑問が解消されず、内定辞退のリスクが高まります。
定期的な連絡や情報提供を行うことはもちろん、内定者の個別の懸念や質問に丁寧に対応することが重要です。また、内定者同士の交流を深める内定者懇親会や、社員とのコミュニケーション機会を設けるのも効果的です。
内定辞退のリスクを軽視している
内定辞退が発生すると、採用活動全体の効率が大きく損なわれます。しかしながら、そのリスクを軽視している企業も少なくありません。
内定辞退時の対応策がない、そもそも内定承諾の確認が不十分、入社前研修プログラムや入社前のフォロー体制が不足しているといった要因が重なると、内定辞退の可能性が高まります。これらのリスクを分析し、予防策を講じることが重要です。
企業文化や社風を伝える機会がない
選考プロセスが形式的になっていたり、社員の生の声に触れる機会がなかったりすると、企業文化や社風を十分に伝えられず、入社後に「思っていた会社と違う」というリスクが高まります。
選考プロセスの早い段階から内定に至るまで、さまざまな接点を通じて一貫したメッセージを発信し続けることで、応募者が企業文化を理解し、入社後のギャップを減らすことができます。
入社前研修や懇親会を実施していない
入社前研修や懇親会を実施していない場合、入社初日からの不安や戸惑いが大きくなり、場合によっては手厚いフォローを受けた別企業へ入社の意思決定をしてしまうことがあるかもしれません。
入社前研修プログラムを整備し、同期入社者や配属予定部署のメンバーとの交流機会を設けて入社前の不安や疑問点を解消するなど、スムーズに就業できる環境を整えましょう。
御社の採用業務を副業社員に任せてみませんか?
この記事では、採用計画、採用スタート、採用手法、選考、内定フォローの5つのフェーズに分けて、採用がうまくいかない24の原因を解説しました。採用活動には専門知識や経験が求められ、これらの問題点をすべて自社で解決するのは容易ではありません。
「採用領域に課題を感じているが、採用領域のプロが社内にいない…」そのような企業では、副業人材の活用を検討するのも一つの方法です。『lotsful』は、初期費用0円で始められる副業人材とのマッチングプラットフォームで、即戦力ビジネス系職種に特化したデータベースを持っています。
案件作成や人材探し、契約手続きなどは『lotsful』で対応するエージェント型サービスを採用しており、これにより案件作成や契約手続きなどの工数の削減にもつながります。
リソースが足りない、正社員採用よりもスピーディーに現場ニーズを満たしたい場合など、人的リソースに課題を抱える企業の皆さまは、ぜひ『lotsful』の活用をご検討ください。