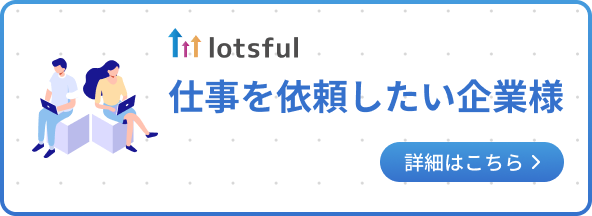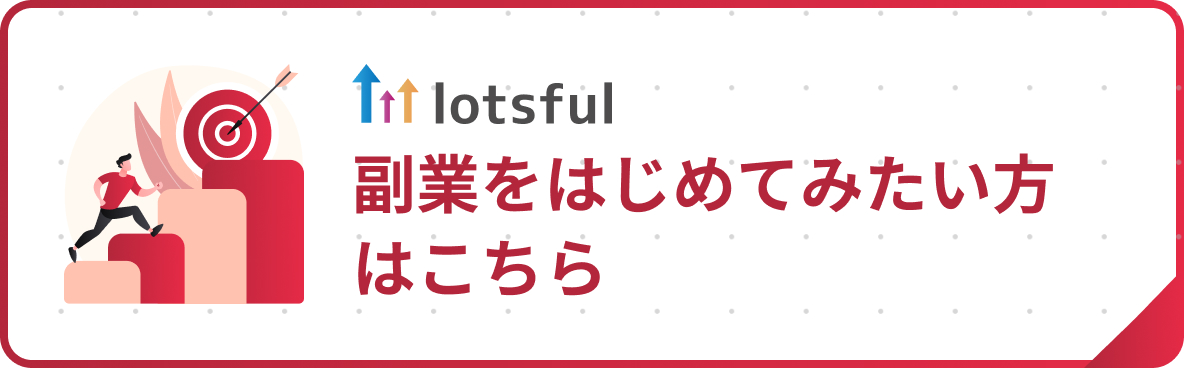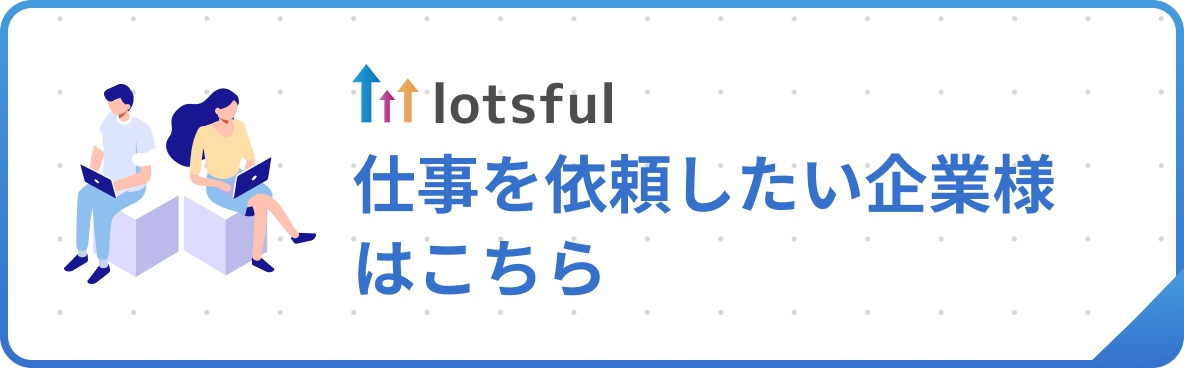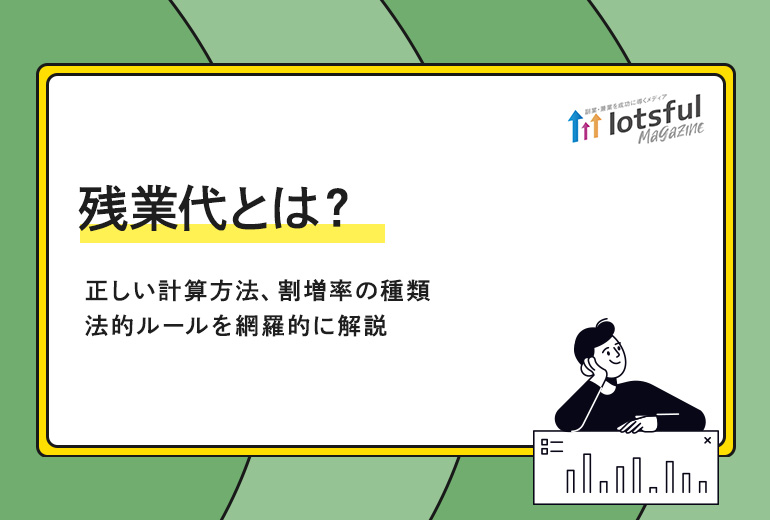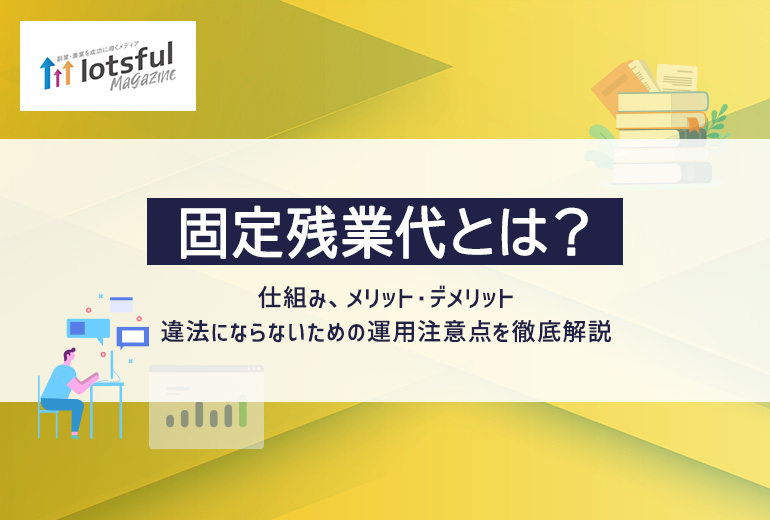新卒採用基準の決め方、具体例を注意点とともに解説
企業にとって新卒採用基準の設計が重要な理由は、学生を確保するための判断材料となるだけでなく、組織の中長期的な成長にもつながるためです。また、明確な採用基準の設計は、副業社員を獲得する際にも非常に役立つでしょう。
そこで本記事では、新卒採用基準の決め方や具体例、注意点などについて解説します。さらに、中途採用基準との違いにも触れておりますので、ぜひ御社の採用活動にお役立てください。
新卒採用で採用基準が重要な理由
新卒採用において明確な採用基準の設計が重要な理由としては、以下の4点が挙げられます。
経験が乏しい新卒は、ポテンシャルや人柄の見極めが特に重要
新卒者である学生は、正社員としての職務経験を持っていません。このため、履歴書や面接だけで適性やスキルを判断することは難しいといえるでしょう。
学生の経験値ではなく、「ポテンシャル」「人柄」「価値観」などを見極めることにより、自社文化にマッチした人材の採用が実現します。
判断軸がないと選考が主観的になり、評価がばらつく
新卒採用時に明確な判断軸が存在しない場合、選考が採用担当者の主観に左右されやすくなります。その結果、候補者の評価にばらつきが生じ、ミスマッチな採用を招くおそれがあります。
自社がどのような人材を求めているかを明確にし、具体的な判断軸を設定することで、一貫性のある公平な選考が実現できるでしょう。
採用のミスマッチを防ぎ、早期離職リスクを軽減できる
採用基準が明確に設計されていない場合、自社が求める人物像と新卒者の適性が合わず、ミスマッチが発生しやすくなります。それにより、早期離職のリスクが高まります。
長期的に活躍できる人材を見極めるには、「スキル」「志向」「価値観」といった要素を具体化して採用基準に盛り込むことが重要です。これにより、採用時のミスマッチ防止と早期離職のリスク軽減が可能になります。
面接官間の共通認識ができ、選考の一貫性が保たれる
新卒採用において明確な採用基準を設計することにより、面接官の間で「どのような人材を採用すべきか」について共通認識を持つことができます。
各面接官の判断軸が統一されるため、評価基準にぶれが生じることなく、公平かつ一貫した選考が実現するでしょう。
新卒採用の採用基準の決め方
新卒採用における採用基準の決め方として、以下の5つを実践することをおすすめします。
自社のミッション・ビジョン・価値観を整理する
新卒採用で最初に取り組むべきことは、自社の「ミッション(Mission)・ビジョン(Vision)・価値観(Value)=MVV」を整理することです。そのうえで、明確になったMVVに基づいて採用基準の設計を行いましょう。
自社のMVVに共感しながら行動できる新卒者を採用することで、長期的な活躍が期待できるだけでなく、組織の強化や成長にもつながります。
活躍している若手社員の特徴や行動を分析する
既に自社で活躍している若手社員の特徴や行動を詳細に分析し、その結果に基づいて採用基準を設計することは、新卒採用の効果を高めるうえで非常に有効です。
新卒者と立場の近い人材に共通する要素を探り当てることで、「抽象的な優秀さ」ではなく、自社にとって最も適切かつ具体的な人物像が見えてくるでしょう。
MUST(必須)/WANT(望ましい)条件に分けて整理する
新卒の採用基準の決め方として、「必須条件(MUST)」と「望ましい条件(WANT)」を明確に分けて整理しておくのが理想的です。
また、これらの条件は一律ではなく、ポジションや育成方針に応じて柔軟に設計する必要があります。新卒者に求める条件を適切に分類しておくことで、採用のスピードが向上するだけでなく、質の高い選考も可能になります。
評価項目ごとの定義と判断基準(レベル感)を設定する
新卒採用において、評価項目ごとの定義やレベル感といった判断基準を設定することが、選考の一貫性と質の向上につながります。
たとえば、主体性の高い人材を求めている場合、採用担当者によってその解釈は異なる可能性があります。「何をもって評価するか」という具体的かつ共通の定義があれば、候補者の見極め精度は格段に向上するでしょう。
面接官や関係者と基準を共有し、すり合わせを行う
新卒採用では、自社文化や成長戦略に基づく明確な採用基準の設計はもちろん、面接官や現場関係者との認識のすり合わせも、成果を左右する重要な工程です。
採用基準が共有されていない場合、現場が求める人物像とは異なる人材を採用してしまう可能性があります。このような事態を回避するためにも、面接官と関係者の間でミーティングを実施し、情報と意識のすり合わせを行っておきましょう。
新卒採用の採用基準の具体例
新卒採用基準の具体例として、以下の7項目を紹介します。
素直さ・吸収力があるか
新卒採用では、即戦力としての期待ではなく、入社後にどれだけ成長できるかを見極めることが重要です。素直に物事を学び、吸収できる人材は、組織への適応力も高く、今後の伸びしろも大きいといえるでしょう。
候補者の素直さや吸収力の有無を確かめるには、面接時に「他者から指摘されたことで印象に残っていること」や「過去の成功例だけでなく、失敗にどのように対応したか」などの質問が効果的です。
主体的に行動できるか
他者からの指示を待つのではなく、自ら課題を見つけて主体的に行動できる人材は、入社後の成長スピードが早く、業務や環境の変化にも柔軟に対応できるでしょう。
候補者の主体性を見極めるには、過去の経験をもとに「Situation(状況)」「Task(課題)」「Action(行動)」「Result(結果)」の4要素に沿って話を聞くSTAR法の活用が有効です。学生時代などに自ら行動し、成果を出した経験を具体的に質問してみましょう。
チームでの協調性・コミュニケーション能力があるか
チームでの協調性やコミュニケーション能力は、組織ではたらくうえで基本的かつ重要なスキルといえるでしょう。チーム内で良好な関係を築ける人材は、組織に早く馴染めるだけでなく、周囲と協力しながら業務を進められるため、成長スピードも期待できます。
候補者の協調性やコミュニケーション力を確かめるには、グループディスカッションなどを通じて、他者の意見をどう傾聴しているか、また意見をどうまとめているかといった「人との関わり方」をチェックすることをおすすめします。
企業の理念や文化に共感しているか
新卒者の早期離職の原因の一つとして、担当業務そのものよりも、企業の理念や文化に共感できないなど、価値観の不一致が挙げられます。カルチャーフィットした人材は、業務においても高いパフォーマンスを発揮しやすくなります。
候補者の共感度を見極めるには、面接時に自社の理念や文化についての印象などを質問し、回答が候補者自身の価値観とどのように結びついているかをチェックしましょう。
論理的に物事を考える力があるか
自身に与えられた課題の構造を理解し、論理的に筋道を立てて考えられる人材は、業務スピードだけでなく、質の面でも優れている傾向があります。
候補者が論理的に物事を考える力があるか見極めるには、「ある製品の売上が伸び悩んでいる原因はなにか」などの具体例を交えた質問をすることで、根拠に基づいた仮説を立てて説明できるかどうかの思考力を判断することができるでしょう。
学業や課外活動での継続的な努力や成果があるか
業務において成果を上げるためには、継続的な努力が不可欠です。このため、学生時代からコツコツと地道な努力を続けて成果を出した人材は、入社後に困難な場面に直面しても、それを乗り越えられることが期待できます。
候補者の学業や課外活動について質問する際は、単なる継続の事実だけではなく、「目的意識や成長の実感があるか」に重点を置くことをおすすめします。
挑戦心・向上心があるか
常に挑戦心や向上心をもって物事に取り組む人材は、組織という環境にも早く適応し、活躍することが可能です。一方、受け身型の人材では、成長スピードに差が出てしまう傾向があります。
候補者に挑戦心や向上心があるかを見極めるには、過去の挑戦経験だけでなく、現在取り組んでいることについても、その過程や工夫した点などを含めて質問してみましょう。
新卒採用の採用基準設計時の注意点
新卒採用の採用基準を設定する際は、以下に挙げる6つの注意点があることを認識したうえで、具体的かつ柔軟性のある基準を設けることが重要です。
ポテンシャルを重視する
新卒採用において学生のポテンシャルを重視することは、非常に賢明な選択といえるでしょう。たとえ難関校出身や業務に直結する専攻学科出身であっても、自社との相性が良いとは限りません。
ただし、ポテンシャルといっても企業ごとに評価軸が異なるため、あらかじめ明確な定義づけを行っておく必要があります。さらに、ポテンシャルのみに偏らない、バランスの取れた採用基準の設計が求められます。
評価基準を言語化する
新卒採用における評価基準では、学生が持つ基礎力に加えて、ポテンシャルや将来性といった「伸びしろ」も重要です。この将来性を感覚に頼らず、言語化しておくことで、より適切に候補者を見極めることが可能になります。
たとえば、主体性や学習意欲がある人材を採用したい場合は、「自発的に学ぶ姿勢があるか」「課題を自ら設定し、学んだことを行動に移した経験があるか」といった、具体的な評価項目に落とし込むことが重要です。
評価シートやガイドを整備する
新卒者のポテンシャルや人柄など、採用担当者によって解釈が分かれやすい資質を公平に評価するには、評価シートやガイドの整備が必要不可欠です。
一貫性と客観性を兼ね備えた評価シートや、質問項目が明示されたガイドを用意することで、採用担当者の主観に頼らない評価を実現できます。
高すぎる基準を設けすぎない
優秀な人材を確保したいあまり、高すぎる採用基準を設定してしまうと、多くの学生が条件を満たせず、結果として採用ゼロという結果につながりかねません。
また、運よく基準を満たす人材を採用できたとしても、期待値と現実のギャップが大きい場合、早期離職につながるリスクがあるため注意が必要です。
現実的な基準を設計する
理想像を追い求めて、あまりに高い採用基準を設定してしまうと、新卒採用そのものが機能しなくなる可能性があります。新卒者である学生は職務経験がなく、業務におけるスキルも未知数です。
そのため、自社ではたらく若手社員と比較して、「どの程度の資質があれば無理なく活躍できるか」を踏まえた、現実的な基準設計を行うことが重要です。これにより、スムーズな新卒採用の実現が期待できます。
時代や学生の傾向に合わせて柔軟に見直す
学生の行動や価値観は、時代の流れとともに変化します。たとえば、現在の学生の多くは、上位のポジションを目指して残業を厭わずに努力するよりも、「ライフワークバランスの取れた柔軟なはたらき方」や「安定性」を重視する傾向にあります。
このような背景から、体育会系的な価値観や過度な積極性を求めすぎてしまうと、応募数や採用結果に悪影響を及ぼす要因にもなります。また、DX(デジタルトランスフォーメーション)化やリモートワークの推進など、職場環境の変化に対応するためにも、柔軟性の高い採用基準の見直しは欠かせません。
新卒採用基準と中途採用基準の違い
「新卒採用基準」と「中途採用基準」では、どのような点に違いがあるのでしょうか。以下で、それぞれの違いについて解説します。
新卒採用基準:ポテンシャル・人柄・文化適応力を重視する
新卒採用と中途採用では、求める人物像と評価点に明確な違いがあります。
新卒採用では、候補者に企業での職務経験がないため、即戦力としての能力ではなく、育成や長期的な活躍を視野に入れた採用が必要になります。
このため、自社の将来を担う存在として、「ポテンシャル」「人柄」「企業文化への適応力」といった観点を重視した新卒採用基準を設定しましょう。
中途採用基準:即戦力性・スキル・業務経験を重視する
一方、中途採用では、候補者のこれまでの経験やスキルに基づき、入社後早期から自社の売上貢献や組織拡大を担える人材が求められます。ここが、新卒採用との大きな違いです。
したがって、中途採用基準に関しては、短期間で成果を出してもらうことを前提に、「即戦力性」「スキル」「業務経験」を重視した採用基準の設計が不可欠です。
御社の業務に副業社員を検討してみませんか?
今回は、新卒採用時に採用基準の設計が重要な理由をはじめ、その注意点を踏まえた有益な情報をお届けしました。
新卒採用・中途採用に限らず、明確な採用基準の設計と、目的に適した採用チャネルの選択は、成果を左右する重要なポイントといえるでしょう。
採用業務の課題を、なるべくコストや工数をかけずに解決したいなら、副業人材マッチングサービスの「lotsful」へお気軽にご相談ください。
御社の希望に見合った優秀な副業社員との出会いが、初期費用をかけずに叶うのが「lotsful」の魅力です。従来型の採用チャネルよりスピード感がある点も、大きな特徴といえるでしょう。ぜひ「lotsful」を、御社の採用業務の質向上にお役立てください。
関連記事
・新卒採用と中途採用の違いとは?特徴・メリットデメリットを比較
・企業が新入社員に求めることとは?新卒・中途別まとめ