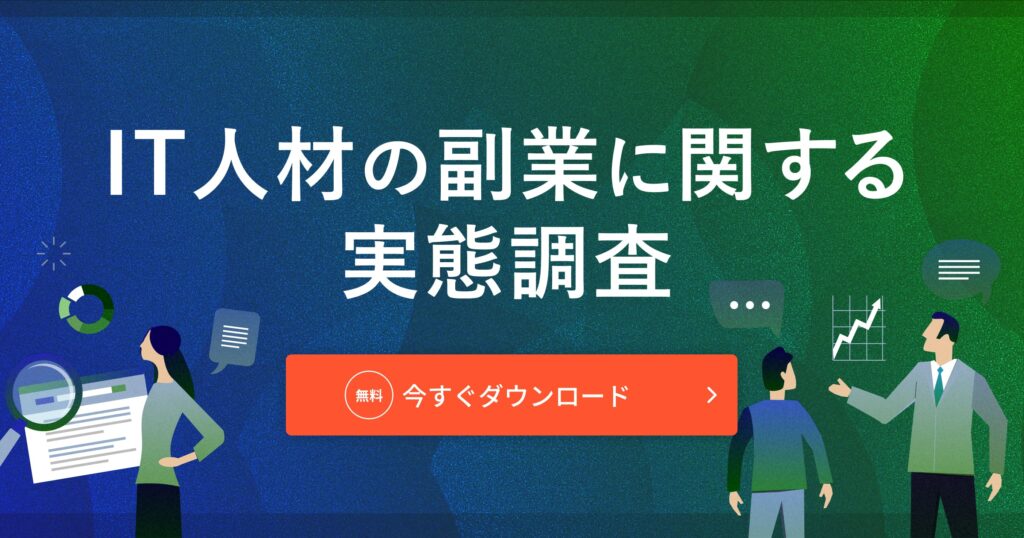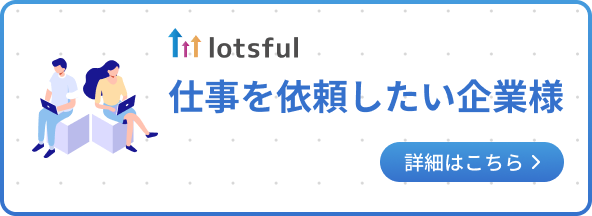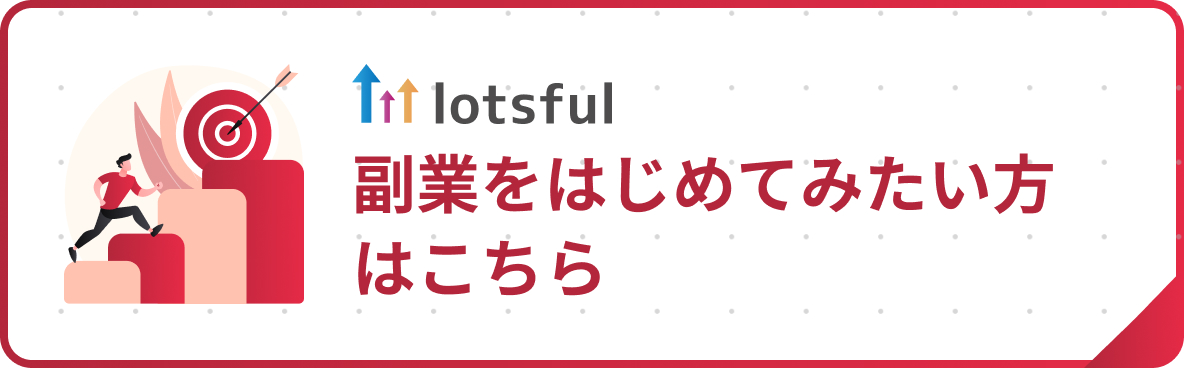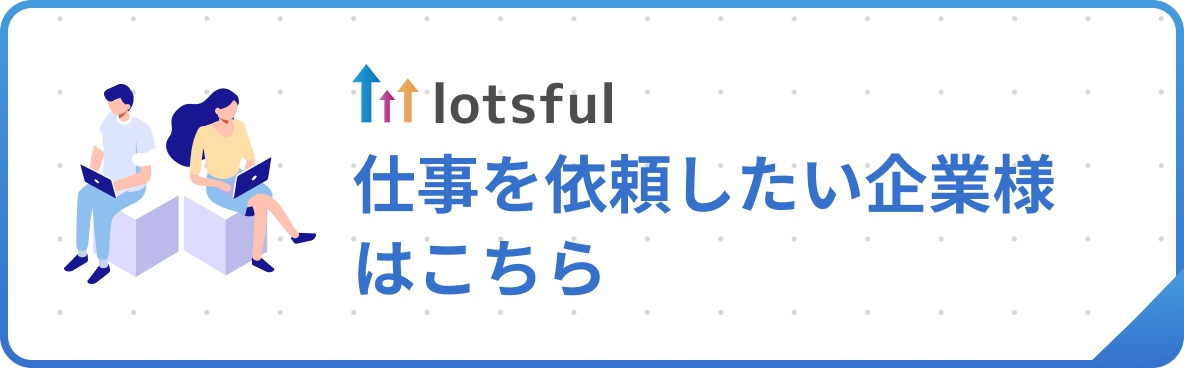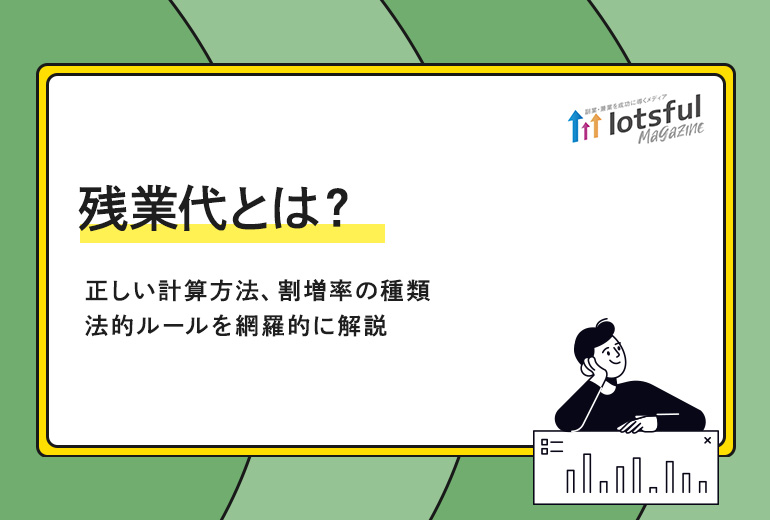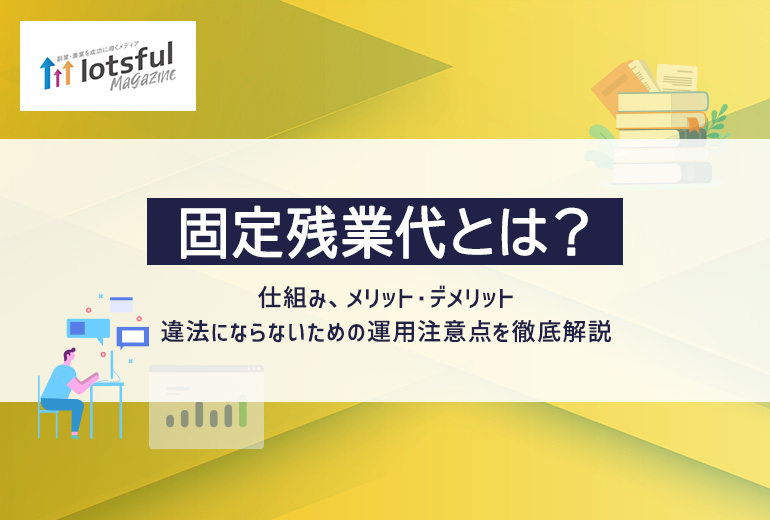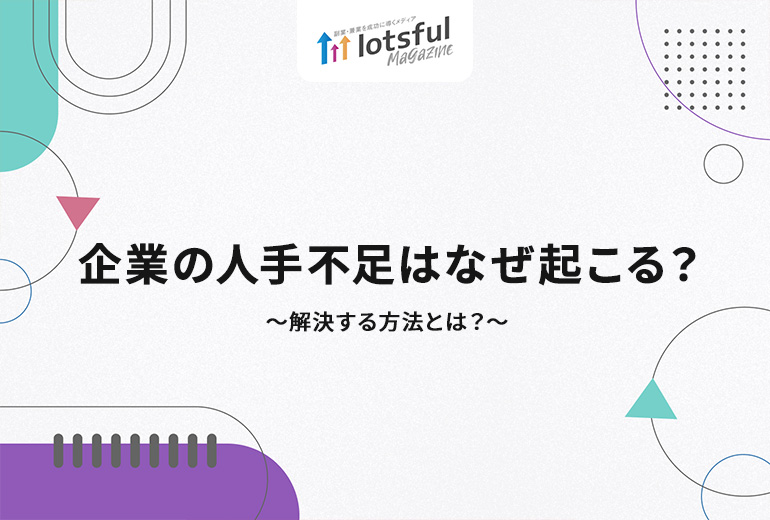
企業の人手不足はなぜ起こる?解消する方法とは?
2010年ごろから、多くの企業が人手不足に頭を悩ませています。この記事では、日本における人手不足の原因や背景を確認したうえで、人手不足が企業に及ぼす影響を解説し、企業が人手不足を解消するために取り組むべき対策や方法の事例を紹介します。
また、採用業務においては、副業人材を活用するという選択肢もあります。詳しくは記事の最後をご覧ください。
- 最も人材が不足しているIT職種は「データサイエンティスト・アナリスト」
- 業務委託人材を活用したことがある企業が47.4%
- 業務委託人材との取り組みで「成果が出た」企業が86.7%
日本における人手不足の原因と背景
日本で深刻化する人手不足の原因と背景には、さまざまな要因が関わっています。
まず、少子高齢化による生産年齢人口の減少が原因として挙げられます。日本は、世界的に見ても急速に少子高齢化が進行している国の一つです。実際に、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少を続け(※1)、2024年には7,372万8,000人となっています(※2)。
また、産業構造の変化も人手不足に拍車をかけています。2025年1月時点で、正社員不足を感じている企業は53.4%にのぼります。特に、ITやAI技術の進展に伴う産業構造の変化により、情報サービス業界のシステムエンジニア不足が最も深刻であり、人手不足の割合は業種別でトップの72.5%となっています(※3)。
これらの社会的な変化に加え、若年層の仕事に対する価値観の変化も人手不足に関係しています。はたらきやすさや自身の成長機会を重視する傾向が強まり、これまで以上に転職に対して肯定的な考えを持つ若年層が増えています。そのため、企業にとっては優秀な人材を確保し、中長期的に育成することが一層困難になっているのが現状です。
※1出典:内閣府『令和4年版高齢社会白書 第1章高齢化の状況』
※2出典:総務省統計局『人口推計(2024年(令和6年)10月確定値、2025年(令和7年)3月概算値)』
※3出典:帝国データバンク『人手不足に対する企業の動向調査(2025年1月)』
人手不足が企業に及ぼす影響
人手不足は企業にさまざまな影響を及ぼします。ここからは、その例を3つご紹介します。
労働環境の悪化
人手不足の状態が続くと、既存の従業員の業務負担が増加し、長時間労働が常態化するリスクがあります。休暇が取りづらくなり、ワークライフバランスが崩れることで、従業員の心理的ストレスが蓄積し、メンタルヘルスの悪化を招く可能性があります。
また、目の前の業務をこなすことが優先され、従業員の成長やスキルアップのための時間が確保できなくなると、モチベーションの低下を引き起こします。このような状況が続くと、職場の雰囲気が悪化し、チームワークや組織の一体感の低下につながるでしょう。
離職リスクの高まり
労働環境が悪化すると、既存社員の離職リスクが高まります。1人が退職すると、残された従業員の負担がさらに増加し、それに耐えられなくなった人が次々と退職する「離職ドミノ」の現象が発生することもあります。
特に若手社員や優秀な人材ほど転職市場での価値が高く、労働環境の悪化を理由に早期退職する傾向があります。こうした人材の流出は、企業の競争力低下につながるでしょう。
売上の低下
リソース不足は、さまざまな観点で企業の売上を低下させる要因になりえます。たとえば、人員不足により品質管理に十分なリソースを割けない場合、商品・サービスの質や生産性の低下を招き、最終的には売上の減少につながります。
製造業やサービス業では、納期に間に合わせる人員が不足しているために受注を断ったり、新規案件の獲得を見送らざるをえない状況が発生し、売上損失の要因となるでしょう。企業として新規事業や拡大計画の延期・中止を余儀なくされるケースが増えると、企業の成長戦略全体に影響を及ぼします。
人手不足を解消する方法
ここからは、人手不足を解消するために企業が取り組むべき方法を12個紹介します。
給与や福利厚生の見直し・向上
競争力のある給与水準と魅力的な福利厚生は、優秀な人材を確保するために重要な要素です。社会の流れや競合他社を踏まえ、自社の報酬体系を定期的に見直すようにしましょう。
通勤手当や住宅手当の付与、自己啓発支援や補助、健康・運動を促進する制度など、給与面以外でも社員が健康的にモチベーション高くはたらける福利厚生を充実させることも、中長期的に社内で活躍してもらうために重要です。
柔軟なはたらき方の導入(リモートワーク、フレックスタイムなど)
多様なはたらき方を受け入れることで、社員のはたらき方に対する満足度向上につながるほか、より幅広い採用ターゲットにアプローチできるでしょう。
たとえば、リモートワークやフレックスタイム制を導入すると、育児や介護と仕事の両立を支援できます。また、「平日のお昼に1時間だけ用事があるが、丸一日休みを取るほどではない」といったケースでも柔軟に対応できるため、個々人のライフスタイルに合わせたはたらき方を提供できます。
採用プロセスの効率化
そもそも採用プロセスのどこかに課題があるケースもあります。応募から選考、内定までのプロセスを見直し、効率化しましょう。
選考期間が長期化していることで候補者の志望度が低下していないか、入社前に候補者と十分にコミュニケーションが取れているか、疑問は解消できているかなど、プロセスごとに見直すと良いでしょう。選考段階での優秀な人材の流出を防ぎ、採用成功率を高めることができます。
多様な人材の積極的な採用(女性、高齢者、外国人など)
今後、国内で人手不足は加速します。従来の採用基準や固定観念にとらわれず、多様な人材の採用を検討することも重要です。
女性の管理職登用やシニア層の経験を活かした再雇用、外国人材の受け入れなど、さまざまな選択肢があります。多様性を受け入れる組織文化の醸成が前提となりますが、異なる視点や経験を持つ人材が社内に増えることで、イノベーションが促進される可能性もあるでしょう。
従業員のスキルアップやキャリア開発支援
モチベーションを維持し、自社で長く活躍してもらうためには、既存社員のスキル向上やキャリア開発を支援することが大切です。スキルアップ研修やeラーニングの提供、資格取得費用の会社負担など、従業員の成長を促す取り組みが有効です。
定期的に社員との1on1ミーティングを設けるなど、社員が会社で実現したいことやチャレンジしたい仕事をヒアリングして把握したり、社内でのキャリアパスや成長ビジョンを共有したりすることも重要です。
職場環境の改善とはたらきやすさの向上
物理的な職場環境の改善は、はたらきやすさの満足度に直結します。コミュニケーションを促進するオープンエリアと集中ブースを分けたフリーアドレス制の導入や、仕事の息抜きができるリフレッシュスペースの設置など、社員が快適に生産性高くはたらける環境を整えましょう。
また、ハラスメント対策など心理的安全性の確保も重要です。ハラスメントに対する定期的な研修の実施やガイドラインの整備に加え、問題が発生した際に相談できる窓口を設置するのも有効です。
従業員エンゲージメントの強化と定着率向上策
従業員のエンゲージメントを強化する施策を行うのも一つの方法です。高いエンゲージメントを持つ従業員は、単に楽しくはたらいているだけでなく、会社の目標達成に向けて自発的に努力し、長期的に組織貢献したいと考える傾向があります。そのため、企業にとっては生産性向上、離職率低下、顧客満足度向上などの具体的なビジネス成果につながると考えられています。
具体的な施策としては、上司と部下の1on1ミーティングなど定期的なコミュニケーションの実施、透明性の高い評価制度や表彰・報奨制度の整備などの充実、ジョブローテーションなど成長機会の提供のほか、社員満足度調査の実施などが挙げられます。
業務の自動化やITツールの導入による効率化
ITやAI、ロボティクスなどのテクノロジーを活用し、定型業務を自動化することで、限られた人材をより創造的・戦略的な業務に集中させる工夫も必要です。
たとえば、経理業務の自動化や一部ペーパーレス化、顧客対応におけるチャットボットの導入、社内申請のワークフロー化など、さまざまな業務で効率化が可能です。
パートタイムや契約社員の活用
正社員だけでなく、パートタイム、契約社員、派遣社員など、さまざまな雇用形態の人材を採用することで、業務の繁閑に応じた柔軟な人員配置が可能になります。特に、季節変動のある業種や、特定の期間だけで人手が必要な業種においては有効な選択肢の一つです。
インターンシップや新卒採用の強化
将来的に経営層を担う人材を早期から育成するという観点から、インターンシップや新卒採用に力を入れることも重要です。
近年、就職活動の前にインターンシッププログラムに参加する学生が増えており、企業との重要な接点となっています。一定期間、自社と深く関わる機会を設けることで、学生に自社の魅力を伝えられるだけでなく、お互いのミスマッチを防ぐことにもつながります。
社内コミュニケーションの活性化とチームビルディング
風通しの良い組織文化を構築し、部門間の連携を強化することは、活気ある職場づくりのみならず、中長期的には企業の成長にも影響を与えます。具体的な施策として、定期的な全社ミーティングや部門間交流イベントの開催、メンター制度の整備などの取り組みが考えられます。
近年、リモートワーク環境下では、チャットツールの活用、オンラインランチ会の開催、会議中の少人数ブレイクアウトセッションなど、コミュニケーションツールを活用したチームワーク構築の工夫が求められています。
外部リソースの活用(アウトソーシング、派遣社員など)
自社のコア業務に集中し、それ以外の業務に外部リソースを活用することは、人材不足問題に対して即効性のある対策の一つといえるでしょう。ルーティーンワークや事務作業だけでなく、専門性の高い業務や一時的なプロジェクトにも外部の専門家を活用することで、効率的な業務遂行が可能になります。
御社の採用業務を副業社員に任せてみませんか?
この記事では、日本で深刻化する人手不足の原因と背景を確認し、企業に及ぼす影響を解説しました。さらに、給与や福利厚生の見直し、柔軟なはたらき方の導入、業務効率化、多様な人材活用など、人手不足を解消するために企業が取り組むべき施策についても紹介してきました。
「新規事業を検討しているけれど、人手が足りない…」そのような課題を抱える企業には、副業人材の活用を検討するのも一つの方法です。『lotsful』は、初期費用0円で始められる副業人材とのマッチングプラットフォームです。転職市場ではなかなか出会えないノウハウを有する優秀な人材が多数登録しています。
また、経験豊富なコンサルタントがオンボーディングや受け入れ後の体制構築まで伴走するエージェント型サービスを採用しており、案件作成や契約手続きなどの工数削減が可能です。
専門領域のプロが社内に不足していて新規事業のアクセルを踏めない、手を動かせる人材が不足しているなど、人的リソースに課題を抱える企業の皆さまは、ぜひ『lotsful』の活用をご検討ください。