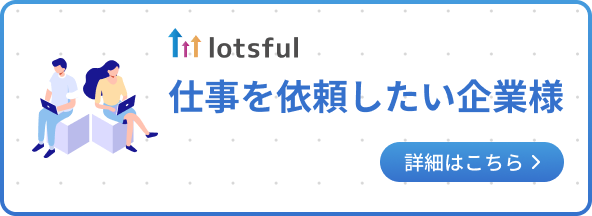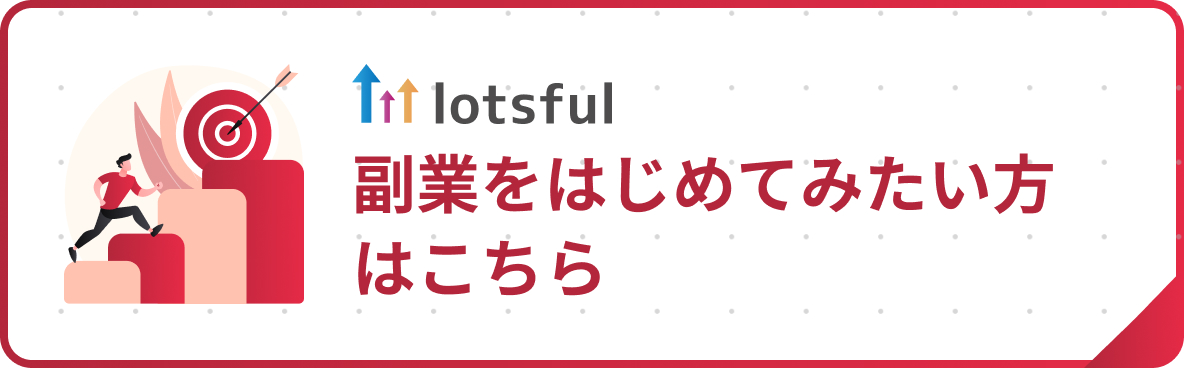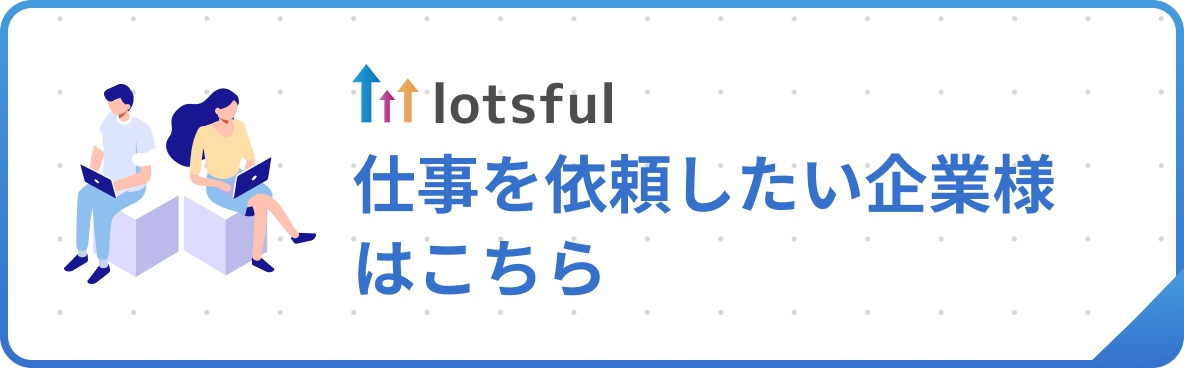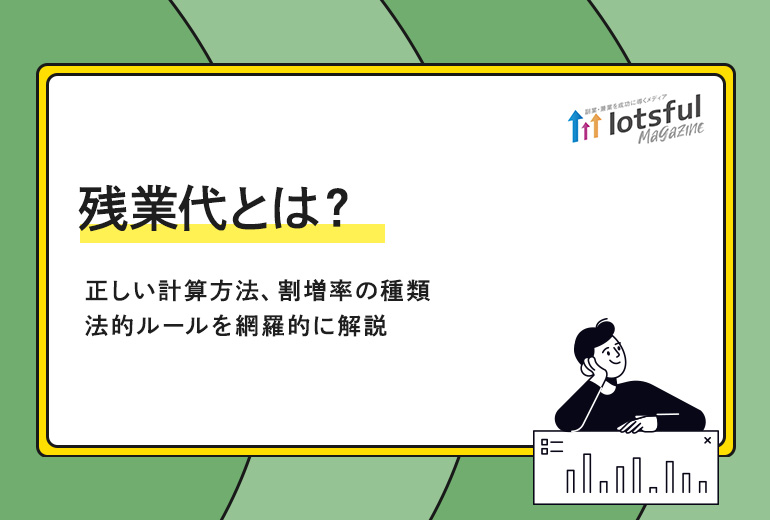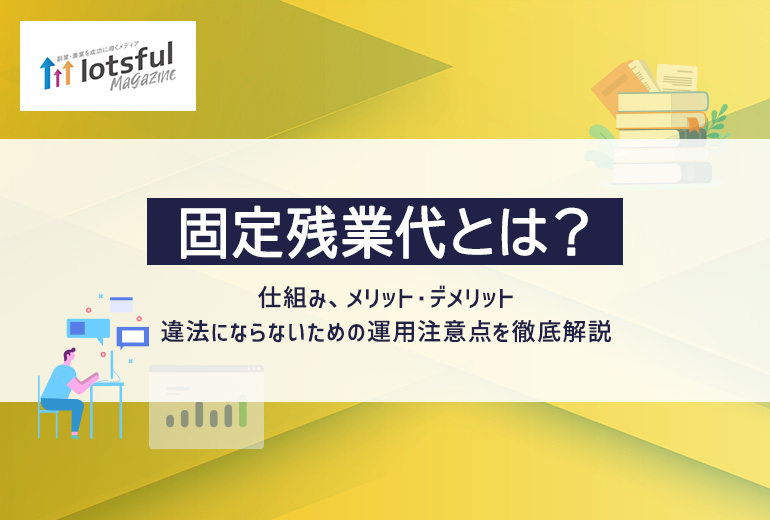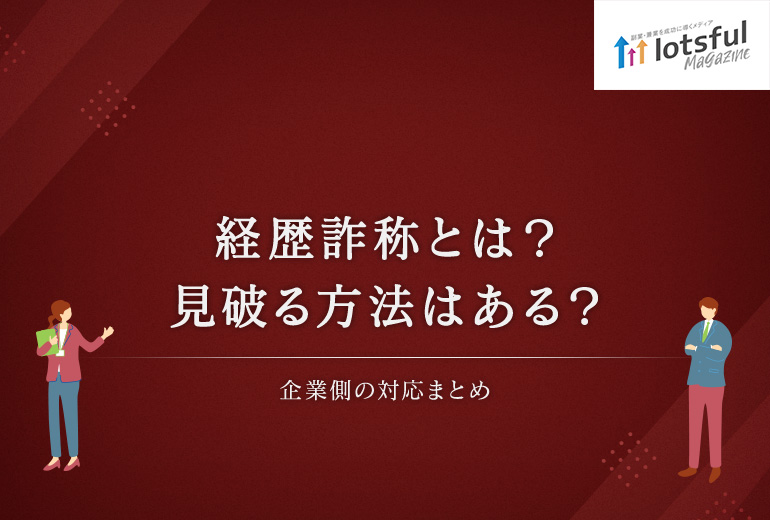
経歴詐称とは?見破る方法はある?企業側の対応まとめ
就職や転職活動を有利に進めるために、応募先企業に対して自身の学歴や職歴などを偽る行為を経歴詐称といいます。
正社員だけでなく、副業社員の獲得時にも経歴詐称をした応募者を採用した場合、企業にとって不利益となる人材採用を行ったことになります。
今回は、経歴詐称に該当する項目をはじめ、見破る方法や企業が取るべき対応について詳しく解説します。
経歴詐称とは
経歴詐称とは、自身の学歴や職歴、所有資格などを偽る行為を指します。経歴詐称を行う背景としては、採用に不利な条件を隠し、内容を誇張することで有利に進める目的があります。
応募者による経歴詐称は、新卒採用や中卒採用いずれにおいても発生する可能性があります。特に、即戦力としてより高いスキルや経験値が求められる中途採用では、多い傾向にあるでしょう。
詐称の程度には差があるものの、経歴詐称をした人材の採用は企業にとって大きなリスクをもたらします。
場合によっては、内定取り消しや懲戒解雇だけでなく、軽犯罪法違反や私文書偽造罪に問われるケースもあります。企業としては、応募者の経歴詐称に関する事前対策が急務といえるでしょう。
経歴詐称になり得る項目
応募者が自身の情報を偽るにあたり、経歴詐称になり得る可能性の高い項目として、以下に挙げる8つが代表的です。
学歴
高卒であるにも関わらず大卒と偽る、あるいは出身校ではない大学名を名乗る学歴の詐称は、経歴詐称の中でも多い事例といえるでしょう。
たとえば、企業が提示する応募条件を大卒以上としていた場合、選考を有利に進めるために、学歴を偽るケースがあります。
職歴
中途採用者の場合、これまでどのような企業で、どのような職務を担っていたかは、採用の可否を判断する重要な要素になるでしょう。
職歴に関する詐称としては、実際に勤務していない企業名や従事していない職務名を挙げる、あるいは役職・雇用形態を偽ることが該当します。
また、自身の職歴に何らかの事情でブランクがある場合、転職において不利になると考える応募者も少なくありません。このため、一部の応募者は、入社日や退社日、勤続年数を偽ってしまうケースがあります。
年収
転職をする際、前職の年収額が高ければ、年収交渉が有利に進む場合があります。少しでも多くの年収を得たいという気持ちから、前職での年収額を多めに申告するケースも詐称にあたります。
企業側が年収額の詐称を見破る方法として、中途採用者が年末調整時に提出する前職の源泉徴収票でチェックすることが可能です。
資格・免許
日商簿記、TOEIC、普通自動車免許といった資格や免許は、募集職種上必要とされる場合があります。また、それらの資格や免許を所持していることで、採用後に手当が支払われることもあります。
資格や免許に関する詐称は、実際には取得していないにもかかわらず所持していると偽る、あるいはスコアを誇張することで、選考通過や手当を得るケースが考えられます。
業務内容
実際には携わっていなかった業務内容を偽ることも、経歴詐称に該当します。
たとえば、実際にはサポート業務に携わっていたにもかかわらず、主要なポジションとして重要な業務を任されていたと主張することが、業務内容に関する詐称にあたります。
業務内容に関する虚偽を見抜くには、面接での具体的な質問やリファレンスチェック、試用期間を通じて真偽を確認することが重要です。
雇用形態
パートやバイト、契約社員での勤務経験を、正社員として申告することも詐称に該当します。
雇用形態の詐称を見抜くため、在職中の応募者には在籍証明書を、退職済みの応募者には退職証明書の提出を求めると良いでしょう。また、前職へのリファレンスチェックも有効な手段です。
提出された証明書の確認やリファレンスチェックにより、応募者の実際の雇用形態を確認することができます。
病歴
病歴に関する詐称の中でも、メンタル疾患や職務遂行に影響を及ぼす重病に関する詐称が多い傾向にあります。たとえば、過去にメンタル疾患や重病による長期休業をしていた事実を隠すケースが挙げられます。
ただし、病歴に関しては、自社の業務遂行に支障がない限り、解雇することはできません。また、原則として収集が禁止されている特定の機微情報に該当するため、選考プロセスの中で候補者へ情報の開示を求めることは、困難であるといえるでしょう。
犯罪歴
経歴詐称の中でも最も重大なのが、自身の犯罪歴を隠すことです。履歴書の賞罰欄や面接時に犯罪歴を問われた際、応募者は正直に申告する必要があります。
ただし、申告が必要な犯罪歴は「有罪判決が確定したもの」に限定されます。逮捕歴や起訴猶予といった前歴、あるいは遠い過去の犯罪歴は、これには該当しません。
また、刑法第34条の2(※)により、禁錮以上の刑の執行が完了し、その後罰金以上の刑に処せられず10年が経過した場合、刑の言い渡しが消滅するため、申告しなくても経歴詐称にはなりません。
※出展:e-Gov法令検索 刑法
企業が経歴詐称を見破る方法
経歴詐称をした人材を採用しないために、企業はあらかじめ自衛策を講じる必要があります。ここでは、企業が経歴詐称を見破るために効果的な5つの方法を紹介します。
履歴書・職務経歴書の矛盾チェック
経歴詐称を見破るには、履歴書や職務経歴書の内容を精査することが重要です。学歴や職歴の開始・終了年月が連続しているか、前職での職務内容が履歴書と職務経歴書で一致しているかを確認します。
これらをチェックし、異なる内容が記載されている場合、矛盾が疑われます。また、履歴書に記載されている前職の在籍期間に偽りがある場合は、年金手帳の内容と照合することで詐称を見抜くことが可能です。
前職へのリファレンスチェック
応募者の前職で関わった同僚や上司へリファレンスチェックを実施することも、経歴詐称の有無を見抜く有効な手段です。
ただし、リファレンスチェックを行うには、応募者の同意が必要です。また、リファレンスチェックの結果が必ずしも信頼できるとは限らないため、慎重に実施することが求められます。
公的書類の提出要求
応募者の経歴詐称を見破るには、卒業証明書や退職証明書はもちろん、年金手帳や雇用保険被保険者証、源泉徴収票の提出を求めることも非常に効果的です。
卒業証明書は学歴の確認に、退職証明書は前職の企業名の確認に役立ちます。
年金手帳には、年金の加入日が記載されています。このため、履歴書に記載されている経歴の日付と年金手帳の記録が一致していなければ、経歴詐称をしている可能性があります。
また、雇用保険被保険者証や源泉徴収票では、直近まで勤務していた企業名が明らかになるため、前職の経歴を偽っていた場合に見破ることが可能です。
SNS・公開情報の調査
応募者のSNSを調査することも、経歴詐称を見破る方法として有効な手段です。応募者のアカウントをリサーチし、プロフィールや投稿内容などをチェックしましょう。
応募者から伝えられた情報と、SNS上の記載内容に矛盾がなければ、経歴詐称をしていない証拠になります。
また、応募者の経歴や刑事・民事訴訟歴といった情報を調査するバックグラウンドチェックの専門会社を活用するのもおすすめです。
試用期間中の実務評価
業務内容に関する詐称などは、試用期間中に応募者が申告したスキルの検証を行うことで見破ることが可能です。具体的な業務課題を設定し、実務を通じてスキルや経験の真偽を確認しましょう。
実務に関連するテストや評価を実施することで、応募者が申告した業務スキルや経験を実際に身に付けているかどうかを判断できるでしょう。
経歴詐称が発覚した際の企業の対応
応募者や既に採用した人材の経歴詐称が発覚した場合、企業が取るべき対応として、以下に挙げる5つの方法が有効です。
採用内定の取り消し
採用候補者の経歴詐称が発覚した場合、内定取り消しに至るケースがあります。ただし、一度内定を出すと労働契約を締結したとみなされるため、慎重な対応が必要です。
詐称していた内容が学歴や職歴に関するものであれば、労働契約法第16条(※)の「客観的かつ社会通念上正当な理由」に該当するため、内定取り消しを行えます。
※出典:e-Gov法令検索 労働契約法
解雇処分
解雇は懲戒処分の中でも最も重い処分です。このため、経歴詐称であっても、労働契約法第15条・16条(※)により、客観的かつ合法的な理由があり、社会通念上相当でなければ認められません。
解雇処分とするには、詐称した内容が極めて悪質であり、企業が損害を被るか否かが基準になります。軽微な勤務期間の省略や、年月日などの書き間違いに関しては該当しません。
また、企業が従業員を解雇する場合は、あらかじめ就業規則に懲戒処分の種類や事由について定めておく必要があります。
※出典:e-Gov法令検索 労働契約法
降格・配置転換
経歴を偽って重要なポジションや部署に配属された人材の場合、役職や職級を下げる処分として、降格人事や部署の配置転換などを行います。
また、降格に伴って給与が減額される場合がほとんどです。ただし、いずれの処分を行う際にも、就業規則に基づき適切に実施される必要があるため、あらかじめ確認を怠らないようにしましょう。
減給・戒告
従業員の経歴詐称が発覚した場合、企業は当該者に対して減給や戒告処分を行うことができます。
比較的軽微な詐称に対しては、当該者の賃金を減額する処分(減給)が適用されます。減給額や期間は、就業規則や労働契約に基づいて決定されます。
また、戒告は当該者に対する厳重注意を意味し、書面での通知や始末書の提出を求めることもあります。
損害賠償請求
応募者の経歴詐称により、企業が何らかの損害を被った場合、民法第709条の「不法行為による損害賠償」(※)に基づいて損害賠償請求を行うことも可能です。
ただし、企業側が応募者の故意または過失を立証する必要があります。たとえば、虚偽の経歴に基づいて応募者が採用され、その結果企業に損害を与えた場合は、損害賠償請求が可能です。
また、特定の資格や経験が必要な職務において、応募者が虚偽の経歴を申告して採用された場合なども該当します。
※出典:法令リード 民法
御社の採用業務を副業社員に任せてみませんか?
今回は、経歴詐称に関するさまざまな情報をお届けしました。経歴詐称はあってはならないことですが、企業側が嘘を見破る方法を理解し、適切な自衛策を講じることがカギとなります。
このため、御社の採用業務をハイスキルな副業社員に任せることで、トラブルを未然に防ぐこともできるでしょう。
採用業務経験はもちろん、さまざまなスキルを保有する優秀な副業社員をお探しなら、副業人材マッチングサービスの「lotsful」をぜひご活用ください。
採用にかかるコストや工数を懸念される方でも、「lotsful」なら“初期費用0円&最短5日”でマッチングが可能です。
さらに、専属のエージェントがスタートからゴールまで併走するため安心してご利用いただけます。