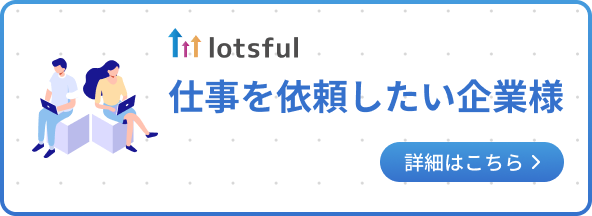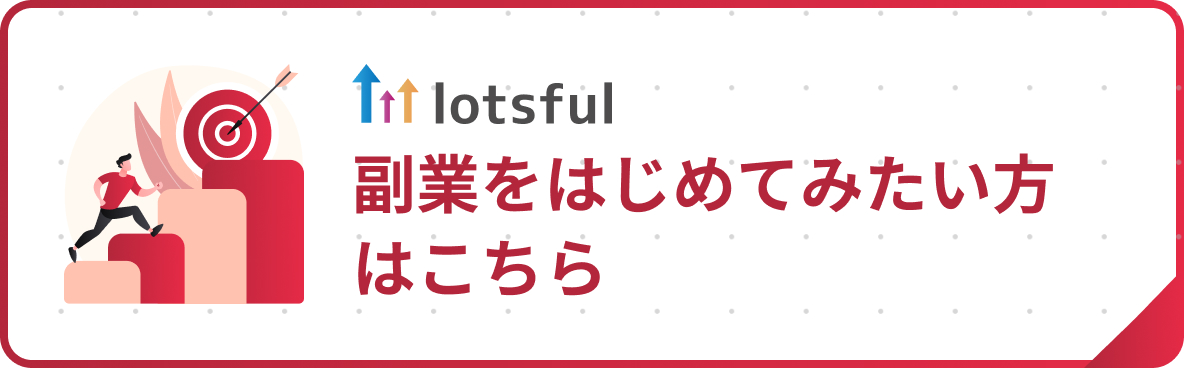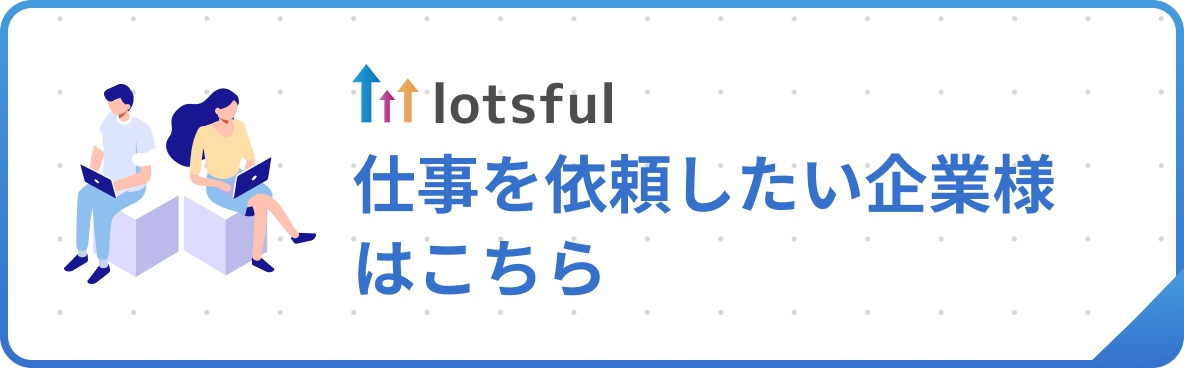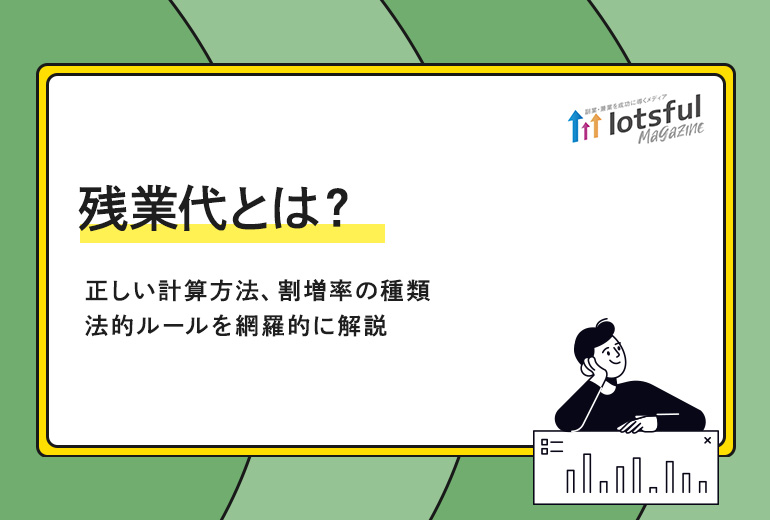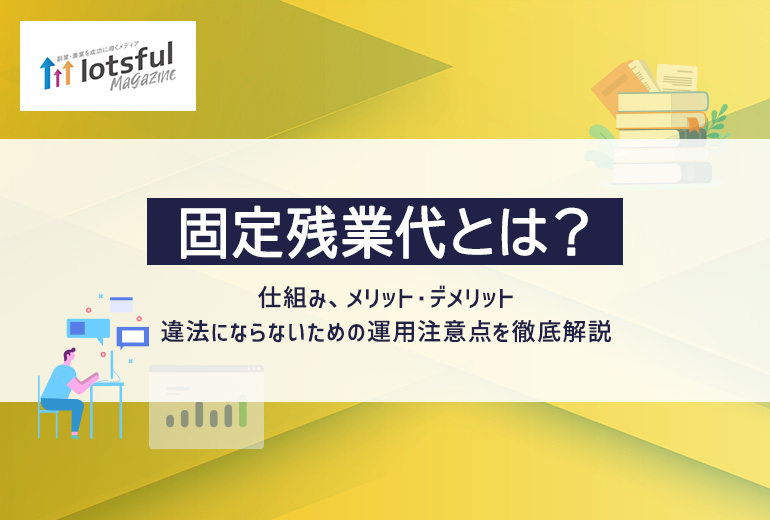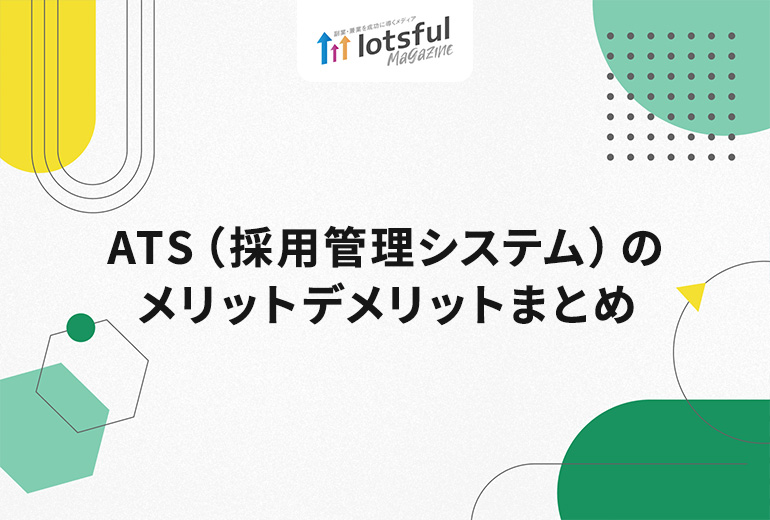
ATS(採用管理システム)のメリットデメリットまとめ
企業の採用活動において、ATS(採用管理システム)の導入は、業務効率の大幅な向上に貢献します。候補者のデータを一元管理できるATSは、正社員採用だけでなく、副業人材の獲得にも非常に役立つツールといえるでしょう。
そこで本記事では、企業の採用活動におけるATS導入のメリットとデメリットに加え、選び方のポイントや導入フローについても詳しく解説します。
ATS(採用管理システム)のメリット
採用管理システムとも呼ばれるATS(Applicant Tracking System)は、企業の採用活動における各プロセスの効率を高める機能を搭載したシステムです。
ATS(採用管理システム)を導入することで企業が得られる7つのメリットを以下にご紹介します。
応募者情報を一元管理でき、選考の進捗が把握しやすい
ATSの最大のメリットは、履歴書や職務経歴書、選考時の評価といった応募者情報を一元管理できる点にあります。Excelや紙ベースでの管理とは異なり、情報の見落としや重複入力を回避することができます。
また、応募者ごとの選考ステータスが一覧で表示されるため、進捗状況をリアルタイムで把握することが可能です。どのプロセスが停滞しているかを可視化できるため、進捗の偏りが解消されるでしょう。
面接日程の調整や連絡を自動化でき、工数削減につながる
ATSを活用すれば、採用担当者や面接官のスケジュールと応募者の希望日程に基づき、候補日時の提示や調整を自動化することができます。
これまで、企業と応募者の間でメールや電話により行っていた連絡が不要となるため、採用部門や面接官の工数削減につながります。
過去の選考履歴を蓄積し、再アプローチが可能になる
ATSでは、選考時の評価や辞退理由など、応募者ごとの詳細な選考履歴が自動で保存されます。これにより、過去の応募者データを簡単に検索・参照できるようになります。
このため、過去に辞退や採用を見送った人材に対して、再度アプローチをかけることも可能です。ATSは、いわゆるタレントプールとしての活用ができる点でも、導入するメリットが大きいといえるでしょう。
面接官や採用チーム間での情報共有がスムーズになる
これまでExcelや紙などで管理していた応募者情報を、ATSによって一元管理できるようになるため、面接官や採用チームは、リアルタイムで情報にアクセスすることが可能になるでしょう。
最新の選考状況を、関係者全員がいつでも確認できるようになるため、担当者間の声がけやメールによる進捗確認が不要となり、各部門の連携が円滑になります。
候補者対応の抜け漏れを防ぎ、採用CXが向上する
ATSの導入により、候補者の選考ステータスや対応履歴が一元管理されるため、連絡漏れや対応ミスを防ぐことが可能です。
応募者一人ひとりに対して、迅速かつ、丁寧な対応を行えるようになることで、企業に対する信頼感が高まり、採用における候補者体験(採用CX)も向上します。
採用データを活用し、効果分析や改善に活かせる
採用活動にATSを導入すれば、各選考プロセスにおける応募数や選考通過率などがデータとして蓄積されます。
これらの情報を分析することで、「どの媒体からの応募が効果的か」「どの選考プロセスに改善余地があるか」が可視化されるため、次回以降の採用活動に向けた具体的な改善策を講じることができるでしょう。
外部媒体との連携により、求人出稿や応募受付も簡素化できる
ATSは、外部の求人サイトや転職エージェントとの連携が可能です。ATSで作成した自社の求人情報を、複数の媒体に一括で出稿できるほか、各媒体からの応募情報も自動で取り込まれます。
これにより、手作業による入力やチェックといった手間が省けるだけでなく、入力ミスや情報の重複といったヒューマンエラーを回避できるため、採用業務全体の簡素化に貢献するでしょう。
ATS(採用管理システム)のデメリット
ATSの導入は、企業の採用活動にさまざまなメリットをもたらす一方で、選び方を間違えると以下に挙げる5つのデメリットが生じる可能性があります。
導入コスト・運用コストが発生する
ATS導入時には、自社の採用フローに合わせてシステムの設定や構築を行う必要があります。このため、ベンダーによる初期設定やカスタマイズにかかる費用が発生します。
また、運用においては、多くのATSが月額課金制のSaaS型で提供されているため、月額利用料が発生するほか、利用人数などに応じて費用が変動するプランもあります。
企業規模や導入するシステムによって費用対効果は異なるため、導入フローを明確にし、予算枠の確保と事前の比較検討が重要です。
社内メンバーへの操作教育や運用ルールの整備が必要
ATS導入時に見落とされがちなのが、社内メンバーへの操作教育や運用ルールの整備です。システム操作が得意な社員ばかりとは限らず、明確な運用ルールがないまま導入すると、現場で混乱が生じる可能性があります。
また、ATSの操作に慣れるまでには一定の期間を要します。そのうえ、採用担当者や現場責任者など、役割ごとに異なる操作方法を教育しなければなりません。
さらに、社内マニュアルを作成し、ルールに基づいた運用体制を構築したうえで、社員への周知徹底が求められるため、人的リソースを割けない企業では対応が難しい場合もあります。
機能が多すぎると使いこなせず、逆に非効率になる場合がある
ATSは多機能であればよいというわけではありません。機能が多すぎると、「どの機能を使えばよいかわからない」といった混乱を招くことがあります。また、機能数が多くなることで、社内での教育工数もさらに増えてしまいます。
操作が複雑なATSを導入した場合、自己流で操作する社員も出てくるため、結果としてデータが崩れるなどのトラブルが発生するおそれもあります。このような事態を防ぐためにも、自社の業務レベルに適した機能が搭載されたATSを選ぶことが重要です。
自社の採用フローに合わないシステムを選ぶと定着しにくい
ATSを導入しても、現場に定着しなければ意味がありません。選定したATSが自社の採用フローに合わない場合、操作性の悪さなどを理由に、従来の手作業に戻ってしまうケースも見受けられます。
このように、ATSの活用が現場に定着せず、ATS導入が形骸化してしまうと、結果として費用対効果も低下するおそれがあります。
データ移行やシステム連携に時間や手間がかかることがある
これまでの応募者データや選考履歴が、他の採用システムやExcel、紙ベースなどで保存されている場合、それらの情報を一元化してATSへ移行しなければなりません。
また、既存システムと導入するATSの仕様が合わない場合、連携のためにカスタマイズ費用が発生することもあります。
ATSの導入には、データ移行やシステム連携にかかる時間と手間だけでなく、コストがかかる可能性があることを、あらかじめ認識しておきましょう。
ATS(採用管理システム)の選び方
自社の採用活動においてATSの効果を最大化するには、システムの選び方が大きく影響します。以下に挙げる8つのポイントを重視し、自社のニーズにマッチしたATSを選びましょう。
自社の採用規模やフローに合った機能があるか
ATSの選び方で注意すべき点の一つは、自社の採用規模やフローに適した機能が搭載されているかどうかを確認することです。
たとえば、自社の年間採用人数が数名程度の小規模採用にも関わらず、多機能なATSを導入しても費用対効果に見合わない可能性があります。
また、部署ごとの評価ステップなど、自社特有の採用フローを再現できないATSでは、業務をシステムに合わせる必要があり、結果として現場の混乱を招く原因になり得ます。
UIがシンプルで使いやすく、現場でもすぐに運用できるか
UI(ユーザーインターフェース)がシンプルかつ、使いやすいATSは、現場でのスムーズな運用や定着において非常に重要な要素といえるでしょう。
項目が見やすく整理されており、ワンクリックで必要な情報に即座にアクセスできるUIであれば、誰でも操作しやすく、入力ミスやデータ更新漏れを防ぐことが可能です。
必要な外部連携(求人媒体、チャットツールなど)が可能か
ATSを選ぶ際は、あらかじめ自社で使用している求人媒体やチャットツールと連携可能かを確認しておきましょう。
自社が利用している媒体やツールと連携できないATSの場合、応募情報の手動転記やスケジュール管理などの手作業が発生し、業務負担が大きくなるだけでなく、人為的なミスの増加にもつながる可能性があります。
データ分析やレポート機能が充実しているか
自社の採用活動を継続的に改善していくには、データ分析機能やレポート機能が充実しているATSを選ぶことが重要です。
媒体別の応募数や、選考通過率、辞退率などを可視化し、改善策を導き出すためのデータ分析とレポートは必要不可欠です。
詳細なデータ分析と充実したレポート機能を備えたATSであれば、課題の早期発見と迅速な対応が可能になり、採用の精度とスピードの両立が実現できるでしょう。
セキュリティ対策や個人情報保護の水準が十分か
ATSには、応募者の個人情報が大量に保存されるため、セキュリティ対策や個人情報保護体制が万全であるかどうかは、非常に重要なチェックポイントです。
セキュリティ水準の低いATSを選ぶと、情報漏えいや不正アクセスのリスクが高まり、法的トラブルや企業の信頼失墜にもつながりかねません。
リスク回避の観点からも、セキュリティレベルの高いATSを選ぶことは企業の責任といえるでしょう。
サポート体制が整っているか
ATSを導入する際には、業務に必要な機能が搭載されていることはもちろん、サポート体制の手厚さも重視すべきです。
ATSの初期設定だけでなく、運用中にトラブルが発生した場合の迅速な対応や、導入後の運用支援が受けられるかどうかも確認しておきましょう。問い合わせ対応のスピードや、伴走型サポートの有無なども選定の大きな判断材料となります。
無料トライアルやデモが提供されているか
どれほど評判がよく、高機能であっても、実際に使用してみなければ自社に適しているかどうかは判断できません。まずは、無料トライアルやデモを通じて、操作感や実際の使用感を確認してみましょう。
操作性とベンダーの対応を確認したうえで、現場が使いやすく、自社の業務フローにも合うATSを選ぶことで、スムーズな導入と早期の定着につながります。
価格帯が自社の予算に見合っているか
高機能なATSであっても、自社の予算を超過してしまうと継続利用が難しくなります。予算の都合で途中解約という結果にならないよう、価格帯をしっかり見極めなければなりません。
ATS導入時には、初期費用や月額費用だけでなく、カスタマイズやサポートにかかるコストも含めて、トータルコストで比較検討しましょう。
ATS(採用管理システム)の導入フロー
ATSは、以下に挙げる8つの導入フローに沿って進めるとスムーズです。
1. 導入目的・課題の整理
自社のATS導入の目的や解決すべき課題が明確でない場合、ATSを導入しても効果を十分に発揮できません。また、解決すべき課題や業務フローに合わないATSを選ぶと、費用対効果が大幅に低下するリスクがあります。
2. 要件の定義
自社の採用フローや課題にマッチしたATSを選ぶためには、自動化を希望する業務やその範囲に関する具体的な要件定義が求められます。自社の採用フローと課題を踏まえ、必要な機能を洗い出し、利用者の役割や操作権限も明確にしておきましょう。
3. 複数サービスの比較・資料請求・デモ利用
自社の要件に合うサービスを見極めるために、複数のATSサービスを比較検討しましょう。見た目ではわからない仕様や機能については資料請求をし、可能であればデモを利用して操作性も含めて確認しておくと安心です。
4. 社内関係者との合意形成・承認取得
ATS導入時には、人事部門だけでなく現場責任者やシステム部門などの社内関係者との合意形成が欠かせません。導入目的や課題のすり合わせを行い、費用対効果も含めて意思決定者から正式な承認を取得しましょう。
5. ベンダーとの契約・導入スケジュールの確定
ベンダーとの契約では、「料金体系・契約期間」「サポート範囲」「トラブル時の対応」などの条件を明確にしたうえで、正式な導入スケジュールを確定しましょう。契約条件やスケジュールが曖昧なままだとトラブルの原因となります。
6. 初期設定・マスタ登録・既存データの移行作業
ATSの効果を最大限に引き出すためには、丁寧な初期設定が不可欠です。自社の業務に早期に適合させるため、基本情報のマスタ登録や既存データの移行を行い、動作確認と整合性チェックも実施しましょう。
7. 社内向けの操作説明・マニュアル作成・運用ルールの整備
全社員が問題なくATSを使いこなせるよう、マニュアルと運用ルールを整備し、社内向けの操作説明会を実施しましょう。これは、社内でATSを定着させるための最も重要なフェーズです。
8. 運用開始後の定期的な振り返りと改善
ATSの運用開始後は、実際の運用状況を定期的に振り返り、使い勝手や業務効果を継続的に改善していくことが重要です。現場での活用状況に課題がある場合は、早期に改善策を講じることで、成果と定着率の向上につながります。
御社の業務に副業社員の活用を検討してみませんか?
今回は、採用活動の効率アップに大きく貢献するATS(採用管理システム)について、選び方や導入フローなど、企業が知っておくべき情報をわかりやすくまとめてお届けしました。
ATSは、御社の採用業務の質と効率向上に大きく役立ちます。もし御社がリソース面で課題を抱えているのであれば、ATSの機能と副業社員のスキルをうまく組み合わせて活用することで、さらに効果が高まるでしょう。
即戦力となる人材をお探しであれば、新たな採用チャネルとして効果的な副業人材専門のプラットフォーム「lotsful」の活用を検討してみてはいかがでしょうか?
「lotsful」なら、御社がお望みのスキルを兼ね備えた副業社員とのマッチングを、初期費用0円で迅速に実現します。副業人材の導入に関するご相談は、何でもお気軽に「lotsful」へお問い合わせください。