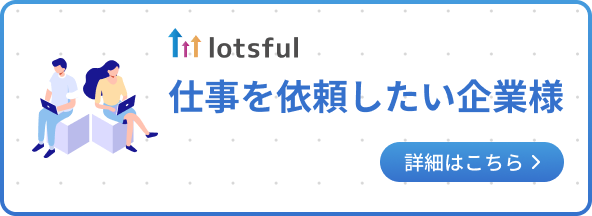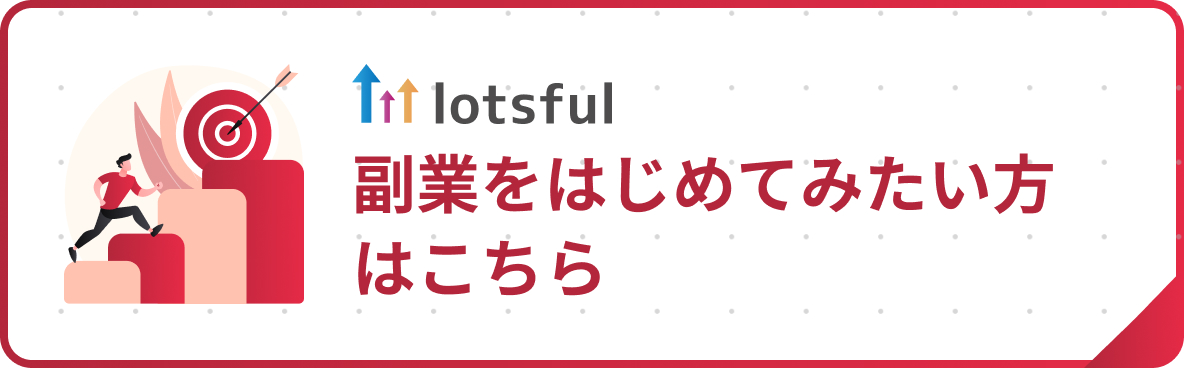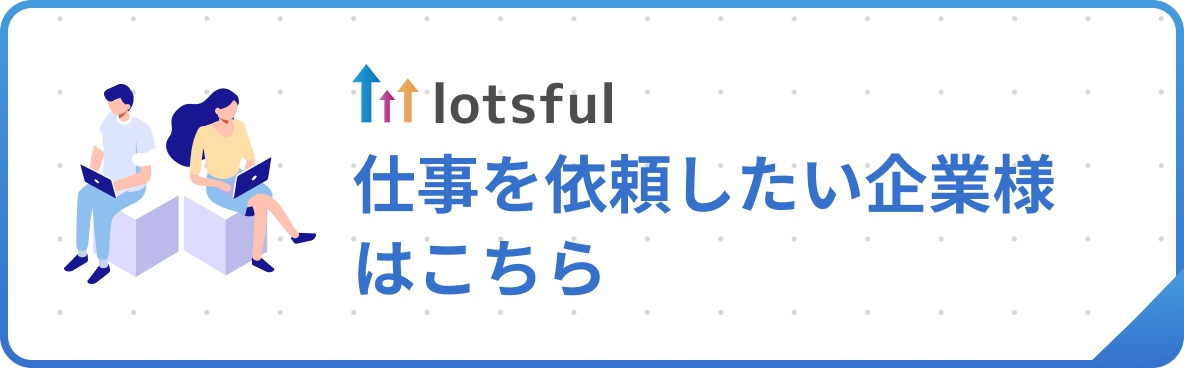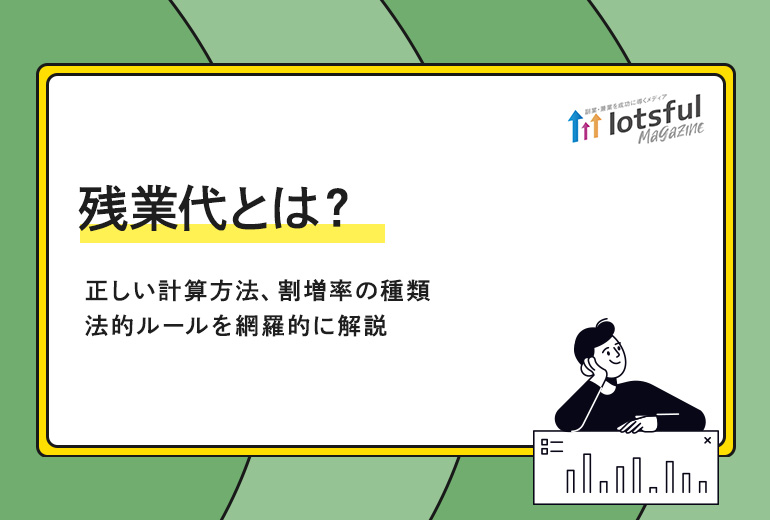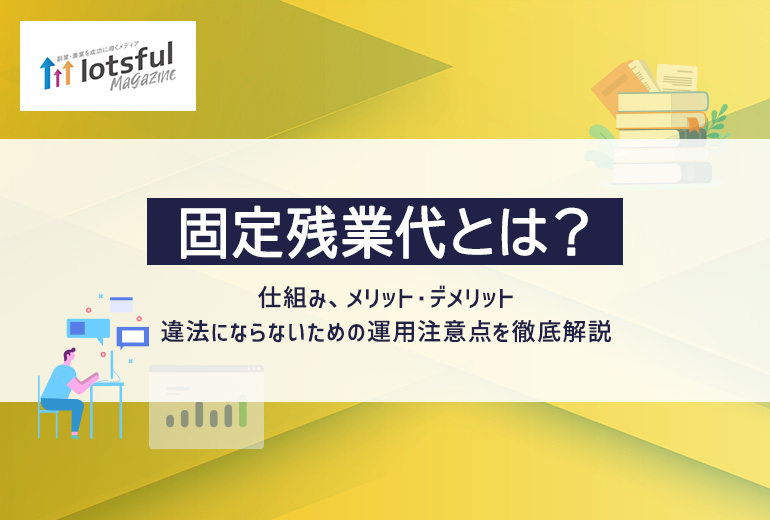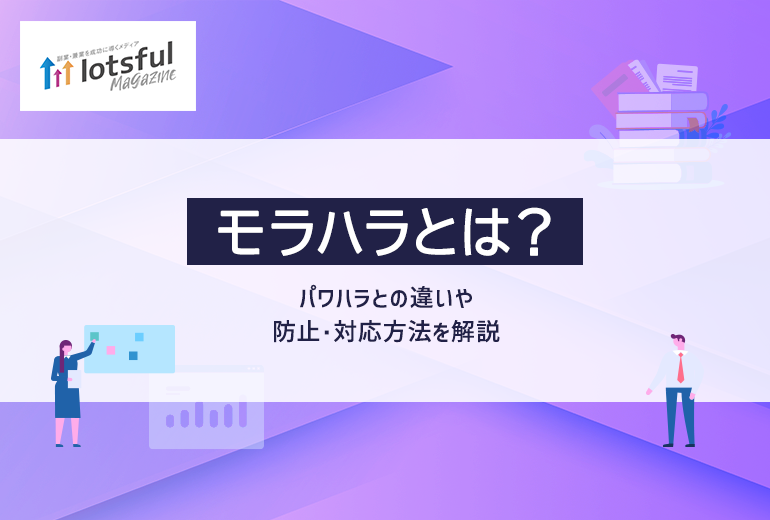
モラハラとは?パワハラとの違いや防止・対応方法を解説
モラハラが大きな問題へと発展した背景には、職場における精神的な健康や人間関係の重要性が、社会的に広く認識されるようになったことがあります。
職場におけるモラハラは、正社員だけが対象ではありません。パートやアルバイト、契約社員、副業社員など、組織に関わるすべての人々が加害者にも被害者にもなり得るリスクがあります。
本記事では、モラハラの具体的な例をはじめ、パワハラとの違いや加害者の特徴、防止策、企業として取るべき対応までを詳しく解説します。
モラハラとは
モラハラとは「モラルハラスメント」の略称であり、攻撃的な言葉や態度によって相手を傷つけ、精神的に追い詰める行為を指します。
身体的な暴力ではなく、心理的なダメージを与える行為が中心です。具体的には、以下のような行為がモラハラに該当します。
- 相手の人格を否定・侮辱する
- 無視などをして孤立させる
- 過度な干渉や監視行為を行う
- 脅迫したり怒鳴ったりする
- 問題や結果の責任を転嫁する
モラハラは職場だけでなく、学校や家庭など、人間関係が存在するあらゆる場で発生する可能性があります。社会人が長期間モラハラを受けた場合、仕事のパフォーマンス低下や離職につながることも少なくありません。
また、うつ病や不安障害といった深刻な健康被害を引き起こすこともあり、長期療養を余儀なくされる場合もあります。
企業をはじめとする組織では、相談窓口や通報制度の整備だけでなく、管理職への教育を通じてモラハラを容認しない職場風土の形成が求められます。
モラハラとパワハラの違い
ハラスメントには加害者と被害者が存在しますが、「モラハラ」と「パワハラ(パワーハラスメント)」は、似ている部分がある一方で、原因や行為の性質、発生場面などに違いがあります。
以下の表に、モラハラとパワハラの主な違いについてまとめました。
| 区分 | モラハラ | パワハラ |
|---|---|---|
| 特徴 | 言葉や態度で相手の心を攻撃する精神的な嫌がらせ行為 | 立場や権力を利用して相手に苦痛を与える行為 |
| 原因 | 嫉妬や支配欲、感情的敵意などの個人的感情 | 上下関係や業務上の権限の乱用 |
| 行為の性質 | 継続的かつ陰湿で、相手を心理的に追い詰める | 直接的かつ攻撃的で、相手の肉体・精神両面に圧力をかける |
| 発生場面 | 職場・家庭・学校など幅広い人間関係で発生 | 主に上司や部下間など、職場内で発生 |
| 法的位置付け | 法的定義は曖昧だが、職場のモラハラはパワハラに含まれる場合もある | 労働施策総合推進法※(通称:パワハラ防止法)により企業に防止措置が義務化 |
※出典:厚生労働省HP「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等」
職場におけるモラハラの例
職場におけるモラハラの例として、代表的な4つの事例を以下に紹介します。
無視・挨拶を返さない
企業では、上司や先輩、同僚が特定の人物の存在や言動を好ましく思わず、意図的に無視したり、挨拶を返さなかったりするケースがあります。
このような状況が発生する背景には、職場内での意見の対立や派閥構造、業務評価や昇進への影響などが関係している場合があります。また、異動や新入社員の受け入れ時にも発生しやすい傾向があります。
過度な叱責や人格否定
業績目標の未達などを理由に、上司や先輩社員が成果の上がらない社員に対して、過度な叱責や侮辱的な言葉を投げかける行為も、職場のモラハラに該当します。
上層部からのプレッシャーによるストレスや、「厳しく𠮟ることが教育につながる」とする組織文化、日常的なコミュニケーション不足などが原因となることもあります。
業務上必要な情報を意図的に共有しない
日常的な会話だけでなく、業務上必要な情報を意図的に共有しない行為も、職場におけるモラハラの典型的な例です。
情報を与えられなかった従業員は、業務の遂行に支障をきたし、不利益や不当な評価を受けるリスクが高まります。
加害者の心理的背景としては、情報を支配の手段として利用し、被害者を排除または追い詰める目的がある場合が多いとされています。
陰口や噂の流布による心理的な追い込み
被害者の業績や能力、ポジションに対する嫉妬心から、陰口や噂を広めて心理的に追い込む行為も、職場におけるモラハラでよく見られる事例といえます。
また、加害者が単独でなく、周囲が「仲間外れにされたくない」という心理から同調するケースも少なくありません。競争や評価を重視する社風では、ライバルを蹴落とす目的で噂が利用されることもあります。
職場におけるモラハラ加害者の特徴
職場におけるモラハラ加害者には、主に以下の3つの特徴が見られます。
権限を誇示し、部下を支配しようとする傾向がある
上司が部下に対して権限を誇示し、支配的に振る舞うのは、自己肯定感の低さや不安の裏返しである場合があります。
部下を服従させることで、自らの優位性や存在価値を確認しようとします。また、上司の権力を容認する組織文化も、このような支配的行動を助長する要因となり得ます。
感情のコントロールが苦手で、怒りを他人にぶつけやすい
職場という公的な場であっても、感情のコントロールができず、怒りを他人にぶつけやすい人は、自己制御力の低さや衝動性が強い傾向にあります。
また、自身のミスや劣等感を認めたくないため、「相手が悪い」と感じて理不尽な怒りを正当化する場合もあるでしょう。
自分のやり方・価値観を押しつける傾向がある
自分の能力に自信を持つ人物は、仕事の進め方や価値観を他者に押し付ける傾向があります。
一方で、自信のない人物も、他者の意見を受け入れると「否定された」と感じ、攻撃的になることがあります。また、共感力や協調性の乏しさも、モラハラ加害者に共通する特徴の一つといえるでしょう。
職場のモラハラを放置するリスク
職場のモラハラを放置した場合、どのようなリスクや影響を被るのでしょうか。以下では、職場のモラハラを放置した際に起こりうる3つのリスクを紹介します。
被害者のメンタルヘルス悪化・休職・離職につながる
職場のモラハラを長期間放置すると、抑うつ状態など被害者のメンタルヘルスが悪化し、休職や離職につながるおそれがあります。
早期段階での適切な対応や相談窓口が設けられていない場合、被害者の回復が遅れ、復職が困難となるケースもあります。企業にとっては、優秀な人材の損失だけでなく、人手不足による業務停滞や生産性の低下を招くリスクもあります。
職場全体の士気が下がり、チームワークが崩壊する
職場のモラハラを放置すると、被害者だけでなく、周囲の社員も「次は自分が被害に遭うかもしれない」という不安を抱くようになります。その結果、職場全体の士気が低下してしまいます。
社員一人ひとりの意欲が低下すれば、信頼関係やチームワークが崩壊していきます。このような状態が続けば、組織の生産性や利益率が下がり、取引先との関係や採用活動にも悪影響を及ぼすでしょう。
法的トラブル・損害賠償リスク
モラハラの程度が深刻化、あるいは長期化した場合、加害者だけでなく、適切な対応を怠った企業にも法的責任が問われる可能性があります。
また、職場のハラスメント防止措置を講じていない企業は、労働基準監督署や行政機関の指導対象となるおそれがあります。状況によっては、改善命令や企業名の公表、罰則などに発展するケースもあります。
職場のモラハラの防止方法
職場のモラハラを防止するためには、以下に挙げる4つの方法を実践することが重要です。
モラハラに関する明確なルールやガイドラインを整備する
モラハラを防止するには、「どのような行為や言動がモラハラに該当するのか」を社内で明確に共有する必要があります。そのため、モラハラの具体的な例を示したルールやガイドラインを整備し、社内で周知徹底することが求められます。
明文化されたルールやガイドラインがあることで、上司をはじめとする社員の予防意識が高まり、被害者も声を上げやすくなるでしょう。
相談窓口や外部相談機関の設置
モラハラの防止には、ルール設定やガイドラインの整備と並行して、被害者が安心して相談できる社内窓口や外部相談機関を設置することも欠かせません。
初期段階での介入ができれば、被害者の離職やメンタル不調、訴訟などのリスクを未然に防止できます。特に外部の相談機関を活用すれば、被害者が組織内の立場を気にせず相談できる環境が整います。
定期的な1on1や面談を通じた早期発見体制の構築
定期的に1on1ミーティングや面談を実施することで、上司や人事担当者が社員の人間関係やストレス状況を早期に把握できます。
被害者が安心して相談できる環境を整えることは、休職や離職の防止につながるだけでなく、企業に対する信頼感や職場の心理的安全性を高め、はたらきやすい職場環境づくりにも寄与します。
被害者・加害者双方の視点で事実確認を行う体制を作る
モラハラは、一方の主張だけで判断すると誤解や不当な評価につながるおそれがあります。被害者と加害者の双方の意見や状況を丁寧に確認することで、正確な事実関係を把握することができます。
公平な調査体制を整えることで、職場の信頼性や透明性を高めることが可能です。その結果、相談や報告が活発になり、モラハラの放置や隠ぺいが起こりにくくなるでしょう。
職場でモラハラが起こってしまった場合の対応
職場でモラハラが発生した場合、企業としてどのように対応すべきでしょうか。以下では、3つの具体的な対応方法を紹介します。
被害者のヒアリングを丁寧に行い、精神的安全を確保する
職場でモラハラが発生した際の初動対応として、被害者への丁寧なヒアリングとフォローは最も重要です。
被害者の精神的安全を早期に確保することで、不安の軽減だけでなく、正確な事実把握や組織への信頼維持にもつながります。
中立的な立場での事実確認と記録の徹底
被害者または加害者のいずれかに偏ったヒアリングや判断は、さらなる不信感やトラブルを招くおそれがあります。第三者の中立的な立場で事実確認を行うことで、公平で信頼性の高い対応が可能となるでしょう。
その際には、発言内容や日時、状況などを詳細に記録しておくことが重要です。これにより、後日の検証や「言った・言わない」といったトラブルを防止できます。
加害者に対する注意喚起・指導・懲戒処分の検討
モラハラが確認された場合、再発防止のためには、加害者自身が行為の問題性を認識し、改善に向けて行動することが不可欠です。
加害者にはモラハラの内容や程度、再発リスクを踏まえ、口頭または書面での注意喚起やハラスメント研修の受講などを指導します。モラハラ行為が継続的かつ悪質な場合には、懲戒処分を検討する必要があります。
御社の業務に副業社員を検討してみませんか?
今回は、モラハラの特徴やパワハラとの違い、企業が取るべき対応方法などをお届けしました。そもそもモラハラとは、職場に限らず、いかなる環境でも許されない行為です。
組織文化や業務体制を見直し、はたらきやすい環境を整備することで、従業員の定着率向上や生産性の向上につながります。その際に有効なのが、豊富な経験とスキルを兼ね備えた副業社員の力を活用することです。
もし、御社が優秀な人材をお探しであれば、副業人材マッチングサービス「lotsful」にご相談されることをおすすめします。
御社が求めるスキルを持つ副業社員と出会える「lotsful」なら、従来の採用チャネルよりもスピーディーな人材確保が可能です。 御社の業務の質と効率を格段に高める「lotsful」へ、ぜひ一度ご相談ください!