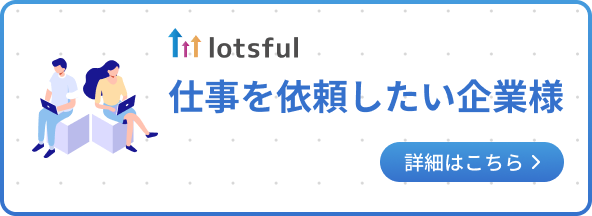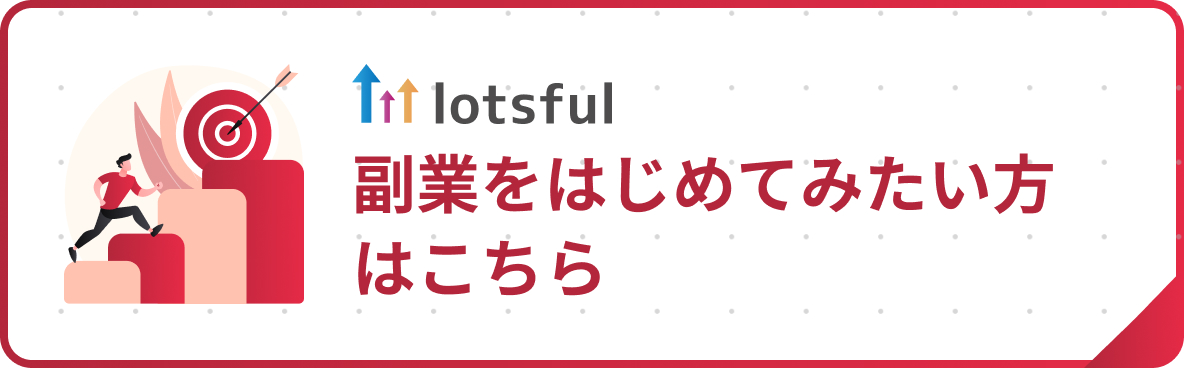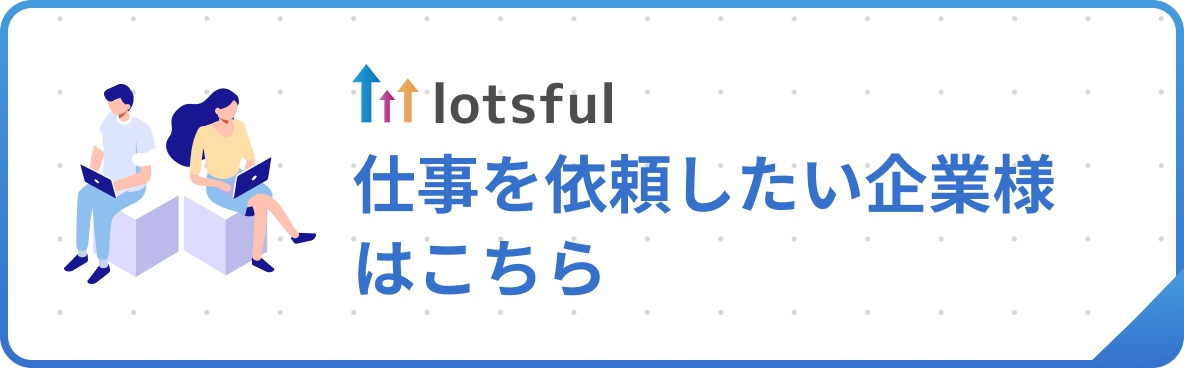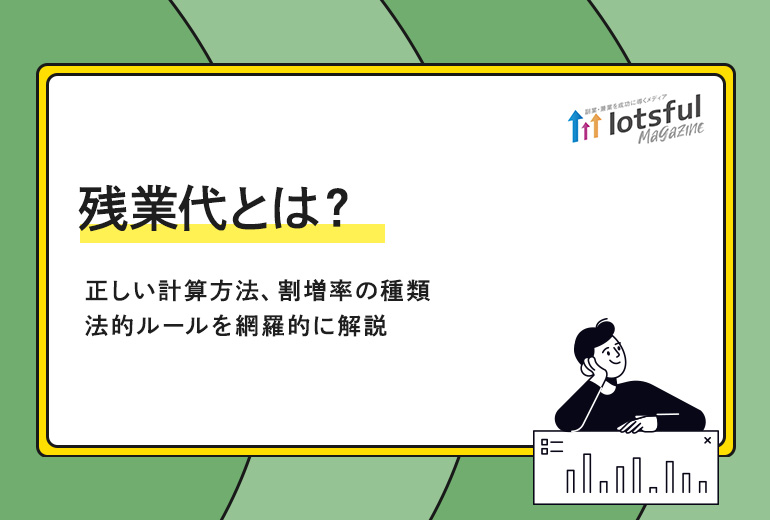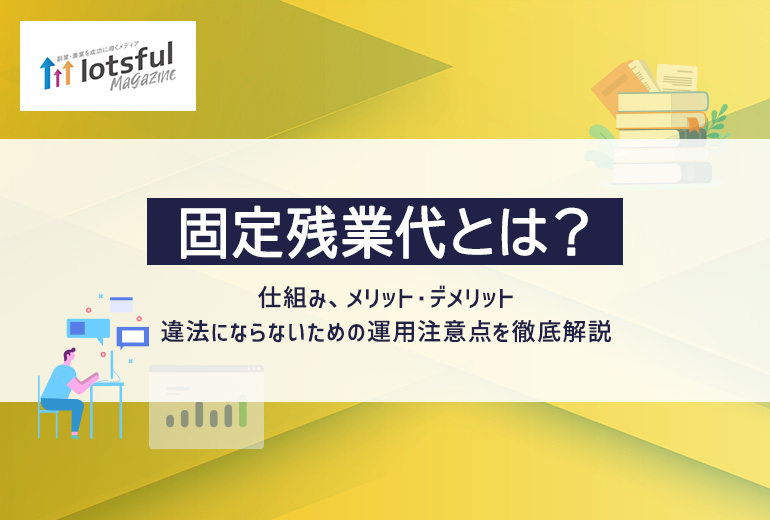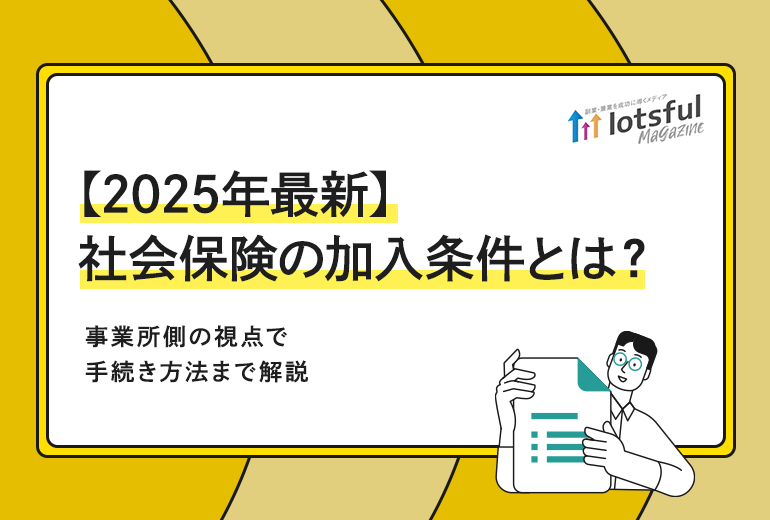
【2025年最新】社会保険の加入条件とは?事業所側の視点で手続き方法まで解説
事業所による社会保険への対応は、正社員や契約社員、派遣社員、パート・アルバイトなどの短時間労働者に限った問題ではありません。
また、副業社員についても勤務時間や報酬、主な勤務先を確認し、必要に応じて加入手続きを行う必要があります。
本記事では、事業所側の視点からみた社会保険の加入条件について、手続き方法や現状、今後検討されている変更点までを詳しく解説します。
事業所における社会保険の加入条件
社会保険の加入適用に関しては、事業所が判断します。2024年10月の「厚生年金保険法」および「健康保険法」の改正(※)以前は、従業員数が101人以上の企業に勤務するパートやアルバイトなどの短時間労働者は、一定の条件を満たす場合にのみ社会保険の対象となっていました。
法改正以降は、従業員数51人以上の企業で勤務するパート・アルバイトも新たに社会保険の加入対象に含まれています。また、事業所における社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入条件は、次の2つの観点に基づき決定されます。
社会保険の強制適用事業所に該当する条件
社会保険の強制適用事業所とは、「健康保険法」および「厚生年金保険法」に基づき、従業員を雇用した時点で自動的に社会保険の加入が義務付けられる事業所を指します。
強制適用事業所に該当する場合、加入条件を満たすすべての従業員を社会保険に加入させる必要があります。また、管轄の年金事務所へ新規適用届(※)を提出しなければなりません。
以下の表に、強制適用事業所となる区分や条件を示します。
| 区分 | 対象 | 義務 |
|---|---|---|
| 法人事業所 | 株式会社、合同会社、社団法人、医療法人などすべての法人 | 従業員が1人でもいれば自動的に強制適用 |
| 個人事業所 | 常時5人以上の従業員を雇用している場合に強制適用(ただし適用外の業種あり) | 非適用業種(任意適用):農業、林業、水産業、サービス業、自由業、宗教など |
社会保険の任意適用事業所に該当する条件
任意適用事業所とは、法律上は社会保険への加入義務がないものの、事業主の申請と従業員の過半数の同意により加入できる事業所を指します。
以下に、任意適用事業所の対象条件をまとめます。
| 区分 | 対象条件 |
|---|---|
| 法人事業所 | 常時従業員5人未満の法人 |
| 個人事業所 | 常時従業員5人未満の個人事業所 |
| 特殊業種 | 農林漁業や家族従業者が中心の事業所など、原則適用外の事業所 |
任意適用事業所となった場合は、日本年金機構または協会けんぽに対し、健康保険と厚生年金保険それぞれの任意適用申請書(※)を提出し、承認を得る必要があります。
従業員の社会保険の加入条件
従業員における社会保険の加入条件について、以下の3つの雇用形態別に「条件」および「加入義務」を含めて解説します。
正社員の場合
正社員として雇用された場合、原則として全員が社会保険の加入対象となります。
| 条件 | ・常時雇用されている正社員 ・週の所定労働時間が常時雇用されている従業員の4分の3以上、かつ1ヶ月の 所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である従業員 |
|---|---|
| 加入義務 | 健康保険・厚生年金ともに全員加入義務あり |
派遣社員の場合
派遣社員に該当する場合は、登録している派遣会社が社会保険加入手続きを行います。
| 条件 | ・週の所定労働時間および日数が派遣先の正社員の4分の3以上であること ・長期的に勤務する見込みがあること |
|---|---|
| 加入義務 | あり(短期派遣であっても、条件を満たす場合は加入義務あり) |
契約社員の場合
契約社員として雇用されている場合は、契約期間にかかわらず正社員と同様の条件が適用されます。
| 条件 | ・期間の定めがある場合でも、週の所定労働時間および日数が正社員の4分の3以上であること ・契約更新があり、継続して勤務する見込みがあること |
|---|---|
| 加入義務 | あり(おおむね週30時間以上の勤務が目安) |
パート・アルバイトの場合
パートやアルバイトは、2016年の制度改正により社会保険の加入対象が拡大されました。以下の5つの条件をすべて満たす場合、社会保険への加入が可能です。
| 条件 | ・従業員が51人以上在籍する企業に属していること ・所定労働時間が週に20時間以上あること ・月額賃金が8.8万円以上であること ・2ヶ月以上の雇用見込みがあること ・夜間・通信を除く学生でないこと |
|---|---|
| 加入義務 | 上記の条件をすべて満たした場合に発生 |
今後検討されている社会保険の加入条件の変更点
現時点で検討されている社会保険の加入条件の変更点は、以下の3点が中心です。
年収106万円の壁の撤廃
現在、年収が約106万円(月額8.8万円)を超えると、勤務先の企業規模や労働時間などの条件を満たす場合に社会保険への加入義務が生じます。
「年収106万円の壁」の撤廃は、2026年10月の施行を予定する年金制度改正法に基づくものであり、社会保険の適用要件を見直す重要な改革とされています。
段階的な企業規模要件の撤廃
社会保険の適用対象となる短時間労働者には、現在「従業員数51人以上」という企業規模要件があります。しかし、2025年6月に成立した年金制度改正法(※)により、この要件を段階的に撤廃する方針が決定しました。
段階的な撤廃によって、将来的には企業規模に関係なく、一定の条件を満たす短時間労働者も社会保険に加入できるようになり、健康保険と厚生年金の保障を受けられる見込みです。
個人事業所における適用範囲の拡大
これまで、社会保険は主に法人の従業員が対象であり、個人事業主や小規模事業所に従事する従業員の多くは加入対象外という状況でした。
しかし、適用対象となる従業員数の要件緩和や範囲拡大により、個人事業所などの従業員も医療費負担の軽減や将来の年金受給額の増加が見込めるようになり、生活面での安心感が向上すると考えられます。
事業所側の社会保険の加入手続き方法
事業所が従業員を雇用し、社会保険の適用事業所となる場合は、所定の書類を準備のうえ、社会保険の加入手続きを行う必要があります。
以下では、それぞれの項目ごとに必要書類・手続き期限・提出先について順に解説します。
必要書類
まず、事業所が初めて社会保険に加入する際には、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」(※1)を提出しなければなりません。この書類は、日本年金機構(※2)の公式サイトからPDF版またはExcel版をダウンロードできます。
届出時に必要となる主な書類は、以下のとおりです。
- 登記簿謄本(法人の場合)
- 法人番号指定通知書などの写し(法人の場合)
- 事業主の住民票の写し(個人事業主の場合) など
また、雇用保険の適用事業を開始した場合には、「雇用保険適用事業所設置届」(※3)を提出する必要があります。この届出に際して必要となる主な書類は、以下のとおりです。
- 登記簿謄本
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 源泉徴収票 など
さらに、事業主の名称や所在地などを変更した場合には、「雇用保険事業主事業所各種変更届」(※4)の提出が必要です。この際にも、登記簿謄本などの添付を求められることがあります。
※出典1:日本年金機構HP「1-1:事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき」
※出典2:日本年金機構HP「健康保険・厚生年金保険 新規加入に必要な書類一覧」
※出典3:厚生労働省「雇用保険適用事業所を設置する場合の 手続きについて」
※出典4:日本年金機構HP「事業主の変更や事業所に関する事項の変更があったときの手続き」
手続き期限と提出先
健康保険および厚生年金保険の手続きを行う際、事業所を新規に設立した場合は「事業所設置届」(※1)を提出する必要があります。また、新たに従業員を雇用するたびに、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」(※2)を提出します。
さらに、雇用する従業員に扶養家族や親族がいる場合は、上記に加えて「健康保険・厚生年金保険被扶養者(異動)届」(※3)も提出しましょう。
| 手続き内容 | 提出先 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 事業所を新規設立した場合 | 事業所を管轄する下記いずれか ・日本年金機構の事務センター ・年金事務所 ・健康保険組合 |
・最初の従業員を雇用した日から 5日以内 「事業所設置届」および「雇用保険被保険者資格取得届」(※4)を提出 |
| 健康保険・厚生年金の対象従業員を雇用した場合 | ・入社日から5日以内 雇用するたびに、「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」および「雇用保険被保険者資格取得届」を提出 |
|
|
扶養家族や親族がいる従業員を雇用した場合 |
・入社日から5日以内 雇用するたびに、「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」に加え、「健康保険・厚生年金被扶養者(異動)届」と併せて提出 |
雇用保険の手続きに必要な書類は、従業員を雇用する段階や状況によって異なるため、提出タイミングには注意が必要です。
具体的には、以下のタイミングでそれぞれ書類を提出しなければなりません。
| 手続き内容 | 提出先 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 事業を新規設置し、初めて従業員を雇用した場合 | 事業所を管轄するハローワーク |
・最初の従業員を雇用した日の翌日から10日以内 |
| 雇用保険の対象となる従業員を初めて雇用する場合 | ・雇用日から10日以内 「雇用保険被保険者資格取得届」を提出するタイミング |
※出典1:日本年金機構HP「1-1:事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき」
※出典2:日本年金機構HP「健康保険・厚生年金保険の資格取得届、資格喪失届および健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」
※出典3:日本年金機構HP「健康保険・厚生年金被扶養者(異動)届」
※出典4:ハローワークインターネットサービス 「雇用保険被保険者資格取得届」」
※出典5:厚生労働省HP「労働保険の成立手続」
御社の業務に副業社員を検討してみませんか?
今回は、社会保険の加入に関して、必要な手続き方法をはじめ、事業者である企業が知っておきたい情報をお届けしました。
社会保険は、企業にとっては優秀な人材確保につながる「信頼の証」であり、従業員にとっては生活・医療・老後を支える重要な制度です。
複雑な社会保険関連の実務は、経験豊富な副業社員のスキルを活用することで、正確かつ効率的に対応することが可能です。
優秀な人材との出会いをスピーディーに実現したい企業様は、副業人材マッチングサービス「lotsful」の活用を検討してみてはいかがでしょうか?
副業社員の採用チャネルとして注目を集める「lotsful」なら、時間や工数、コストを抑えながら理想の人材とのマッチングを実現できます。御社の業務の質と効率向上を、伴走型のサービスで支援する「lotsful」へ、まずはお気軽にご相談ください。