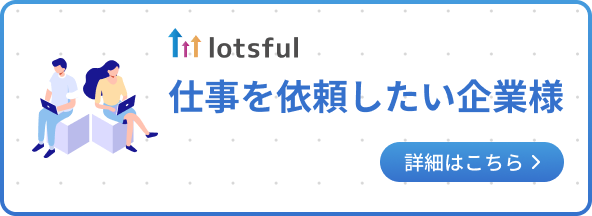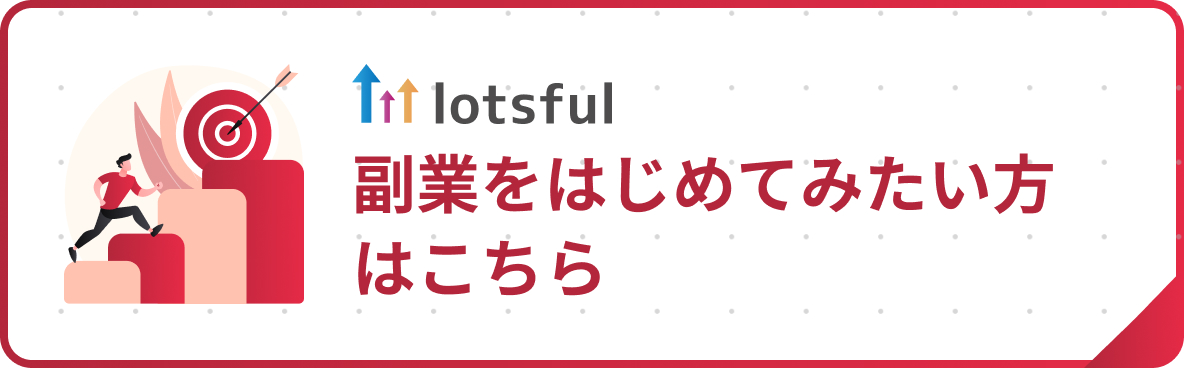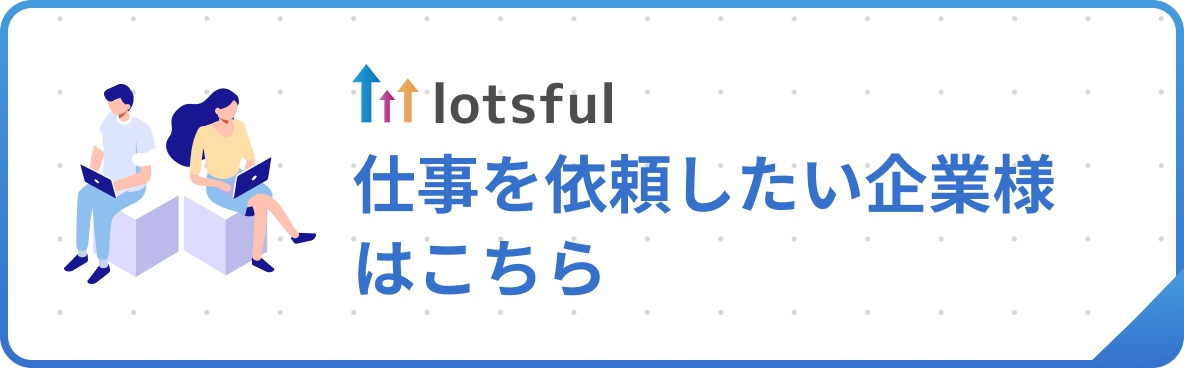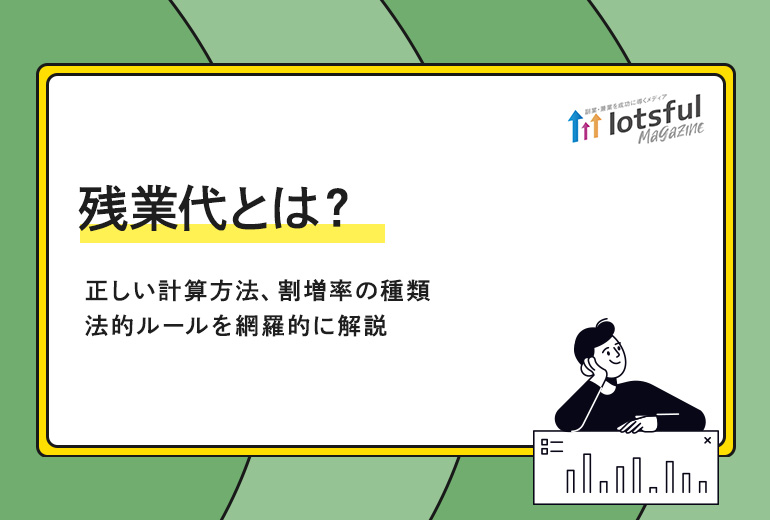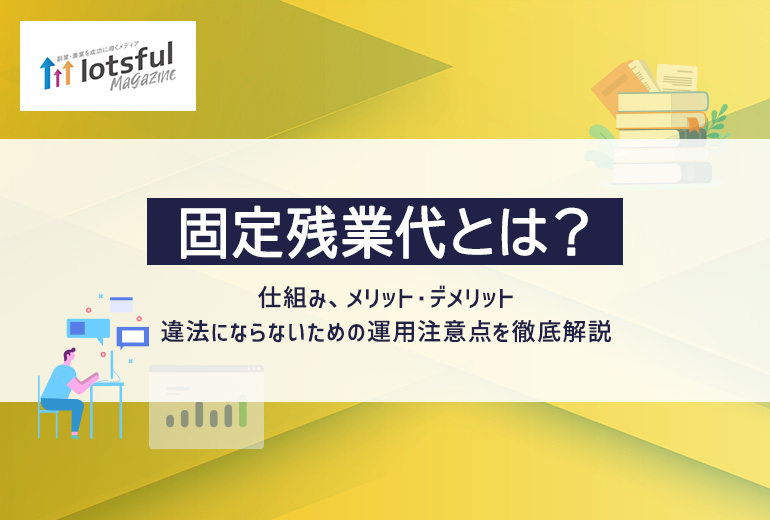採用分析とは?使うデータや分析手法、注意点まとめ
人事部や採用担当者が、無駄なく効果的に自社の採用活動を実施するには、採用分析のプロセスが欠かせないものといえるでしょう。
ただし、効果的な採用分析を行うためには、さまざまなポイントが存在するため、経験値の高い副業人材の活用も有効です。本記事では、採用分析に用いるデータや手法に加えて、リスク回避のポイントや注意点も踏まえ、詳しく解説します。
関連記事:
・人事データの集計時間が1/10に!副業人材がデンソーの「人材ポートフォリオの最適化」に貢献
採用分析とは
自社の採用活動における状況や成果を、さまざまなデータから把握し、課題や改善点を見出していくことが、採用分析です。
データに基づいて分析する主な項目は、以下の6つとなります。
| 各採用プロセスでの歩留まり | どのプロセスで候補者の離脱があるかを特定 |
|---|---|
| 採用チャネルごとの成果 | 各チャネルの応募数や内定数から、どのチャネルが効果的かを判断 |
| 採用コスト | 1名あたりの採用単価や採用活動全体でかかったコストから、 採用予算の最適化を図る |
| 採用までにかかった時間 | 応募~内定、内定~入社に至るスピード感を把握し、改善を図る |
| 内定辞退率と入社辞退率 | 辞退理由を分析し、内定後のオファー改善を実施 |
| 入社後の定着や活躍状況 | 入社後の離職率や活躍状況を通じて、結果として質の高い採用が できているかどうかを判断 |
採用分析に使う主なデータ
採用分析に用いる主なデータとしては、以下の8つが挙げられます。
応募数・エントリー数
採用分析を実施するうえで、自社求人へ実際に応募した人数や、サイトなどへアクセスしてエントリーを行った人数の把握は、最も重要な分析データといえるでしょう。
応募数とエントリー数からは、次のような状況が把握できます。
| 応募数 | 履歴書などの応募書類を企業へ提出することにより、選考対象としてカウント できるため、書類選考以降のプロセス分析が可能 |
|---|---|
| エントリー数 | 応募には至っていないが、自社に強い興味を持っているため、母集団形成時の指標となる |
書類通過率・面接通過率・内定率
自社求人に対して応募があった場合、「書類選考」「面接」「内定」の3つのプロセスごとに、突破した候補者の割合を分析します。
3つのプロセス別に算出した結果を分析することで、次のような状況改善に役立つでしょう。
| 書類通過率 | 書類通過率が極端に低い場合、採用基準が厳しすぎる可能性があるため、 求人内容の見直しが必要 |
|---|---|
| 面接通過率 | 面接官によって通過率にばらつきがある場合、評価基準の統一が必要 |
| 内定率 | 最終的な歩留まりを確認し、内定率が低い場合は、採用要件の見直しや、 面接プロセスの質やスピード感の向上が必要 |
内定承諾率・辞退率・入社率
選考を突破して内定を獲得した候補者のなかには、残念ながら入社まで至らないケースもあります。
「内定承諾率」「辞退率」「入社率」のデータ分析を行い、次のような改善策で対応しましょう。
| 内定承諾率 | 内定承諾率が低い場合、オファー内容を検証して改善する |
|---|---|
| 辞退率 | 辞退理由を把握し、オファー内容の改善や内定者へのフォロー体制を強化する |
| 入社率 | 入社率が低い場合、内定から入社までの期間短縮や内定者フォローを徹底する |
採用チャネル別の応募者数・通過率・採用単価
自社が用いた採用チャネル別に、「応募者数」「通過率」「採用単価」の分析を行うことで、採用コストの最適化だけでなく、採用活動全体の質向上にも役立ちます。
以下のような状況が発生した場合、それぞれ適切な対処が必要です。
| チャネル別応募者数 | チャネル別に応募者数を比較し、十分な応募数を確保できているか確認する 応募数が少ない場合は、ターゲット層とチャネルがマッチしているか見直す |
|---|---|
| チャネル別通過率 | 通過率の低いチャネルは、求人内容とのミスマッチの可能性があるため、 ターゲット条件を絞った出稿や内容の見直しを実施する |
| チャネル別採用単価 | 高単価でも候補者の質が低い場合、SNSやリファラル採用などを活用し、 低単価でも効果の高いチャネルへシフトする |
採用までの期間(リードタイム)
募集開始から採用までに要した期間が「リードタイム」です。候補者の多くは複数社へ応募しているケースが多く、選考スピードが遅いと、競合に人材が流れる要因になります。
また、リードタイムが長引けば、その分採用コストや人事担当者の負担も大きくなるでしょう。採用スピードと質の両立に向け、各選考プロセスを分解したうえで、改善可能な目標を設計しましょう。
面接評価スコア・選考フローごとの歩留まり
採用分析において、面接評価スコアは面接官ごとの傾向を把握するだけでなく、採用要件と候補者の一致度も確認できます。
また、選考フローごとの歩留まりは、候補者の離脱を可視化できるため、課題の発見や媒体の見直しにも役立つでしょう。
採用後の定着率・離職率・活躍度(パフォーマンス指標)
採用後の社員定着率や離職率、さらにパフォーマンス指標となる活躍度を分析することで、採用の質に関する評価や採用要件の改善が行えます。
以下は、「定着率」「離職率」「活躍度(パフォーマンス指標)」で問題があった場合の対処法です。
| 定着率 | 面接時の見極め不足や求人内容と入社後のギャップが原因となるケースが多いため、選考時には業務内容や社風についても正直に伝え、納得感を得る |
|---|---|
| 離職率 | 上記の要因に加え、育成や相談できる環境がないことによる離職も多いため、オンボーディングの強化やメンター制度の導入を行う |
| 活躍度 (パフォーマンス指標) |
社員のスキルや志向と現場ニーズを精査したうえで育成し、定期面談などを通して、目標設定や評価の改善を行う |
採用ターゲットと実際の応募者・入社者の属性差
具体的な採用ターゲット像を設定していても、実際の応募者や入社者の属性にズレが生じる場合があります。両者に乖離があると、早期離職や十分な活躍が期待できない結果となるでしょう。
実際の応募者や入社者の属性差を分析することで、現実に見合ったターゲット設定だけでなく、ターゲット外でも活躍可能な人材の再評価が実現します。
採用広報や求人広告のPV・CVR(応募転換率)
自社に合う応募者を増加させるために、採用広報は欠かせません。また、求人広告のPV(Page View/閲覧数)は、候補者の認知や興味・関心の大きさを。CVR(Conversion Rate/応募転換率)は、コンテンツや訴求の質を測る重要な指標です。
これらのデータを適切に分析し、改善していくことで、採用活動における無駄なコストを減らし、媒体選定を最適化できるでしょう。
採用分析の主な手法
採用分析における主な手法として、以下の7つが多く用いられています。
KPI分析(通過率・承諾率などの数値比較)
選考通過率や内定承諾率などの数値比較に有効なのが、KPI(Key Performance Indicator/重要業績評価指標)分析です。どの段階で候補者が離脱しているかを可視化できるため、ボトルネックとなっている要因を特定できます。
KPI分析では、数値比較によって自社が抱える課題を正確に把握し、改善策を具体的に設計・実行・検証するサイクルを確立できるでしょう。
チャネル分析(求人媒体や紹介元ごとの効果測定)
各種求人媒体や紹介元別に「応募数」「通過率」「採用数」「コスト」などの効果測定や比較を行うのが、チャネル分析です。ただ人を集めるだけでなく、戦略に基づいた効果的な採用が実現します。
チャネル別の一人あたりの採用単価が把握できるため、採用コストの最適化が叶うほか、媒体ごとの応募者数や質の可視化により、適切な母集団形成に貢献します。
クロス集計(属性別に採用状況を分析:学歴×通過率など)
候補者属性を軸に、選考通過率や内定率といった採用状況も踏まえた分析を行うのが、クロス集計です。クロス集計では、たとえば学歴×通過率など、特定の属性による通過率の高低を可視化できます。
クロス集計により、ターゲット層の最適化ができるうえ、属性別に適した採用手法やチャネルの選択が可能です。また、属性別の離脱ポイントを特定できるため、歩留まり改善にも役立つでしょう。
トレンド分析(月別・年別など時系列での変化を可視化)
応募数や選考通過率、内定率といった採用指標を、月別や年別に集計し、時系列での変化を可視化する手法が、トレンド分析です。
月や年単位での採用指標の変動が明確になるため、採用効果が高まる時期や、逆に低下する時期の把握が容易になるでしょう。自社の採用活動を時間軸で評価し、改善できる点が最大のメリットです。
ペルソナ分析(活躍人材の傾向を数値化・類似候補発見)
自社で活躍している人材の共通傾向を抽出したうえで数値化し、類似候補の発見につなげる手法が、ペルソナ分析です。ペルソナ分析により、感覚頼みではない人材採用が確立するでしょう。
既に自社に定着し、成果を上げている人材をモデル化することで、あらかじめペルソナにそぐわない候補者の見極めが可能です。ミスマッチの少ない採用が実現する点で、非常におすすめできる手法です。
採用コスト分析(採用単価、CPAの算出と改善)
自社の採用活動にかかる費用を分析し、一人あたりの採用単価であるCPA(Cost Per Acquisition)を算出して、改善につなげる手法が採用コスト分析です。
媒体や職種、ポジション別の費用対効果が把握できるようになるため、予算配分がスムーズかつ最適化できます。採用コスト分析を行うことで、予算をただ使うだけでなく、戦略的な投資へと昇華できるでしょう。
タレントアナリティクス(入社後の活躍・定着との関連を分析)
採用時の候補者データと、入社後の活躍や定着、成長度合いなどを関連づけて分析する手法がタレントアナリティクスです。この分析により、どのような人材が活躍し、定着しやすいかが明確になります。
タレントアナリティクスによって、採用だけでなく中長期的な成果を見据えた戦略的な人材確保が可能になり、育成やその後の配置も含めて一体化した改善ができるようになるでしょう。
採用分析のポイントや注意点
採用分析を行う際に、意識しておきたい7つの「ポイント」および「注意点」を以下で解説します。
目的を明確にし、改善につながる指標に絞って分析する
採用分析を実施しても、「自社の採用活動で、そもそも何を改善したいか?」といった目的が不明瞭な場合、単なる数字の集計で終わってしまいます。
分析数値は採用プロセスごとに存在しますが、すべてを選択する必要はありません。自社の課題を踏まえ、改善につながる指標に絞って分析しましょう。たとえば、内定数に課題がある場合は、面接通過率やオファー受諾率を指標にして、効果的な施策を講じるとよいでしょう。
定量だけでなく定性データ(候補者の声・現場評価)も組み合わせる
採用分析では、応募数や選考通過率、辞退率といった定量データを追うことからスタートします。ただし、定量データのみでは、選考通過率の低さや辞退率の高さの理由までは判明しません。
選考時の不満といった候補者の声や、面接後の総括をはじめとする現場評価など、定性データを組み合わせることで、改善すべき課題がよりクリアになります。
分析結果を可視化し、関係者にわかりやすく共有する
採用分析の最終的な着地点は、自社がどのような課題を抱えているかを関係者にわかりやすく伝え、改善に向けた行動を促すことです。
このため、分析結果はグラフや図などを用いて視覚的に把握できるようにしましょう。そのうえで、関係者全員が明確になった課題に対する共通認識を持てるようになれば理想的です。
KPIの定義を統一し、正確なデータを蓄積・管理する
KPIの定義を統一する最大のメリットは、社内関係者全員が同一基準で現状把握できるうえ、改善の方向性も定まる点です。
さらに、限られた月のみのデータでは数値にブレが生じ、判断を誤りがちです。正確なデータの蓄積と適切な管理を行っていけば、自社における採用の現状が正確に把握でき、効果的な改善につながるでしょう。
採用フローや評価方法が変わった場合は比較に注意する
採用分析で重要なのは、「これまでの採用活動とどう変わったか?」を比較し、改善していくことです。特に、選考通過率や内定率に大きな影響を与える採用フローや評価方法を変更した場合には、注意が必要です。
変更後に書類選考通過率が上昇したように見えても、候補者の質が向上したわけではなく、採用要件を緩和した結果であるケースもあります。そのため、変更を無視して単純に比較しないようにしましょう。
短期的な数値だけでなく、中長期の成果(定着・活躍)も見る
採用分析は、単に入社数の達成=成功ではありません。入社数だけでなく、応募者数や選考通過率といった指標は、あくまで短期的な指標であり、ほんの入口の成果にすぎません。
採用活動の最終的な目的は、入社した採用者が自社に定着し、成果や利益を生み出して活躍することです。採用分析時には、候補者の中長期的な成果も見据えた指標に基づき、モニタリングしていきましょう。
数値に一喜一憂せず、トレンドや原因に注目する
一時的な数値だけを見て、すぐに施策を変更するなどの行動を取ると、本質的な課題解決にならないばかりか、現場が混乱する原因にもなります。
採用データは、時期や競合企業の動向などによって日々変動していきます。限られた期間のデータ変動に一喜一憂せず、年間を通じた推移を確認しながらトレンドを読み取り、数値変化の原因を探ったうえで、適切な対処を行いましょう。
御社の業務に副業社員を検討してみませんか?
今回は、効果的な採用分析について、企業が知っておきたい情報をポイントや注意点を交えながらお届けしました。
御社の採用分析だけでなく、業務全体の質向上を目指すのであれば、新たな採用チャネルとして副業人材専門のプラットフォーム活用もおすすめです。
副業人材マッチングサービス「lotsful」なら、企業のさまざまな課題を優秀な副業社員によって、迅速に解決へと導きます。
コストや工数負担をあまりかけずに、お望みのスキルを持つ人材と出会えるのが「lotsful」の最大のメリットです!人材活用に関するお悩みがある場合は、ぜひ「lotsful」へご相談ください。