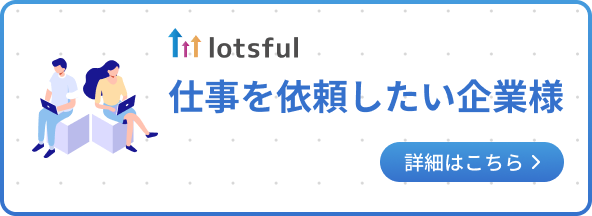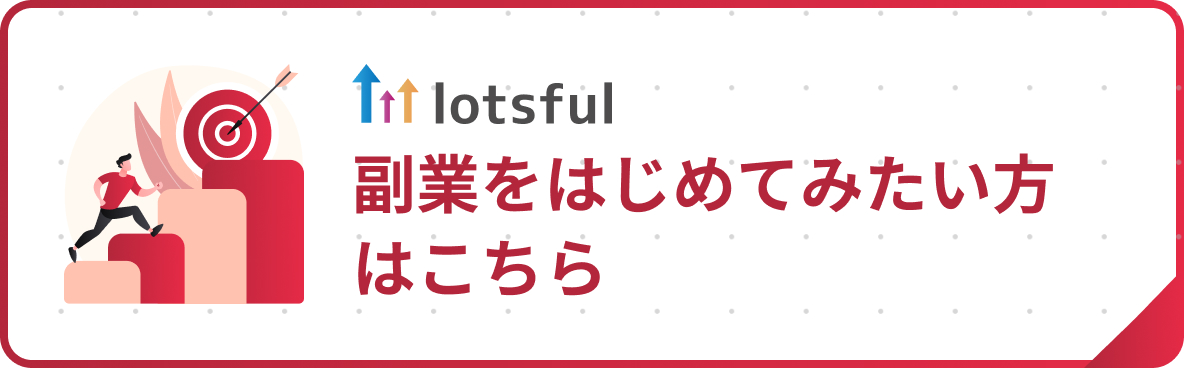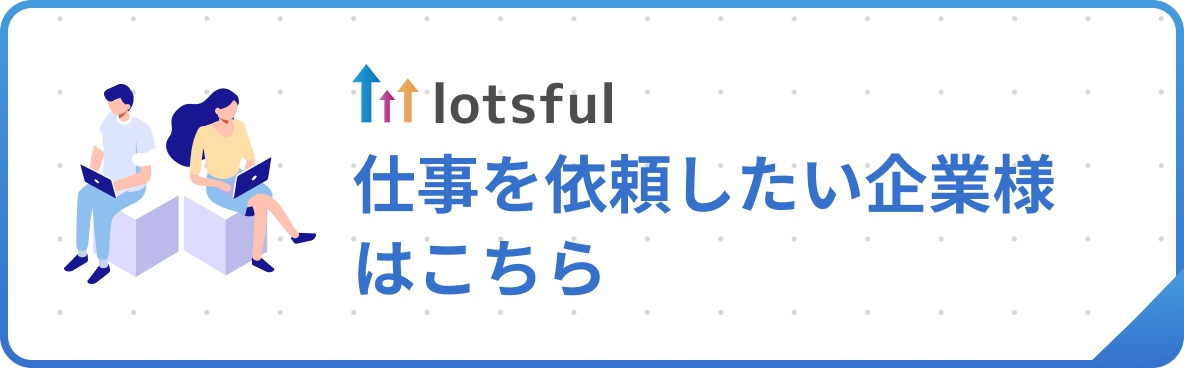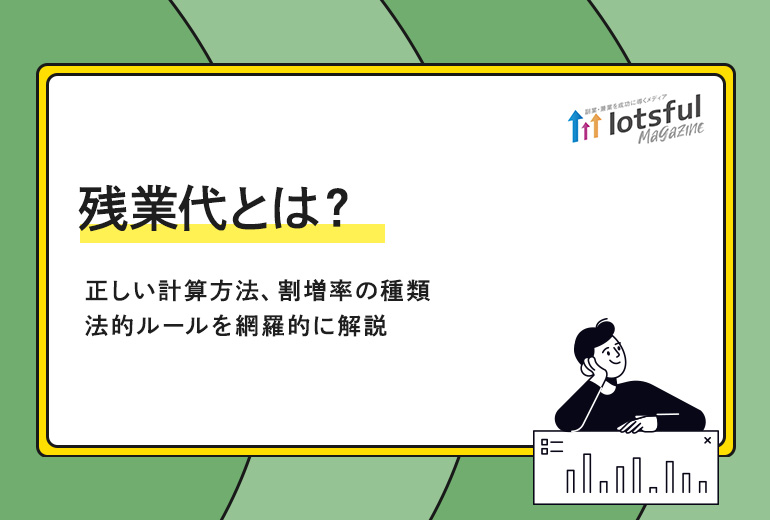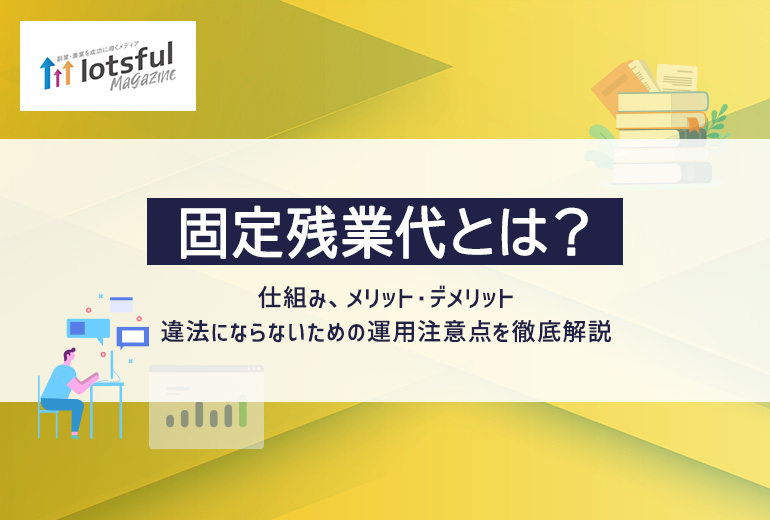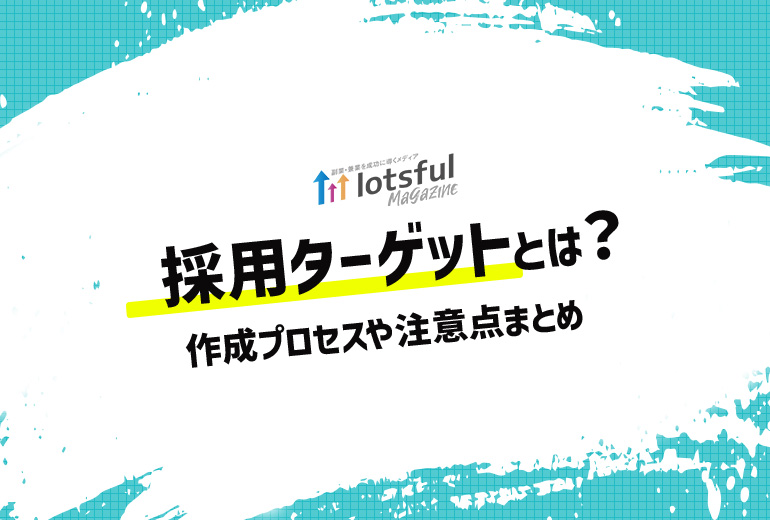
採用ターゲットとは?作成プロセスや注意点まとめ
自社のニーズにマッチした人材を獲得するには、求める人物像を具体化する「採用ターゲット」の設定が欠かせません。
また、副業社員を採用する際にも採用ターゲットを設定することで、即戦力として活躍できる人材の採用が実現します。
本記事では、採用ターゲット設定のメリットや注意点、作成時のプロセスまでを詳しく解説していきます。
採用ターゲットとは
自社の採用活動において、どのようなスキルや経験、志向性を持った人物を求めているのかを具体化したものが、採用ターゲットです。
また、採用ターゲットを設定する主な目的は、以下の3点です。
- 提供する求人情報の精度向上
- ミスマッチの少ない採用
- 効果の高い採用広報の実現
採用ペルソナとの違い
採用ターゲットと同じ意味合いで用いられることの多い「採用ペルソナ」ですが、両者には「目的」「内容の詳細度」「設定のタイミング」において違いがあります。
一般的には、まず採用ターゲットを設定し、その後に人物像をより詳細に具体化するために採用ペルソナを作成する流れが効果的とされています。
採用ターゲットと採用ペルソナを設定することで、採用基準が明確になり、各選考フローもスムーズに進むでしょう。
採用ターゲットを設定するメリット
自社の採用活動において採用ターゲットを設定することにより、以下に挙げる5つのメリットが得られます。
採用活動の効率が向上し、無駄な工数を削減できる
採用ターゲットを設定することで、採用基準が明確になり、自社のニーズにマッチした応募者の選別が容易になります。その結果、不必要なスクリーニングや面接、社内調整を減らすことが可能になります。
無駄な工数の削減は、コスト削減につながるだけでなく、採用活動全体の効率向上にも貢献します。人事担当者がコア業務に専念できるようになるため、採用活動の質も高まるでしょう。
適切な採用チャネルを選定しやすくなる
明確な採用ターゲットを設定することで、ターゲット層に適した採用チャネルを選定しやすくなるメリットがあります。
適切な採用チャネルを選ぶことで、効果の薄い求人広告の掲載が減り、無駄なコストを抑えることもできるでしょう。
面接の評価基準を統一し、選考の精度を向上させる
採用ターゲットを設定することで、面接における評価基準の統一が図られ、面接官の主観に左右されない選考が実現します。
選考精度の向上により、ミスマッチのない採用が可能となるほか、応募者にとっても入社後のギャップが少なくなるため、早期離職のリスクも低減できます。
企業文化や求めるスキルに合った人材を採用しやすくなる
採用においては、スキルだけでなく自社文化との適合も非常に重要です。たとえ高いスキルを持っていても、自社の文化に馴染めなければ早期離職につながる可能性があります。
採用ターゲットを設定することで、スキル要件だけでなく自社文化や価値観に共感する人材を採用しやすくなります。
さらに、ターゲットに合わせた採用活動を行っているため、入社後のオンボーディングもスムーズに進み、採用者の早期戦力化も期待できるでしょう。
採用メッセージや求人票を的確に作成できる
採用ターゲットを明確にすることで、採用メッセージや求人票の作成において、ターゲットのニーズや価値観にマッチした表現が可能になります。
ターゲットに向けて的確に作成された求人票は、採用候補者の共感を得やすく、応募意欲を高めることができるでしょう。
また、的確なメッセージが盛り込まれた求人情報は、自社の認知度や好感度アップにも貢献するため、採用ブランディングの強化にもつながります。
採用ターゲットの作成プロセス
採用ターゲットの作成プロセスでは、以下に挙げる7つのステップを踏む必要があります。
1. 自社の事業戦略・組織課題を分析
採用活動は、常に自社の中長期的な事業戦略と連動していく必要があります。最初のステップとして、自社の事業戦略だけでなく、組織課題を分析することで、自社の成長に大きく貢献する人材の獲得が可能になります。
分析を進める際は、「事業の方向性」「現場が抱える課題」「求める人材要件」に注力して進めていきましょう。
2. 活躍している社員の共通点を整理
効果的な採用ターゲット設定を実施するためのステップ2として、自社で活躍している社員の共通点を整理することが重要です。共通点を可視化することで、成功しやすいターゲット設定が実現します。
成果を出している社員のスキルや経験に加えて、行動や志向性を把握し、自社で能力を発揮しやすい人物像を具体化していきましょう。
3. 必須スキル・経験・価値観を定義
自社で活躍する社員の共通点が可視化できたら、次のステップとして、求める人材の必須スキル・経験・価値観を定義していきます。
これら3つを具体的に定義することで、自社でより能力を発揮できる人材の見極めがしやすくなります。
ただし、自社全体に共通する価値観と、営業や技術職といった職種特有のスキルは個別に設定し、分けて管理するようにしましょう。ポジションに応じた、適切かつ柔軟な採用活動が実現します。
4. ターゲット像を作成
スキル・経験・価値観の定義が完了したら、年齢層や学歴・職歴といった基本的な情報からパーソナリティまでを含めた、具体的なターゲット像を作成するステップに進みます。
例:「現在〇歳、製造業界で〇年のリーダー経験あり。マネジメント職を目指し、チームワークを重んじながら裁量度の高い組織づくりを希望している。高い行動力とフットワークの軽さが強み。」
このように具体的なペルソナ像を設定し、関係者が共有しやすいように明文化しておきましょう。
5. 採用チームと共有し、ブラッシュアップ
明確なターゲット像を作成したら、採用チームと共有し、さらにブラッシュアップを図るステップに入ります。
この際に重要なのは、現場との認識にズレが生じないようにすることです。ターゲット像を現場の責任者などに提示し、求める人物像とマッチしているかを確認してもらいましょう。
また、採用チームの面接官とは、ターゲット像に基づいた評価項目を再確認し、この時点で曖昧な部分があれば調整を行うなど、実用化に向けて仕上げていきます。
6. ターゲットに適した採用チャネルを選定
各部署と連携しながら詳細なターゲット像を完成させても、適切な採用チャネルが選定されていなければ、効果にはつながりません。
ターゲット像にリーチしやすい採用チャネルを選定することで、無駄なコストや工数を削減することもできます。
また、採用チャネルは併用することで採用リスクを分散できます。たとえば、即戦力を重視する場合はダイレクトリクルーティングや人材紹介を、若年層が対象の場合はSNSや若手特化型の求人媒体を活用するとよいでしょう。
7. ターゲットの反応を分析し、定期的に見直す
採用ターゲット作成の最終ステップは、各採用チャネルを通じたターゲットの反応を詳細に分析することです。
「ターゲット層からの応募が少ない」「内定辞退が多かった」といった結果が見られる場合には、設定を見直す必要があります。
分析結果と市場ニーズに基づき、定期的な見直しを行うことで実際の応募状況とのズレを防止し、採用効果を最適化できるでしょう。
採用ターゲットをより具体化する方法
採用ターゲットをより具体化することで、採用活動の効率だけでなく、応募の質も向上します。以下に挙げる3つの方法により、採用ターゲットの具体化と採用効果の最大化が実現します。
過去の採用成功・失敗事例を分析し、傾向を把握する
採用ターゲットをより具体化するには、過去の採用実績を「成功事例」だけでなく「失敗事例」も含めて分析することが重要です。
成功事例としては、現在活躍する社員の傾向を、失敗事例としては早期離職に至った社員について、それぞれ共通点と相違点を抽出しておきましょう。
そのうえで、入社後の活動パターンについて、「なぜ成果が出せたのか」「なぜ離職に至ったのか」を分析します。こうした傾向を把握し採用ターゲットに落とし込むことで、再現性の高い採用が実現します。
現場社員やマネージャーにヒアリングする
これから採用する人材に対して、求められるスキルや価値観、行動傾向をもっともリアルに理解しているのは、現場で活躍する社員やマネージャーです。
人事担当者では見落としがちな、実務において本当に必要とされる能力やパーソナリティをヒアリングすることで、より現実的で実効性のある採用ターゲット像が浮かび上がるでしょう。
データを活用し、応募者の傾向や離職理由を分析する
応募者だけでなく、入社後に離職した社員のデータを活用すれば、採用ターゲットを改善した、より精度の高い設定が可能になります。
応募者については、「年齢」「性別」「経歴」「応募経路」「選考通過率」などのデータを分析することで、どの層が自社にもっともマッチしているかを洗い出すことができます。
また、離職した社員に関しては、離職理由だけでなく入社後の評価も含めたデータを分析することで、自社とミスマッチとなる人材の傾向を把握できるはずです。
採用ターゲット作成時の注意点
採用ターゲットを作成する際は、以下に挙げる4つの注意点があることを認識しておきましょう。特に、設定初期段階で見落としがちな注意点を把握しておくことで、採用活動全体の精度が向上します。
要件を厳しくしすぎない
スキルやパーソナリティともに優れた人材を求めるあまり、要件を厳しく設定してしまうと、応募数そのものが減ってしまいます。
母集団形成が不十分な場合、条件にマッチする人材も少なくなるため、採用が長期化するおそれもあるでしょう。
あらかじめ「必須とする要件」と「あれば望ましい要件」を設定し、現場と調整しながら妥協点を共有する、柔軟性のある対応が肝心です。
スキルや経験だけでなく、企業文化との適合性も考慮する
スキルや経験だけにフォーカスしてしまうと、自社文化に合う人材を見落とす可能性があるため、この点も重要な注意点の一つとして捉えておく必要があります。
スキルや経験値の高い人材は、即戦力としての活躍が期待できます。ただし、自社文化との適合性が低い場合、モチベーションの低下を招き早期離職につながるおそれがあります。
一方で、自社文化に共感する人材は帰属意識も高く、目標に向けて自発的に行動するため、組織の生産性向上にも寄与するでしょう。
採用市場の実情に合った現実的なターゲット設定をする
自社が理想とする採用ターゲットを設定しても、採用市場の実情と合っていなければ、思うような成果には至らないでしょう。この点も、採用ターゲット作成時の注意点として見逃せないポイントです。
このため、採用市場でニーズの高いスキルセットや経験値を考慮したターゲット設定が重要です。現実的なターゲット設定を行うことで、応募者が集まりやすくなり、採用の質とスピードも格段に向上します。
経営層・現場・人事の意見を統合し、一貫性を持たせる
採用ターゲット設定時に「経営層」「現場」「人事」の意見や認識が統一されていないと、採用活動全体に大きなズレが生じてしまいます。
三者の視点をうまく擦り合わせることで、求人情報の内容や面接時の評価基準にも一貫性を持たせることが可能です。
採用活動に一貫性のある企業は、ミスマッチな採用を回避できるだけでなく、入社後のギャップも少ないため、早期離職のリスクも抑えられるでしょう。
このような連携体制を整えることで、採用ターゲットの設定から採用完了までのプロセス全体に一貫性が生まれ、より精度の高い採用活動を実現できます。
御社の採用業務を副業社員に任せてみませんか?
今回は、採用活動の質向上に貢献する採用ターゲットに関して、メリットだけでなく、実務上の注意点も踏まえながら、役立つ情報をお届けしました。
採用ターゲットの策定から実際の募集・選考まで、一連のプロセスにおいて課題が発生しやすい箇所を把握することが、採用活動を成功に導くカギとなります。
採用業務に課題があり、早急な解決にお悩みであれば、副業社員の力を借りて解決するのもおすすめの方法です。御社の採用業務において、即戦力として活躍可能な副業社員をお探しなら、ぜひ一度「lotsful」へご相談ください。
コストも時間もかけずに優秀な人材と出会えることが、副業人材マッチングサービス「lotsful」活用の最大の魅力です。
また、専属のエージェントによるきめ細やかなサービスがあるため、初めてご利用いただく場合でも安心してお任せいただけます。