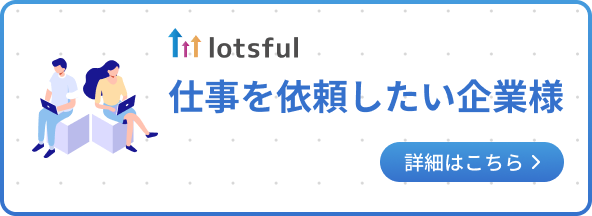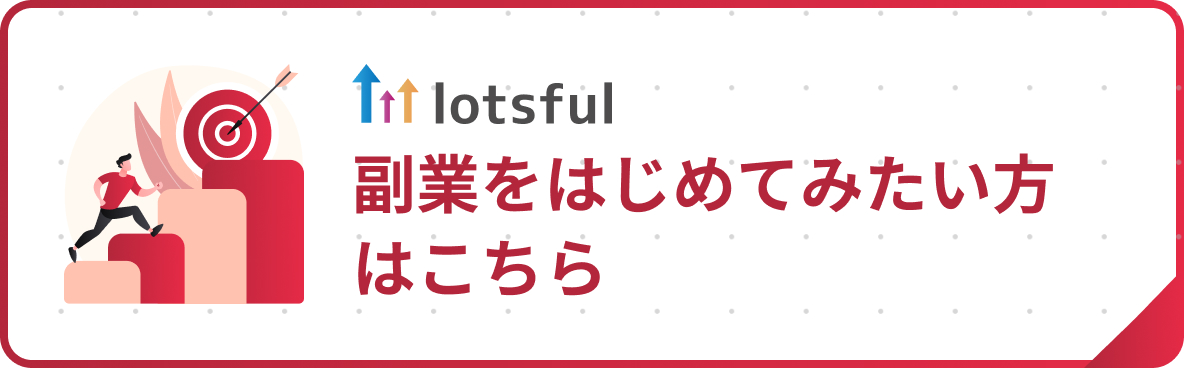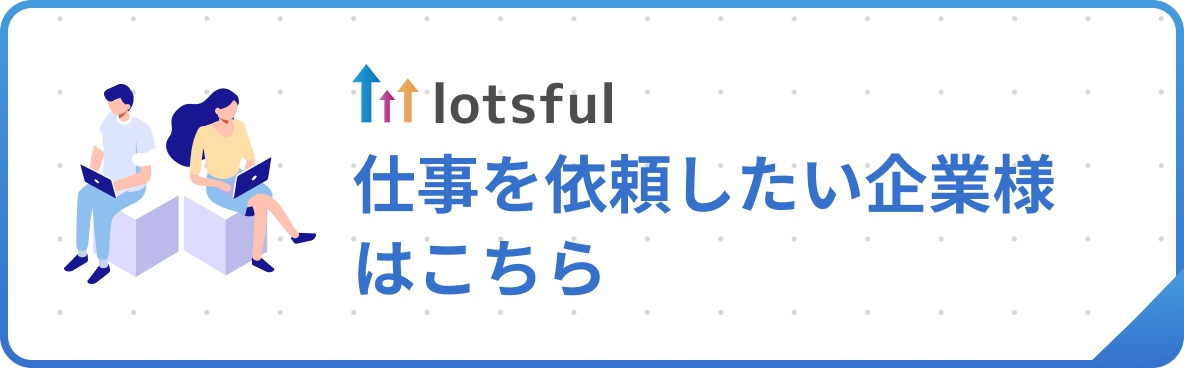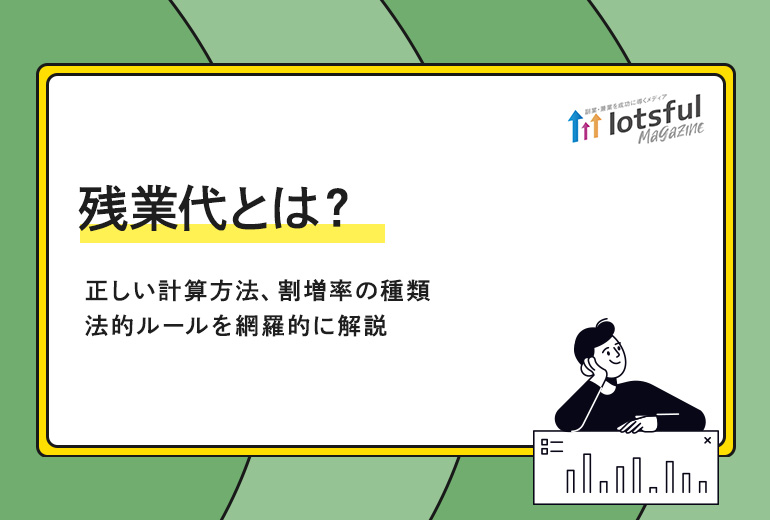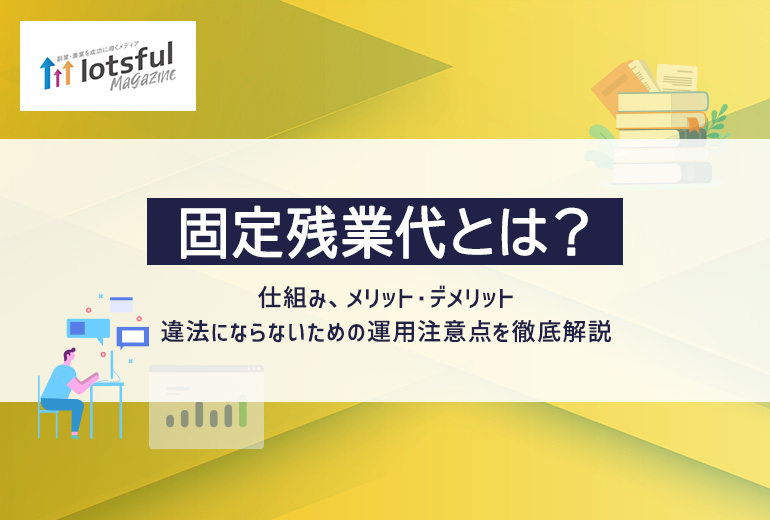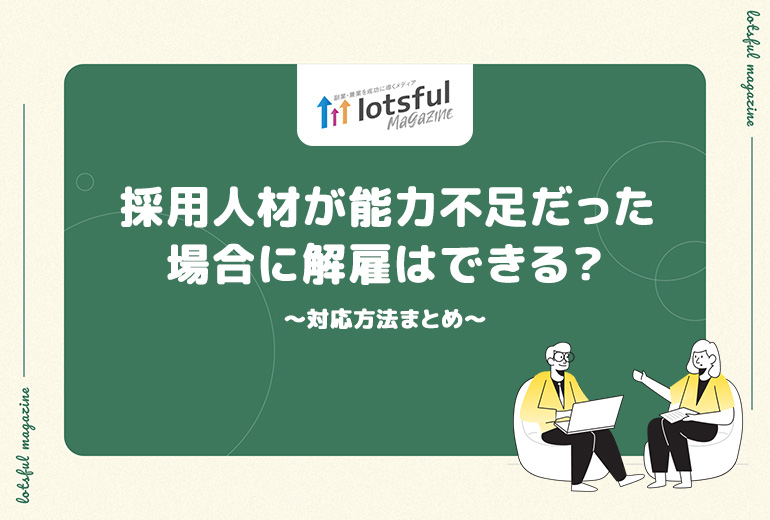
採用人材が能力不足だった場合に解雇はできる?対応方法まとめ
有能な正社員に限らず、即戦力となる副業人材の獲得という採用競争を勝ち抜くために、企業はさまざまな策を講じる必要があります。
しかし、時間と労力をかけて採用した人材が能力不足であった場合、どのように対応すべきか悩む企業も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、採用人材の能力不足について、「解雇の可否」や「取るべき対応」などを詳しく解説いたします。
人材が能力不足だった場合、解雇はできる?
さまざまな選考過程を経て採用に至った人材の能力不足が発覚した場合、その事由のみで解雇することは、非常に難しいといえるでしょう。
解雇の定義については、労働契約法第16条(※)において、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできない」とされています。
たとえば、採用した人材が能力不足であったとしても、起こしたミスや企業が被った物理的な被害などに関する客観的な評価や記録がない状態では、解雇は認められません。
合理的な理由や記録がなく、具体的な改善の機会を与えず、本人の意見も聴取しないなど、然るべき対応を取らないまま解雇通告を行った場合には、不当解雇と判断される可能性が高いため、十分な注意が必要です。
※出典:厚生労働省HP「労働契約の終了に関するルール」
人材が能力不足だった場合の対応
以下では、採用した人材が能力不足だった場合に企業が取るべき7つの対応を紹介します。
業務内容や期待値を明確に伝え、改善の機会を与える
採用した人材の能力不足が明らかになった場合でも、改善の機会を設けることが重要です。該当者が業務内容や進め方を十分に理解していないことにより、本来の能力を発揮できていない可能性も考えられます。
このため、改めて該当者と面談の機会を設け、任せる業務の内容について、範囲や達成基準などを明確に伝えることが求められます。
たとえば、「業務報告書は、月末の最終営業日までに必ず提出する」「今期内に〇件の顧客訪問を実施する」など、自社が求める水準を具体的かつ無理のない範囲で提示しましょう。
OJTや研修を実施し、スキルアップを支援する
能力不足と感じられる人材であっても、OJTや研修を再実施することで、改善が見込まれるケースもあります。また、はじめから多くの業務を一度に任せるのではなく、「できそうな仕事」から少しずつ担当させることで、段階的なスキルアップが期待できるでしょう。
業務自体に対する理解力や遂行能力に課題がある場合は、実際の業務フローを改めて説明し、一つひとつ確認していくことが効果的です。
また、業務マニュアルに基づきながら教育担当者が手本を示し、該当者にも実践してもらい、改善点をフィードバックする研修も有効です。
業務の進捗を定期的に確認し、フィードバックを行う
該当者が業務の進捗において問題を抱えている場合、業務の流れを理解しないまま進めている可能性があります。また、該当者の些細なつまずきが見過ごされてしまうと、やがて業務全体に悪影響を及ぼす原因にもなりかねません。
このため、業務進捗に関する定期的な確認とフィードバックを行うことで、問題の早期発見が可能となるだけでなく、該当者自身の気づきや学びの機会にもつながります。
配置転換や業務の調整を行い、適性に合った役割を探る
該当者と配属されたポジションや業務量が見合わず、自身の強みや適性を発揮できていない可能性もあります。この場合、配置転換や業務の調整を行うことで、状況が改善されることもあるでしょう。
また、ジョブローテーションを実施することで、該当者の適性にマッチしたポジションが見つかるケースもあります。現場とも情報や認識を共有しながら、該当者の適性に合う役割を模索していきましょう。
明確な目標を設定し、達成度を評価する仕組みを作る
該当者に限らず、「この仕事を通じて何を達成すべきか」という目的があいまいな場合、社員は目の前の業務をこなすだけになってしまいがちです。
このため、KPIや具体的な成果基準などによって業務達成度を評価する仕組みを構築するだけでなく、定期的にフィードバックを行いながら、該当者の成長を支援する環境を整えることが重要です。
本人と面談を行い、課題認識と改善意欲を確認する
能力不足が見られる該当者は、「何が問題で、自分がなぜ失敗するのか」といった根本的な自覚を持っていない可能性があります。
このため、本人との面談を通じて、問題点の洗い出しと原因の把握を行う必要があります。たとえば、常に書類の提出期限に間に合わない場合、タスク管理やスケジュール管理に課題があるかもしれません。
問題の原因を探るだけでなく、「どうしたら改善できるか」についてアドバイスを行うと同時に、該当者自身の改善意欲を引き出すようにしましょう。
最終的に改善が見られない場合、降格や異動を検討する
継続的な支援を行っても、残念ながら該当者に改善が見られないケースもあります。その場合には、該当者の状況や適性を踏まえたうえで、降格や異動を検討することもやむを得ないでしょう。
ただし、事前の説明もなくこうした対応を実施してしまうと、トラブルの原因になりかねません。これまでの記録に基づき、該当者の業務上の行動が組織に及ぼした影響を丁寧に説明しましょう。
そのうえで、将来的な見地から降格や異動が望ましい旨を伝え、該当者に納得してもらうことが重要です。
不当解雇とみなされないための解雇方法
採用した人材が能力不足であっても、正当な理由がなければ不当解雇とみなされる可能性があります。解雇に向けて対応を進める場合には、以下に挙げる5つの方法を実践することで、トラブルの回避につながるでしょう。
就業規則や労働契約書に基づいた正当な理由を明示する
不当解雇とみなされないためには、就業規則や労働契約書に基づき、「該当者が起こした問題が何に抵触しているのか」を明示することが肝心です。
該当者に対して、企業としては面談や研修などで改善の機会を与え、本人からも書面で改善する旨の報告があったにもかかわらず、契約上問題となる結果に至った場合には、正当性のある解雇理由となります。
能力不足の具体的な事例や改善指導の記録を残す
能力不足による解雇の正当性を担保するには、該当者による具体的な事例と、これまでの改善指導の記録がカギを握ります。
まず、該当者の業務におけるミスの内容や頻度、自社に与えた具体的な影響などの記録が重要です。そのうえで、行った改善指導の内容も詳細に記録し、再指導によってどのような改善が見られたか、あるいは改善が見られなかったかを、数値などで記録しておきましょう。
本人に十分な説明と改善の機会を与える
該当者の能力不足やミスを一方的に指摘するのではなく、「何が原因で、どのような経緯で問題が発生したか」を、本人に丁寧に説明させる場を設けることが重要です。
本人の説明により原因や経緯が明らかになった場合は、きちんと改善の機会を与えましょう。このとき、具体的な目標と評価基準を設定した改善計画を作成し、いつまでに改善するかという期限も明確に決めておきましょう。
段階的な指導(指導・ 警告・最終通告)を行う
最終的に該当者が解雇される結果となる場合でも、不当解雇とみなされないよう、合理的かつ客観的な視点でのプロセスを踏む必要があります。
以下に挙げる3段階の指導を経ても該当者の問題が改善されない場合は、解雇に至る正当な理由となる可能性が高まります。
| 指導 | 口頭での注意や指導、該当者との面談による課題の洗い出しと改善意欲の確認を行い、本人の反応や意見を含め、内容を記録する |
|---|---|
| 警告 | 口頭での注意や面談実施などで改善されない場合は、人事部・上司立ち会いのもと、指導書などによる書面交付を行い、正式な警告を与える |
| 最終通告 | 指導と警告を経ても改善が見られなかった場合、面談を通じて次回は解雇処分の可能性があることを記載した最終通告書を交付し、書面により通知する |
解雇を決定する前に、配置転換や異動の可能性を検討する
該当者の解雇を決定する前に、配置転換や異動の可能性を検討することは、企業が改善を促し雇用を維持する努力を行った証拠になります。
該当者に対して配置転換や異動を示唆する際には、実際の打診内容と該当者の反応や意見を含めて、きちんと記録に残しておきましょう。そうすることで、最終的に解雇に至った場合でも、不当解雇とみなされる可能性は極めて低くなるでしょう。
御社の業務を副業社員に任せてみませんか?
今回は、採用人材の能力不足に関する対応についてご紹介しました。縁あって採用した人材に問題があった場合でも、できれば解雇という最終手段は避けたいところです。
このような状況を未然に防ぐためにも、雇用前に適性をしっかりと見極めることが重要ですが、面接だけで判断するのはなかなか難しい側面もあります。もし御社が採用に課題を抱えている場合は、どのような人材が現場で活躍できるのか、副業社員の導入を通じて検証してみてはいかがでしょうか。
専属のエージェントがゴールまで伴走する副業人材マッチングサービスの「lotsful」なら、御社の求めるスキルを有した副業社員の獲得が、初期費用0円でスピーディーに実現可能です。
採用コストと工数を抑えながら、優秀な人材を獲得するなら、ぜひ一度「lotsful」へご相談ください!