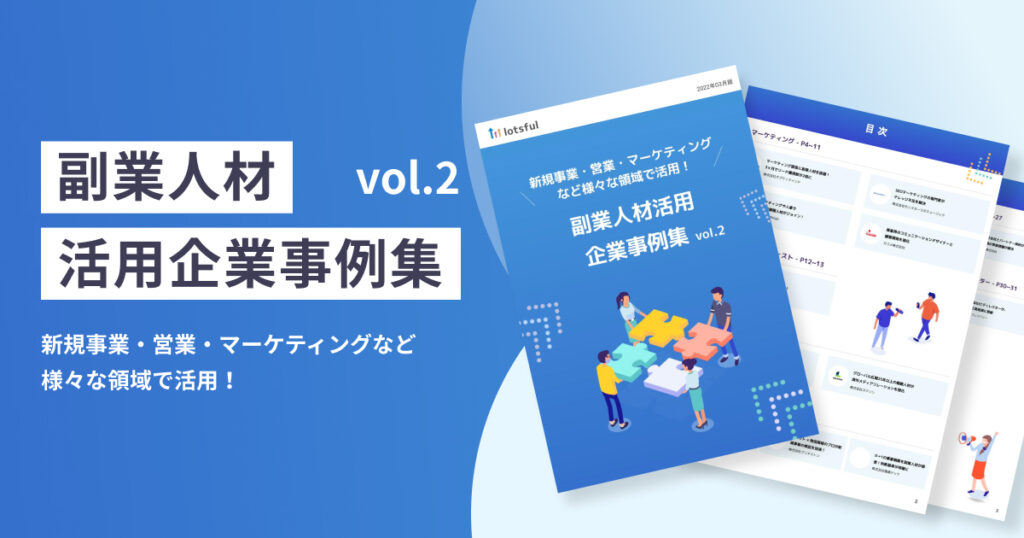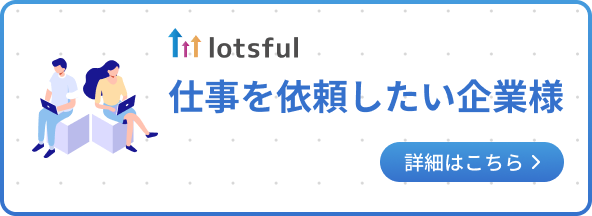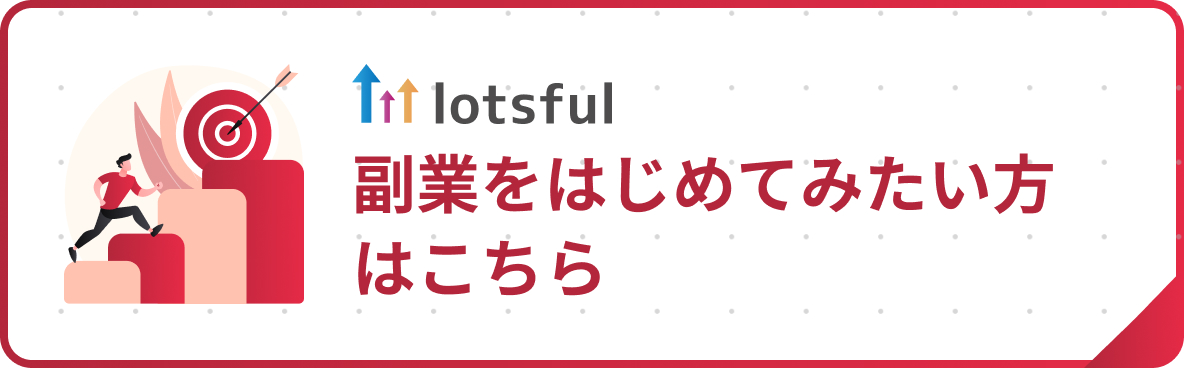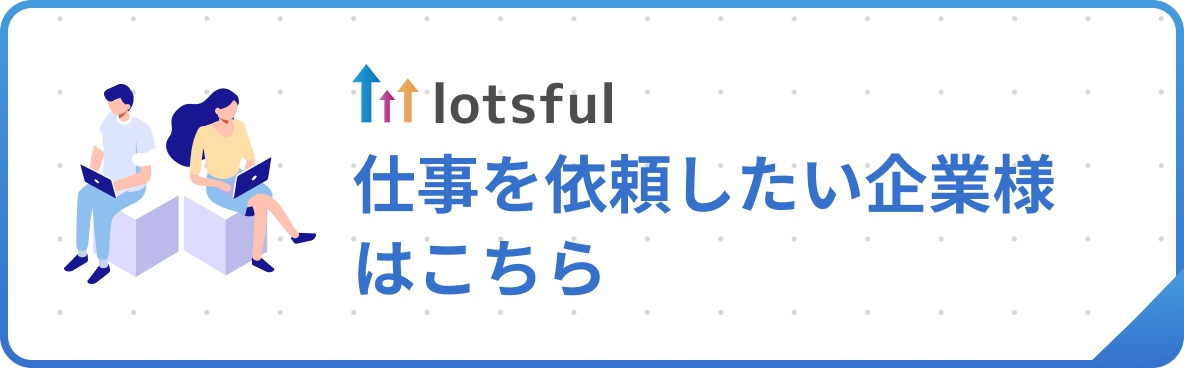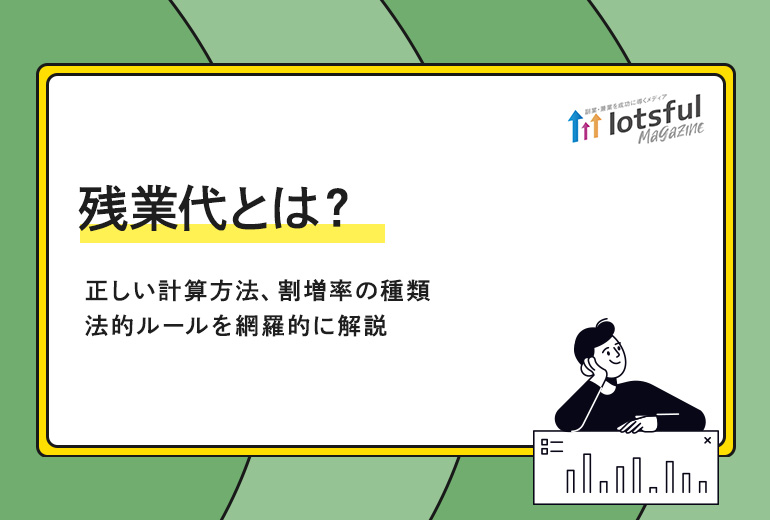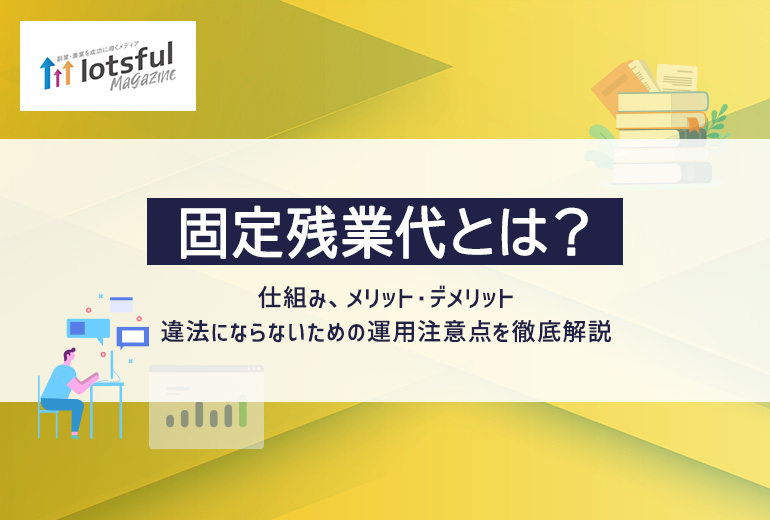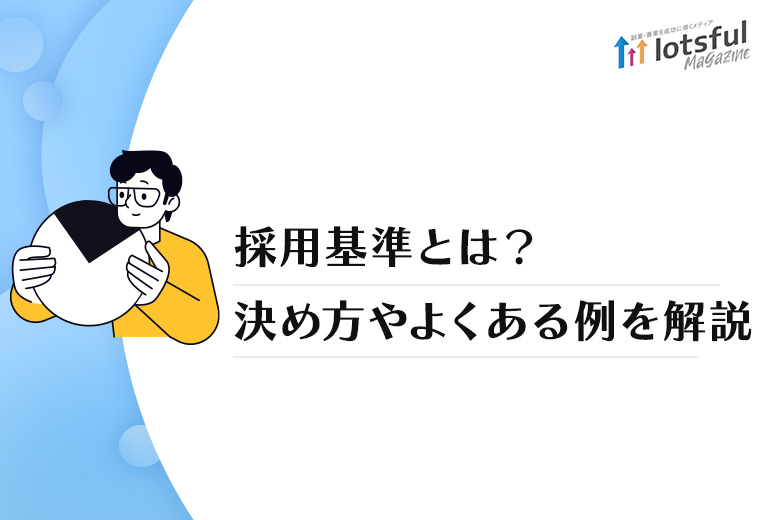
採用基準とは?決め方やよくある例を解説
採用活動のなかで重要となる採用基準。自社が採用したい人材を言語化することは、社内の担当者間で共有できるだけでなく、入社後の双方のミスマッチを防ぐうえでも重要です。
この記事では、そもそも採用基準とは何かを押さえたうえで、採用基準を決めるプロセス、重要な採用基準の例、さらには採用基準に設定するべきでない事項について詳しく解説します。
また、採用業務には副業人材を活用する選択肢もあります。詳しくは記事の最後をご覧ください。
採用基準とは
採用基準とは、企業が採用プロセスにおいて求職者を評価する際に用いる判断指標です。求める人物像や必要なスキル、経験はもちろん、資質や人柄などを明文化し、採用プロセス全体で一貫した評価軸として機能します。
採用基準を設定することにより、採用担当者間で共通の評価基準を持つことができ、選考の公平性と一貫性が保たれるというメリットがあります。採用担当者の主観が入りすぎたり、短期的な人員補充のみを目的に急いで採用したりすると、中長期的な事業成長に影響を及ぼす可能性があるため注意しましょう。
採用基準を決めるプロセス
採用基準を策定する際は、一般的に以下の4つのステップに沿って進められます。
1. 就職・転職市場の分析
・業界・職種別のマーケット分析
・有効求人倍率の把握
・採用ターゲットのトレンドを把握
2. 自社の分析
・企業のビジョンや目標の再確認
・中長期的な事業計画を確認
・各部門へのヒアリングを実施し、ニーズを把握
・既存優秀社員のコンピテンシー(成果につながる行動・思考特性)の洗い出し
3. 合否判定に必要な評価項目の作成
・再度、経営層・各部門にヒアリングし、必要なコンピテンシーを選定
・各コンピテンシーを具体的な行動項目へと落とし込む
・採用したい人物像を具体的に設定
・「必須条件」と「望ましい条件」を区別
・「スキル」「経験」などの定量的評価項目と「人間性」などの定性的指標をともに整理
4. 社内での最終合意形成
・関係者への採用基準の共有
・経営層・各部門とのコミュニケーションとすり合わせ
・フィードバックを反映させ、採用基準を最終調整
採用基準は一度設定して終わりではありません。企業の成長段階や市場環境の変化に応じて、柔軟に進化させていくべきものです。定期的な見直しが、その時々での最適な人材獲得につながります。
重要な採用基準の例
採用基準は業種や職種、企業ごとの採用ターゲットなどによって異なりますが、多くの企業で重視される代表的なものを6種類紹介します。
主体性
さまざまな課題や業務に対して、自ら考え行動できる「主体性」を持つ人材は、多くの企業で求められます。上司や先輩の「指示待ち」ではなく、自発的に課題を発見し、解決に向けて行動できる人材が主体性の高い人材と考えられます。
主体性の高い人材は、新たなプロジェクトや困難な状況に直面した際にも積極的に取り組み、自己成長への意欲も高い傾向があります。面接時には、「困難な状況を乗り越えたエピソード」や「印象に残っている仕事やプロジェクトにおける自身の立ち回り」などの質問をすることで判断すると良いでしょう。
協調性
会社が組織として機能するためには、協調性を持つ人材であることも求められます。ほとんどの企業では複数の社員が協力し合いながらプロジェクトや日々の業務を進めるため、他者と円滑に協働できることは重要な資質といえるでしょう。
協調性の高い人材は、異なる意見を尊重し、対話を通じて最適な解決策を模索します。さらに、目標達成に向け、チーム内における自身の役割を理解し、責任を持って遂行するだけでなく、周囲の人材が行き詰まっている際にはサポートする姿勢を持つこともできます。
面接では、「チームでの仕事経験」や「意見の対立があった際の対処法」などの質問をするほか、グループディスカッションを取り入れることで、実際の協調性を観察することが可能です。
意欲
社員の仕事への意欲や熱意は、企業の中長期的な成長を左右する重要な要素です。技術やスキルは後からでも習得可能ですが、内発的な動機づけは育成が難しく、採用段階での見極めが重要となります。
高い意欲を持つ人材は、困難な状況でも粘り強く前向きに取り組み、常に最善の結果を追求します。自社の事業や職種に対する興味・関心が高く、さまざまな分野への学習意欲を持ち、自己のモチベーションをコントロールすることができます。面接では、「なぜ当社に興味を持ったのか」「将来のキャリアをどのように描いているか」などの質問を通して、その時点での動機や熱意を評価しましょう。
コミュニケーション力
ほとんどの企業では、社内外のさまざまなステークホルダーとコミュニケーションを取りながら業務を進行します。そのため、スムーズな会話のキャッチボールや対人スキルは、必要不可欠なスキルといえるでしょう。
一言で「コミュニケーション力」といっても、さまざまなタイプのコミュニケーション力が含まれます。たとえば、内容を整理し相手にわかりやすく説明する力、相手の意図や感情を汲み取った発言をする力、さらには聞く姿勢を持ち相手の本音を引き出す力も重要です。採用基準として「コミュニケーション力」というワードが挙がった際には、関係者がどのような能力を想定しているのか、認識をすり合わせましょう。
専門性
中途採用において、業務に関連する専門知識やスキルをどの程度持っているかは、即戦力人材を見極めるうえで非常に重要です。過去の実績や保有資格などから専門性を評価するのが一般的です。採用予定の人材が配属される予定の部門と綿密にコミュニケーションを取り、どのようなスキルや専門性を持つ人材が必要かを正しく把握することが入社後のミスマッチを防ぐために重要といえるでしょう。
面接では「具体的なプロジェクト経験」「この分野の最新トレンドや現状をどのように捉えているか」など、専門性を確認する質問を投げかけ、その回答をもとに見極めることができます。
カルチャーマッチ
企業風土にマッチする人材かどうかも重要な指標となります。カルチャーマッチとは、「カルチャーフィット」とも呼ばれ、企業理念やルール、社員の行動や人間関係、価値観などの組織文化と、候補者の行動指針や信念などが合致することを指します。
カルチャーマッチする人材を採用することは、組織へのなじみやすさだけでなく、早期離職の防止にも効果的です。
採用基準にするべきでない事項とは
厚生労働省では、「公正な採用選考を行うことは(中略)応募者の適性・能力とは関係のない事項で採否を決定しない」と定めています(※)。そのため、採用基準を策定する際には、「基準として設定するべきでない事項」について配慮することが求められます。
ここからは、採用基準にするべきでない事項について、注意点を見ていきましょう。
(※)出典:厚生労働省『公正な採用選考の基本』
応募者本人に責任の無い事項
応募者の適性や能力に関係がない事項として、応募者本人に責任のない以下のような項目が挙げられます(※)。
・本籍・出生地に関すること
・家族に関すること(職業、続柄、健康、病歴、地位、学歴、収入、資産など)
・住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など)
・生活環境・家庭環境などに関すること
これらの要素は職務遂行能力と直接的に関連せず、これらを基準にした採用判断は就職差別とみなされる可能性があります。
(※)出典:厚生労働省『公正な採用選考の基本』
応募者本人の価値観の自由であるべき事項
また、応募者本人の価値観など、本来自由であるべき事項も採用基準にするべきではありません。厚生労働省では、以下のような項目を挙げています(※)。
・宗教に関すること
・支持政党に関すること
・人生観、生活信条などに関すること
・尊敬する人物に関すること
・思想に関すること
・労働組合(加入状況や活動歴など)、学生運動などの社会運動に関すること
・購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
多様な考え方を持つ人材が共存すると組織の視野が広がり、より柔軟な思考が促進されることもあります。採用基準を設定する際は、「この職務を全うできるか」という観点に焦点を当て、個人の内面的価値観を尊重する姿勢を持つことが重要です。
(※)出典:厚生労働省『公正な採用選考の基本』
御社の採用業務を副業社員に任せてみませんか?
この記事では、そもそも採用基準とは何かを押さえたうえで、採用基準を決めるプロセス、重要な採用基準の例や逆に採用基準にするべきでない事項などを詳しく解説しました。適切な採用基準を設定することは、優秀な人材の獲得と中長期的な定着に欠かせません。
「採用を強化したいが、専門領域の経験者が社内にいない…。」そのような企業では、副業人材の活用を検討するのも一つの方法です。『lotsful』は、領域ごとに確立・洗練されたノウハウを持つ人材が多数登録している、初期費用0円で始められる副業人材とのマッチングプラットフォームです。
工数を削減できるエージェント型サービスを採用しており、経験豊富なコンサルタントがオンボーディングや受け入れ後の体制構築まで伴走します。
専門領域のプロは社内にいないけれど、採用にかかる費用や工数を削減したいなど、人的リソースに課題を抱える企業の皆さまは、ぜひ『lotsful』の活用をご検討ください。
関連記事
・採用戦略とは?策定方法や効果的なフレームワークを解説
・わかりやすい面接官マニュアル | 質問例、心得、NG言動や行動まとめ