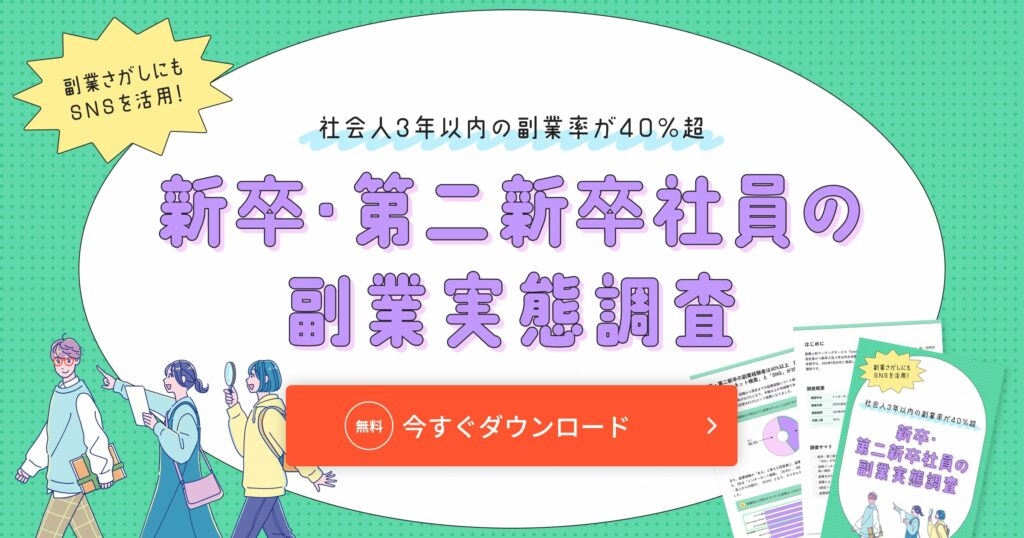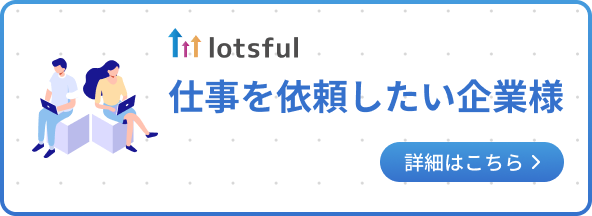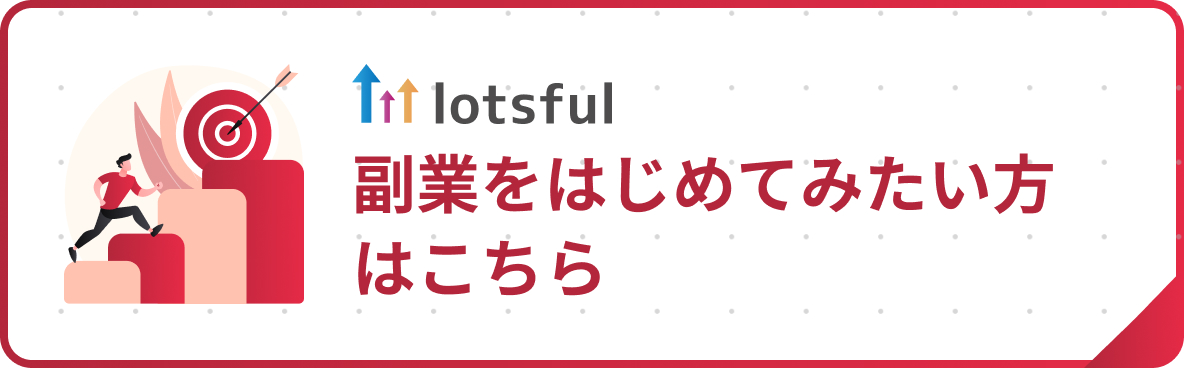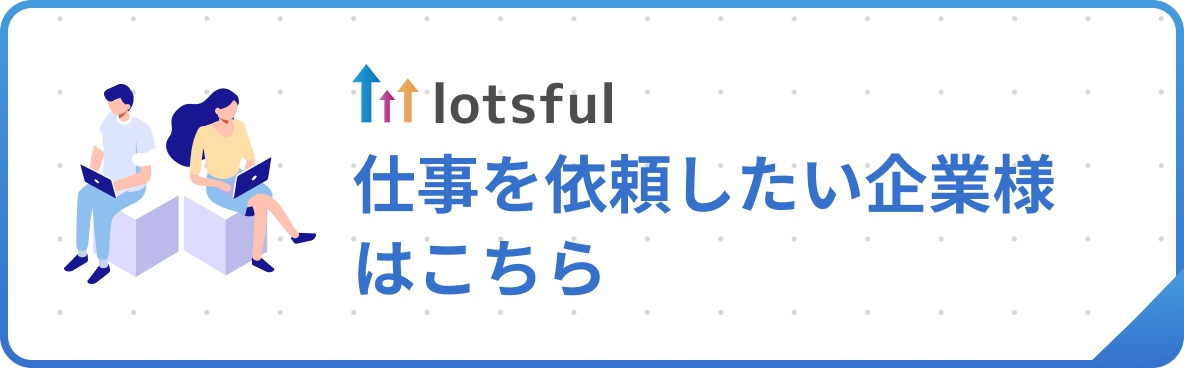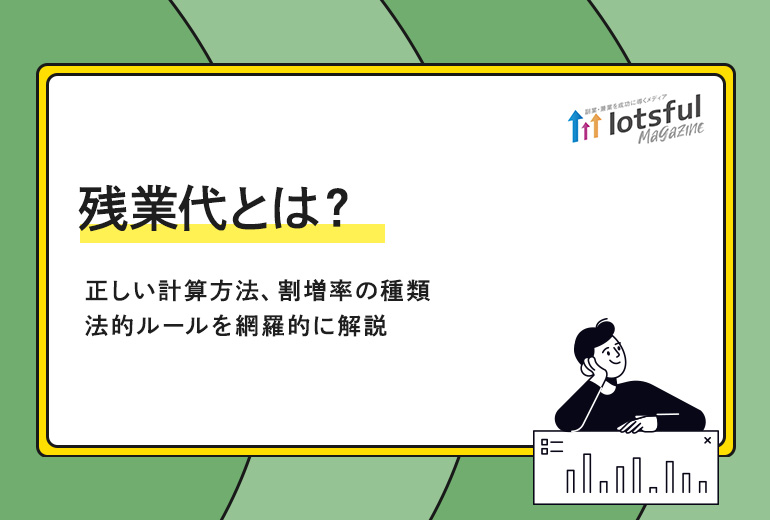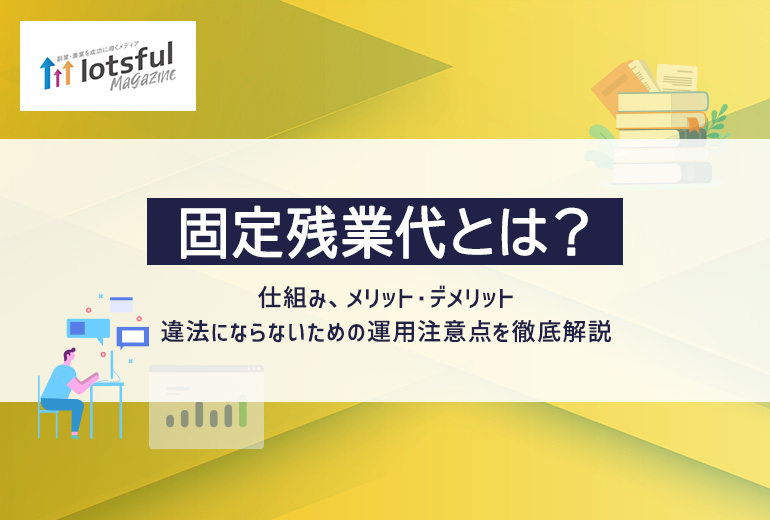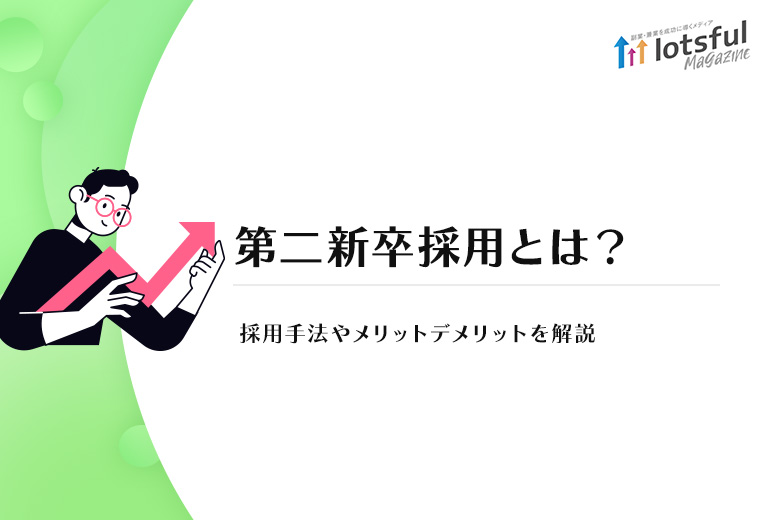
第二新卒採用とは?採用手法やメリットデメリットを解説
第二新卒採用は、社会人としての経験は浅いものの、将来性のある若手人材を採用できるため、新卒採用と中途採用双方のメリットを得られる手法です。また、副業人材の獲得にも有効な方法といえるでしょう。
本記事では、第二新卒採用におけるメリット・デメリットから、主な採用手法や注意点まで、詳しく解説していきます。
第二新卒とは
第二新卒とは、大学などの学校を卒業後、一度就職したものの短期間で離職、あるいは企業に在籍しながら転職を希望する20代の若手人材を指します。
厚生労働省による「若年者雇用を取り巻く現状」(※)では、各企業において第二新卒に関する定義がある場合、その定義に従うものとしており、一般的には、以下の条件が第二新卒者に該当します。
- 正社員として新卒入社後、概ね1~3年以内の若手人材
- 20代前半~中盤が中心
- 新卒で入社した企業を退職している、または在籍しながら転職を希望している
- 社会人経験は浅くとも、業務経験を通じて基本的なビジネスマナーを習得している
また、既卒者との最大の違いは「学校卒業後の就職経験の有無」です。短期間でも就職経験がある第二新卒に対し、既卒者は卒業後も就職せず、就業のブランクがある状態を指します。
※出典:厚生労働省資料「 若年者雇用を取り巻く環境」
第二新卒採用のメリット
第二新卒採用により、企業は以下に挙げる5つのメリットを得ることができます。
若手でありながら社会人経験がある
第二新卒者は、企業での就業経験があるため、若手でありながら社会人としての基本的なマナーが身についています。
正しい敬語の使い方や、メール・電話での応対、タイムマネジメントなどについて、新卒者には一から教育する必要がありますが、第二新卒者であればその手間が省けるため、早期の活躍が期待できます。
また、社会人経験を通じてキャリア観が具体的に形成されているため意欲も高く、「ポテンシャル」と「実務経験」の両方を備えた貴重な若手人材といえるでしょう。
新卒採用よりも早期戦力化しやすい
第二新卒者は新卒者と異なり、1~3年程度の就業経験を有しているため、ビジネスマナーはもちろん、タスク管理やスケジュール調整など、業務の流れに関する一定の理解もあります。
このため、新たな職場でも環境に適応しやすく、早い段階での戦力化が期待できるでしょう。ただし、経験がある分、前職でのやり方に固執する場合もあるため、入社後の適切なフォローは必要不可欠です。
企業文化や業務プロセスに柔軟に適応しやすい
第二新卒者は、自社文化や業務プロセスにも柔軟に対応できる点が、社会人経験を有する第二新卒者ならではの強みといえます。
新たな環境や変化にも適応しやすいため、業務フローや方針を吸収できます。その結果、チーム内での摩擦も起きにくく、円滑に業務を進められるでしょう。
比較的採用競争が少ない
現在も多くの企業は、新卒の一括採用や即戦力を重視した中途採用に注力している状況です。
そのため、第二新卒者は年齢や経験が限られることから、企業間での採用競争が比較的少なく、採用成功率が高いといえるでしょう。
教育コストを抑えつつ、育成の余地がある
第二新卒者は、短期間とはいえ社会人としての経験があります。メールや電話応対など、基本的なビジネスマナーに関する研修を行う必要がないため、教育コストを抑えることが可能です。
さらに、第二新卒者はキャリアにおいても初期のフェーズにあり、教育コストを抑えつつも、長期的な人材育成がしやすいというメリットがあります。
第二新卒採用のデメリット
第二新卒採用には多くのメリットがある一方で、以下のような5つのデメリットがある可能性も理解しておきましょう。
早期離職経験があるため、定着率に不安がある
第二新卒者は就業経験があるとはいえ、社風や人間関係の不和、業務内容との不適合などによる挫折を経て、早期離職に至った経験を持っています。
このため、企業側としては、第二新卒者の組織や業務に対する耐性に懸念を抱き、定着率に不安を感じるかもしれません。
第二新卒者の早期離職原因が「ネガティブ」か「ポジティブ」かを見極めることも必要なため、できる限り詳しく聞いておきましょう。
前職の企業文化や業務スタイルに影響を受けている可能性がある
第二新卒者が前職の企業文化や業務スタイルに影響を受けている場合、新たな環境に馴染みにくい可能性があります。
この場合、前職での業務の進め方にこだわるなど、柔軟性を欠ける対応をしがちであり、自社での学びや成長スピードが鈍化してしまいます。
このような状況に陥らないよう、面接などで前職での「成功・失敗の体験事例」の両方を聞いておきましょう。そのうえで、第二新卒者の柔軟性を見極め、自社文化や業務スタイルを具体的に提示することが重要です。
スキルや経験が不足している場合がある
第二新卒者は企業での就業経験があるとはいえ、1~3年程度です。あまりに高いスキルや経験値を求めても、期待に沿う活躍が得られるとは限りません。
また、就業年数によっては実務的な業務を深く経験していない場合もあります。このため、第二新卒を採用する際は、スキルや経験よりもポテンシャルや意欲を重視しましょう。
新卒や経験者と比較してアプローチが難しい
第二新卒採用は、新卒と経験者採用双方のメリットが得られる一方で、アプローチが難しい側面もあります。
新卒採用は、企業説明会や就活フェアなど接点の場が多く、アプローチは比較的容易です。経験者採用は、高いスキルと経験値を見込んだダイレクトリクルーティングなどで、転職潜在層も含めたターゲットにアプローチできます。
一方で、職歴の浅い第二新卒者に対しては、新たな環境で再挑戦する人材を手厚く支援する体制があることを、求人媒体やSNSの活用により積極的にアピールし、接点をつくっていきましょう。
給与やキャリアパスの期待値が企業と合わないことがある
第二新卒採用において、給与やキャリアパスの面で企業との期待値が合わない背景には、前職での処遇や環境の影響が挙げられます。
前職でそれなりの給与や役割が与えられていた場合、第二新卒者は転職後も同様か、それ以上の処遇を求めてしまうことがあります。
また、第二新卒者がキャリアアップを目指して転職した場合、自らのスキルや経験を高く見積もり、高い給与やポジションを希望するケースもあるでしょう。
一方で、企業側としては第二新卒者の将来性を見込んで採用することが多いため、こうした期待値のギャップが双方で生じる原因にもなります。
第二新卒を採用する主な手法
第二新卒採用では、以下に挙げる5つの採用手法が適しています。
転職サイト
第二新卒者を採用する際に、最も一般的な方法が転職サイトの活用です。転職サイトを利用する層は、現状より良い環境やキャリアアップなど、自身の成長を目指す意欲の高い人材が多い傾向にあります。
また、昨今は第二新卒やポテンシャル採用に特化した転職サイトも多く存在します。このため、自社の求める人材にリーチしやすいでしょう。
技術職などの募集職種に特化した転職サイトもあるため、「年齢層」「業種・職種」に強みのある転職サイトを併用することで、さらに採用効果が高まります。
人材紹介会社(エージェント)
第二新卒を採用する際に人材紹介会社(エージェント)を活用することは、短期間で採用候補者とマッチングが実現しやすい点でも、大きなメリットがあります。
人材紹介会社では、自社が求める人物像に対して、ポテンシャルや志向性、パーソナリティに関する詳細なヒアリングを行い、自社との相性を見極めたうえで候補者を紹介してくれます。
人事担当者の負担を軽減できるうえ、マッチング精度が向上することで、早期離職のリスクも回避しやすくなるでしょう。
ダイレクトリクルーティング
第二新卒者へ直接アプローチするダイレクトリクルーティングも、ポテンシャル採用に適した採用手法です。
ダイレクトリクルーティングでは、オファーメールを通じて、自社の理念や成長環境、採用候補者と同様に若手が活躍し、成長を遂げている実例などを個別にアピールできます。
個別アプローチであるため一定の労力はかかるものの、第二新卒者の興味や関心を引きやすく、比較的採用コストを抑えられる点も魅力です。
ダイレクトリクルーティングについてより詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
関連記事:ダイレクトリクルーティングとは?メリットデメリットや費用相場を解説
SNS
第二新卒者のような20代前半~中盤の若年層にとって、SNSは主な情報収集源となっています。このため、第二新卒者を対象とした採用活動においても、SNSの活用が注目を集めています。
X(旧Twitter)やInstagramに自社アカウントを開設して、定期的に企業の魅力や社員の声を発信していきましょう。無料で運用できるうえ、他の求人媒体よりも自由度が高い点も魅力です。
動画なども活用して自社カルチャーを効果的に発信すれば、採用効果の向上だけでなく、自社ブランディングの強化にもつながるでしょう。
リファラル採用
自社従業員から第二新卒者を紹介してもらうリファラル採用は、マッチング精度の高さと低コストという点でメリットがあることから、おすすめできる採用手法です。
紹介者である従業員が採用候補者のパーソナリティをよく理解しているため、その人物が自社に適しているかどうかの判断がしやすい点も特徴です。
また、発生する費用は従業員へのインセンティブのみで済むため、非常にコストパフォーマンスに優れた採用手法といえるでしょう。
ただし、リファラル採用を行う際には、紹介制度の運用ルールや情報共有の徹底など、注意点もいくつかあります。リファラル採用の導入を検討されている場合は、ぜひ以下の記事もご覧ください。
関連記事:リファラル採用とは?メリットデメリットや注意点まとめ
第二新卒を採用する際の注意点
第二新卒採用では、以下に挙げる6つの注意点を踏まえておくことで、採用におけるリスクを回避しやすくなります。加えて、オンボーディングやキャリア面談など、入社後の対応にも注意点が潜んでいることを意識しましょう。
早期離職の理由を確認し、同じ理由で退職しないかを見極める
第二新卒者は、何らかの理由があって短期間で前職を離れています。転職先である自社が、前職と同様の環境であった場合、再度離職につながるおそれがあります。
このため、採用候補者がどのような経緯で早期離職に至ったのか、その理由をきちんと確認しておく必要があります。
面接では前職の離職理由に加えて、採用候補者が自身に合う環境やはたらき方を理解しているかどうかも確認しておきましょう。また、自社の価値観とマッチしているかを見極めることも肝心です。
企業文化や業務スタイルとの適合性を慎重に評価する
ポテンシャルが高く、新たな環境に対する柔軟性に富んでいる点は、第二新卒者の大きなメリットです。
ただし、そもそも自社の企業文化や業務スタイルと合わない場合には、モチベーションの低下や早期離職を招くといったデメリットが生じるおそれがあります。
採用候補者と自社の適合性を慎重に評価する具体的な方法として、面接時に候補者の職場に対する「期待」「志向性」「価値観」などを確認することをおすすめします。
また、企業側としても、社内の雰囲気や業務の裁量度、評価に関する実情を率直に伝えることで相互理解が深まり、ミスマッチの少ない採用が実現するでしょう。
過度な即戦力を求めすぎず、育成計画を用意する
第二新卒者は、就業経験のない新卒や既卒者に比べて一定の経験値があるため、早期段階からの活躍を期待されがちです。
ただし、第二新卒者の経験やスキルに対して過度な期待をかけると、ギャップによるデメリットが生じる可能性があります。即戦力を前提に対応した場合、プレッシャーがかかりやすく、早期離職につながるおそれがある点もデメリットといえるでしょう。
第二新卒者は、自らの就業経験を通して、新たな環境で成長したいという意欲を持っています。この芽をつぶすことなく、ポテンシャルを最大限に引き出せるよう、中長期的な育成計画を事前に用意しておきましょう。
キャリアの希望や将来像を明確にヒアリングし、ミスマッチを防ぐ
第二新卒を採用する際には、本人が希望するキャリアや将来像を詳細にヒアリングしたうえで、自社が提供できるキャリアプランとすり合わせていくことが重要です。
新天地においても、自身が望むキャリアや将来像とギャップがあると、再度離職につながる可能性があります。第二新卒者が描く未来像と、自社が提供できるポジションや成長ルートが一致していれば、ミスマッチを防ぐことができるでしょう。
選考時にポテンシャルや成長意欲を重視する
第二新卒採用が成功するか否かは、採用候補者のポテンシャルや成長意欲を重視するかどうかがポイントといえるでしょう。
第二新卒者は、社会人としての経験は浅いものの、「これまで得た教訓を活かして、新しい職場で成長したい!」という意欲を持っています。
挑戦する前向きな姿勢や、若手ならではの吸収力・柔軟性を自社で活かせるよう、経験やスキルよりも、第二新卒者の姿勢を重視した選考を行うようにしましょう。
入社後のオンボーディングを充実させ、定着を促進する
第二新卒者を採用し、自社で長く活躍してもらうには、入社後の充実したオンボーディングの実施がカギを握ります。
第二新卒者がモチベーションを維持しつつ、十分なポテンシャルを発揮できるよう、受け入れ体制や育成体制を整備し、定着支援を行いましょう。育成体制が不十分だと、第二新卒者の成長が妨げられるというデメリットがあるため、定着に向けたサポートは不可欠です。
明確な育成計画や的確なフィードバックなど、オンボーディングが充実していることで、第二新卒者の成長意欲の持続とパフォーマンス向上が実現します。
御社の採用業務を副業社員に任せてみませんか?
今回は、近年注目を集める第二新卒採用について、注意点も踏まえた有益な情報をお届けしました。
第二新卒採用を検討しているものの、リソースやノウハウ面に不安がある場合は、経験値の高い副業社員に自社の採用業務全般を任せてみるのも、有効な方法のひとつといえるでしょう。
「優秀な副業社員との出会いを、コストと時間をかけずに叶えたい!」とお考えの企業の皆さまにおすすめなのが、副業人材マッチングサービスの「lotsful」です。
副業市場が拡大する中、初期費用をかけずにスピーディーな副業社員とのマッチングを実現するなら、ぜひ一度「lotsful」へお気軽にご相談ください!