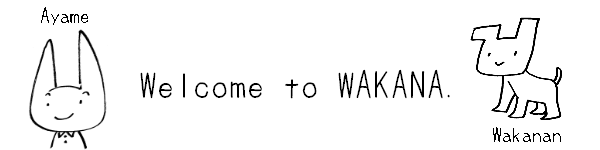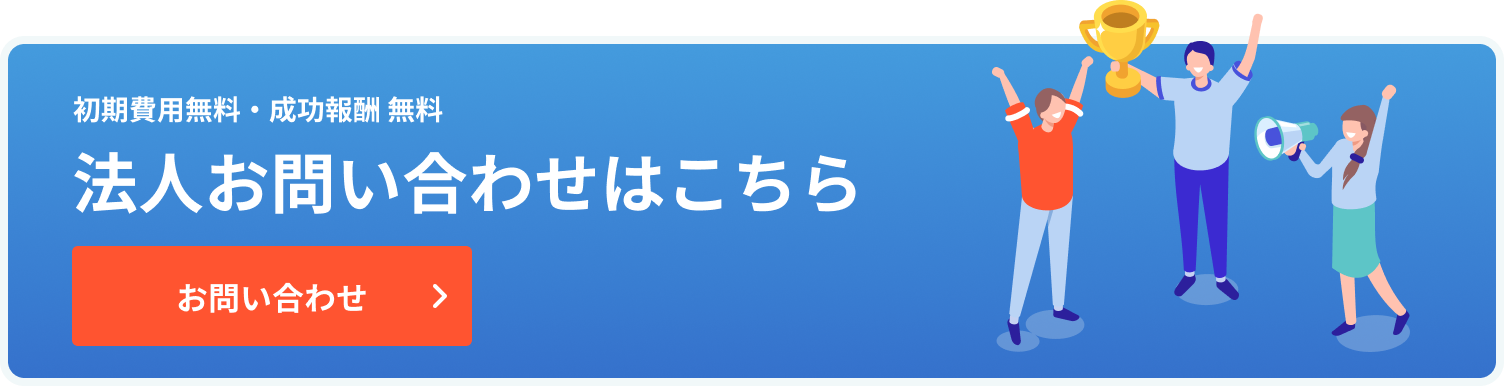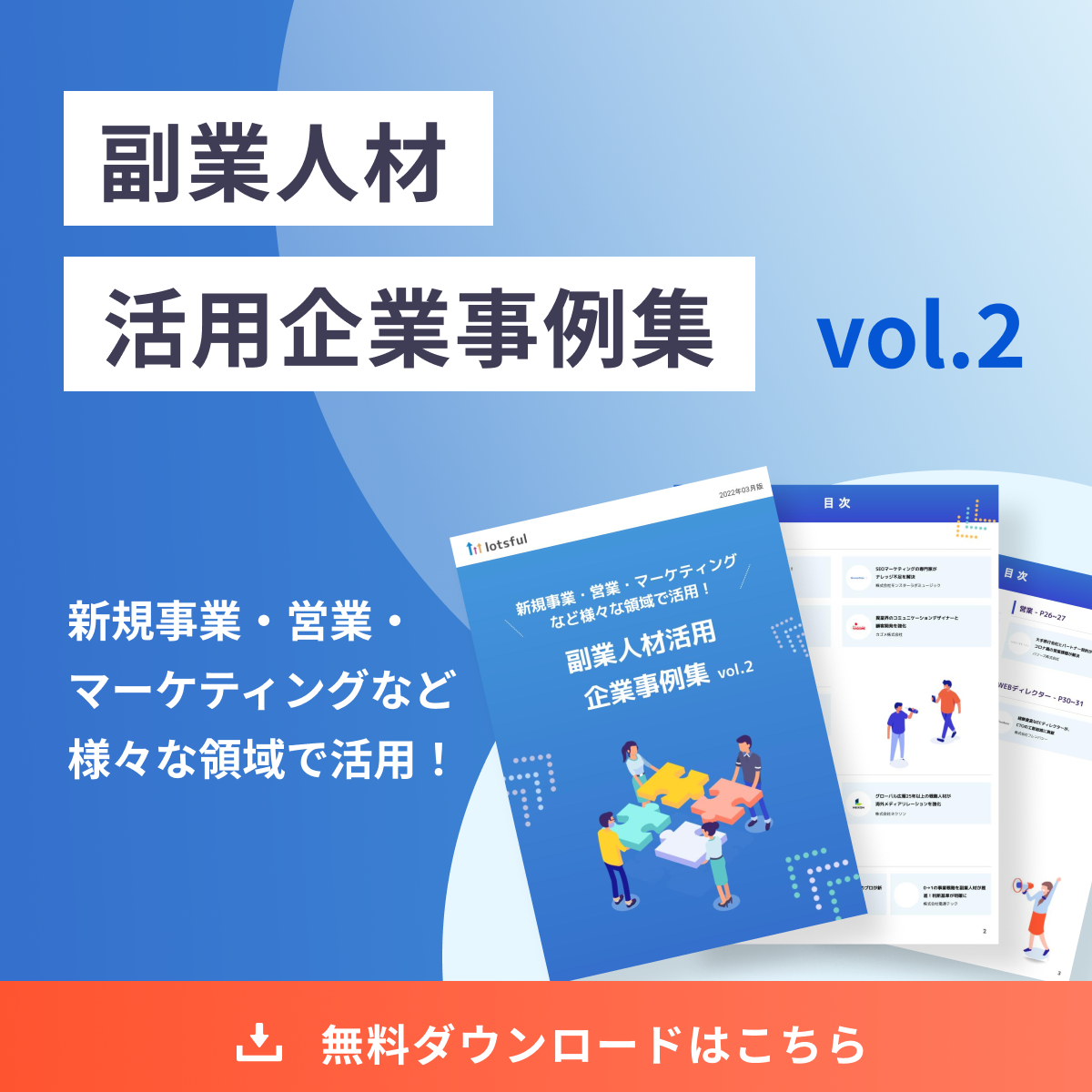「バーチャル美術館」と「新たな人事評価」―社会福祉法人が副業人材活用により、わずか1年で2つの成果!
lotsfulは2023年8月から広島県福山市と連携し、副業・兼業人材活用支援(備後圏域副業・兼業人材マッチング支援プロジェクト)を開始しました。2年目となる2024年度からは、竹原市も追加された7市2町へと対象エリアを拡大し、さらに多くの地域企業に向け、本プロジェクトを展開しています(※)。
本記事では、広島県尾道市・福山市・三原市・世羅町のエリアで複数の施設を運営する社会福祉法人若菜の副業人材活用事例を紹介します。
若菜は22年前に広島県尾道市の廃校した小学校を再利用し、生活介護事業所をスタートした社会福祉法人。「『人の役に立つ』ということを通して利用者・職員が共に成長すること」を理念とし、障害のある人とその家族の生活を支援しています。
今回、若菜が副業人材を活用して取り組んだのは、「利用者さんの芸術作品を展示するバーチャル美術館の立ち上げ」、「職員のモチベーション向上を図るための適性な人事評価制度の確立」の2つのプロジェクトです。全く方向性の異なるプロジェクト2つを、どのように進め、形にしていったのでしょうか。社会福祉法人若菜 理事長 藤本達也氏に話を伺いました。
※関連プレスリリース:副業マッチングサービス『lotsful』昨年度に引き続き、広島県福山市と連携し、副業・兼業人材の活用を支援
https://lotsful.jp/news/346
会社情報
| 社会福祉法人若菜 |
障害福祉サービス事業(障害のある人とその家族の生活を支援する複合施設を運営) |
|---|---|
| 設立年 |
2003年3月 |
| 社員数 |
185名 |
| 副業活用ポジション |
バーチャル美術館ディレクター/人事考課制度設計 |

社会福祉法人若菜
理事長
藤本達也氏
京都市の介護施設で勤務した後、2014年より父親が創業した社会福祉法人若菜に入職。
2023年4月より2代目理事長に就任。
2つのプロジェクトを推進すべく、専門人材を求める
藤本氏
障害福祉専門の福祉施設を運営しています。対象とするのは、放課後等デイサービスや児童発達支援を利用する児童から、65歳までの高齢の障害の方まで。通所施設、入所施設、相談支援事業所などを運営する一方で、飲食店をやっていたり、ギャラリーやカレーの移動販売も手がけています。拠点本部は尾道市ですが、福山、三原、世羅町にも拠点があり、約20施設を運営しています。
藤本氏
若菜は、利用者さんを支援する職員のみで構成されていて、それ以外の専門知識を持った人材がいません。いろいろ取り組みたいことはあったのですが、必要な知識をもった職員がいなかったのです。そんなときに、今回のプロジェクトの話を聞いて、タイミングも内容もピッタリだったので利用することにしました。
藤本氏
若菜ではもともとギャラリーを運営していて、利用者さんの作品を展示したり、イベントを行っていたのですが、やはり家族や友人など見に来る人が限定されてしまうんですよね。私は、それがもったいないなと思っていて。とても良い絵なんですよ。賞を受賞していたり、雑誌の表紙に載ったりなど、一般的な評価も高くて。
なんとか全国の人に届けるツールはないかと考えていました。しかも、HPやSNSに掲載するだけでなくもっと魅力が伝わる方法、「歩き回りながら鑑賞できる美術館」のようなものが出来ないかと考えたのがきっかけです。
藤本氏
自分自身の経験から、人事考課はずっと課題だと思っていました。これまでの人事評価は管理者が文章で評価表を作成し、それを読んで理事長が評価をしていました。しかし、管理者の想いが文章では伝わらず、思っていた評価になっていないことがありました。どうにか管理者の想いを組んだ、しっかりとした評価制度を構築できればと考えていました。
藤本氏
4〜5人の方を紹介していただきましたが、まずは、現役で活躍されていて、新しい考え方や知識、技術を持っている方がいいなと思いました。もうひとつは、私たちとの共通点があるかどうか。地域活性に伴うDX支援事業を手がけているKさんに関しては、福山市で道の駅のPRをされた経験があるというので、身近に感じました。地元の知識もあって話も通じやすいですし、経歴にも安心感がありました。
組織人事コンサルタントであるMさんについても、経歴やスキルはもちろんのこと、最後の決め手は福祉施設に関わる経験があったことです。他の候補者も一般企業での経験をお持ちでしたが、福祉事業に関わる人事評価制度を構築した経験があったのはMさんだけでした。福祉施設ならではの事情や目的が伝わりやすいだろうとの期待を抱いて、Mさんを選びました。

専門人材の人脈と経験を活かし、想いがどんどん形へ
藤本氏
バーチャル美術館については、本当にゼロからのスタートでしたので、まず私がやりたいことを伝えました。そこから、Kさんが具体的な選択肢を挙げていってくれたんです。たとえば、オンラインゲームの中で部屋を借りて、そこで展示する方法など、とにかく選択肢をたくさん出していただいて、その中から私が選んでいくという流れで進めていきました。
Kさんは本当に横のつながりが広い方で、いろいろな方を紹介してもらいました。最終的には、株式会社メタバーズが手がけているCYZY SPACE(サイジースペース)というVR空間を利用することになりました。
藤本氏
福祉法人の取り組みとしては、珍しくて驚かれることが多いです。反応が大きく、やって良かったなと思っています。まだまだ改善の余地はありますが、出来栄えにはとても満足しているんですよ。定期的にコンテンツの更新もしていて、その作業は若菜の職員が行っています。
藤本氏
Kさんとのオンラインでの打ち合わせに、専任の職員も同席させたんです。その場に参加させたことで、いま担当者として頑張ってくれています。バーチャル美術館の立ち上げ当初から関わり、一緒に進めてきたなかで、成長につながりました。

藤本氏
人事制度も、まずは私の考えを話して、それをまとめてもらうところから始めました。Mさんは、私の想いや考えを引き出してくれるのが非常に上手で、「どういう想いでこれをやろうと考えたのですか?」「どんな評価が良い評価だと思いますか?」と、質問をいただきながらいわゆる棚卸をしてくれました。改めて聞かれると、私の方でも「昔こういうことをやろうとしていたな」「本当は自分はこう思ってたんだ」と、自分の中で気づきが生まれたんです。
そうしてまとめたものを、具体化するための提案書をMさんが作成してくれました。それを会議に諮り、そこで出た意見や提案を次の会議までに新しい提案書にまとめていただく、といった形で調整していきました。
Mさんは、高齢者福祉に関わる経験はあったものの、障害者福祉は初めてだということで、本当にいろいろご自身で調べたり、勉強してきてくださって。単に話をまとめるだけでなく、プラスアルファの背景や知識を加えて、ブラッシュアップした提案をしてくださいました。一つお願いしたら、二倍にも三倍にもして応えてくださる方だという印象です。
藤本氏
新制度として令和7年度からスタートさせる予定です。昨年11月には、管理者と共有し、修正点や意見がないか確認しました。皆が納得のいくものができたと思っています。3月頃から全職員に周知し、新年度から導入することを説明する予定です。
藤本氏
簡単にいうと、職員を評価するのではなく、職員に求める姿を示す制度になりました。良い悪いを判断するのではなく、若菜はこういう人材を求めている、あなた方にこうなって欲しい、今その姿にどこまで近づけているかを確認してください、といったものです。
元々は、がんばっている職員をきちんと評価したいというのが目的でしたが、今の若菜はまだその段階ではない。まずは理念を浸透させ、その上で次のフェーズに行くべきだと考えました。組織として礎となる土台をしっかり固めたいという想いを、この制度に落とし込みました。もちろん、評価としての機能も取り入れています。
藤本氏
皆、気持ちよく受け入れてくれました。実はこれも、Mさんに入っていただいたおかげなんです。Mさんは制度を構築していくなかで、「こういう説明をすると理解してもらいやすいですよ」、「管理者の方はこういうことを求めているのでは」、といった”受け入れる側”からのアドバイスもくれました。そのため、今回はまったくトラブルや不満の声が無かったばかりか、チームとしてまとまった感があります。
スピーディーかつ負担が少ないのも、外部人材ならではの魅力
藤本氏
今までお話ししたとおり、スペシャリストの方からのサポートが受けられたことはもちろん、仕事を依頼する私からすると、人事・労務的な管理が不要な点もありがたかったです。月に3〜4回くらい打ち合わせをするだけで、こちらの負担がほとんどありません。仕事の指示や進捗確認を私がやらなくても、お二人が自主的に進めてくれました。
藤本氏
やはり自分たちだけで課題解決するには、どうしても限界があると思います。得意分野がある方や専門知識を持っている副業人材の力を借りるというのは、非常に有効な手段だと感じています。
藤本氏
lotsful さんがすごく良いと思ったのは、サポートが手厚かったことです。たとえば、副業人材の方に直接伝えにくいこと、面と向かって言いづらいことも、間に入って話してくれるので助かりました。もちろん、3者交えての面談も設定してくれますし、さまざまな選択肢を提示してもらえましたね。
また、最初の副業人材の紹介時も、私が求めている要件を整理したうえで、合う方を紹介してくれたので非常に選びやすかったです。いつも、まず私の想いを聞いてくれて、そのうえで選択肢をくれるので、押し付けられ感が無く、寄り添ってくれたという印象でした。
(編集・取材・文:眞田幸剛)
lotsfulのご利用に関して
ご不明な点がございましたら
お気軽にお問い合わせください
初期費用・成功報酬 無料
資料請求・お問い合わせ