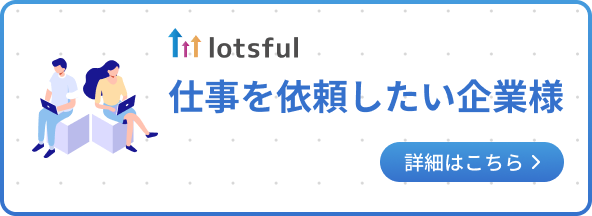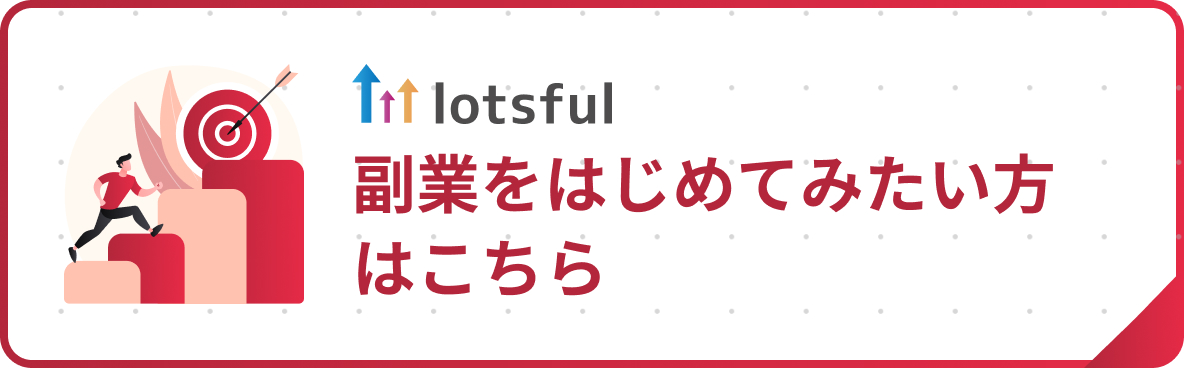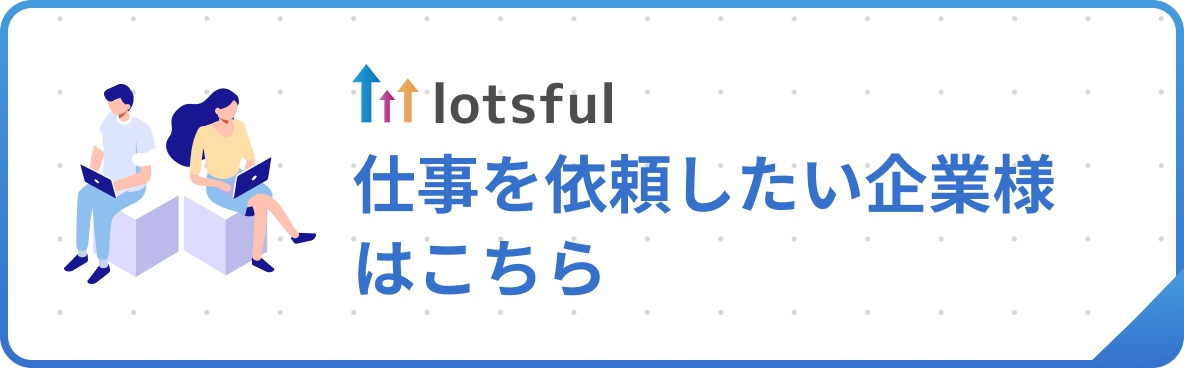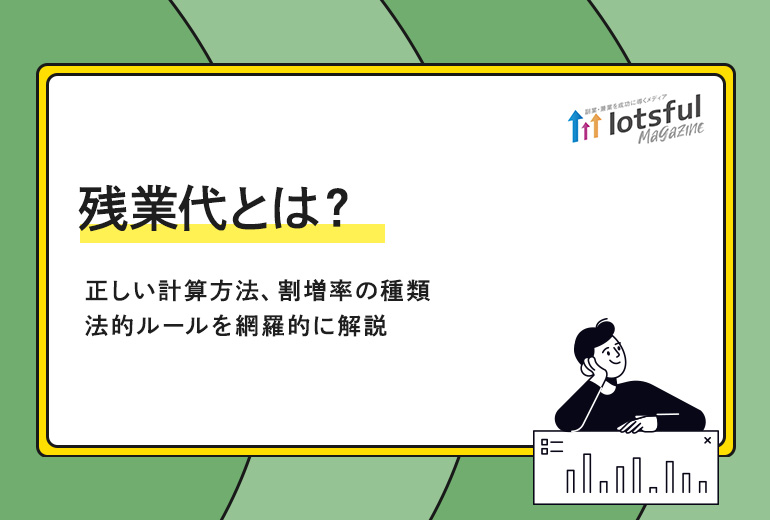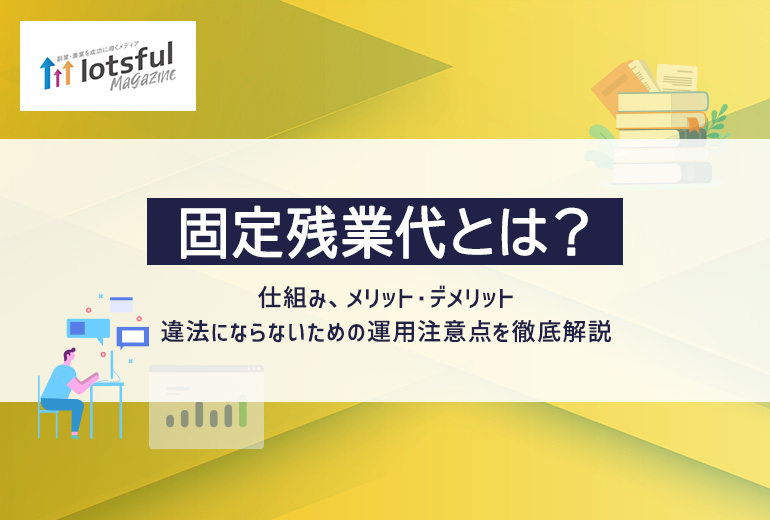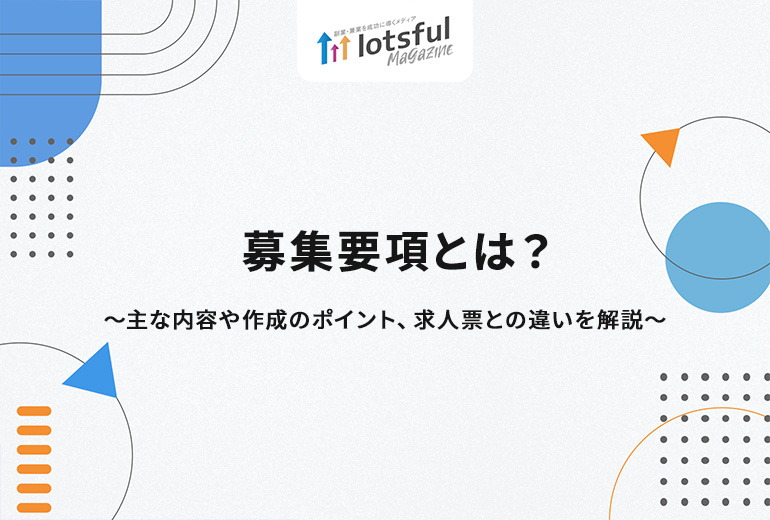
募集要項とは?主な内容や作成のポイント、求人票との違いを解説
募集要項は、正社員や副業人材など、どの採用形態においても、応募者が自ら応募可否を判断できるよう促すものであり、採用の質と企業の信頼性を高める役割を果たします。
本記事では、募集要項の内容や重要性に加え、求人票との違いや作成のポイントについても詳しく解説します。
募集要項とは
自社の求人において、求職者へ向けて自社の募集職種や仕事内容、勤務条件などの具体的な情報を項目ごとにまとめたものが募集要項です。求人票と似た意味を持ちますが、目的が若干異なります。
求職者にとっては、「自社へ応募するかどうかを判断する必須項目」が記載された箇所であり、企業にとっては、採用活動において社内向けに定めた基本的な採用要件といえるでしょう。
募集要項の主な内容
募集要項の内容としては、以下の11項目が主なものです。
・職種名(例:営業職、エンジニア、看護師など)
自社が募集するポジションを求職者が理解できるよう、分かりやすく記載してください。募集職種が社内独自の呼称である場合は、一般的な職種名に置き換えることをおすすめします。
・仕事内容(業務内容・具体的な業務例・1日の流れなど)
仕事内容に関しては、担当業務の列記だけでなく、「具体的な業務例」や「1日のタイムスケジュール例」などを盛り込み、求職者がイメージしやすい内容にしてください。
・応募資格(必須スキル・経験、歓迎条件、免許・資格など)
募集職種の「必須スキルや経験」「免許・資格」などを明確に記載しておくことで、求職者自身が応募条件に当てはまるかどうかを瞬時に判断できます。また、必須条件は絞り込み、歓迎条件と分けて記載することで、幅広い人材へのアプローチが可能です。
・雇用形態(正社員・契約社員・パート・業務委託など)
求人票では、募集職種に関する雇用形態の明確な記載が職業安定法や労働基準法によって義務付けられています。また、雇用形態を明示することで、求職者の誤解を防ぎ、ミスマッチのない採用が実現します。
・勤務地(本社、支社、リモート可否、転勤の有無など)
求職者にとって、「通勤距離」や「はたらき方」などは応募意思に直結します。勤務地が曖昧であったり、リモートの可否や転勤の有無が不明瞭な場合、応募を見送る可能性があります。
・勤務時間(始業・終業時刻、休憩、フレックスタイム制の有無など)
勤務時間やフレックスタイム制の有無などが明確に記載されていれば、求職者は生活スタイルやワークライフバランスを判断でき、採用後の定着率の向上にもつながります。また、シフト制勤務の場合は、シフト例と休憩時間を明記すると良いでしょう。
・給与・賞与・昇給(基本給、手当、賞与回数、昇給タイミング)
「給与」「賞与回数」「昇給のタイミング」などは、求職者の生活の安定に直結します。基本給額や各種手当なども含めて明確に記載しておきましょう。また、モデルケースごとの年収例を記載しておくと、求職者にとって良い目安になります。
・休日・休暇(週休制度、年間休日数、特別休暇など)
給与や待遇と並び、ワークライフバランスや休暇制度は転職理由の上位に入ります。「週休制度」「年間休日数」「特別休暇」などがきちんと明記されていれば、求職者は自分のはたらき方との適合性を判断できます。
・福利厚生(社保完備、交通費、住宅手当、研修制度など)
充実した福利厚生は、求職者にとって大きな魅力になるだけでなく、入社後の満足度や定着率にも直結します。自社ならではの福利厚生は、できるだけ詳細に記載しておきましょう。
・選考フロー(書類選考・面接回数・適性検査の有無など)
選考フローが事前に分かれば、求職者は自身のスケジュールや準備すべきことを検討できます。また、書類選考や面接回数、適性検査の有無が明示されていれば、途中辞退を減らすことも可能です。
・応募方法・連絡先(応募フォーム、採用担当者の連絡先など)
応募方法が不明瞭だと、応募意欲があっても行動に移せません。特にWeb求人の場合は、応募ボタンやリンクの配置・表示が分かりやすいと、即応募を促せます。
募集要項の重要性
人材採用における募集要項の重要性を軽視すると、優秀な人材の獲得機会を逸してしまう可能性があります。募集要項の重要性は、以下の5つの要素における目的達成にあります。
求職者が応募判断をする上での最も重要な情報源となる
求職者は募集要項をもとに、自身のスキルや条件がマッチしているかをチェックし、応募するかどうかを判断します。
チェック段階で、自身の希望やライフスタイルに合わない場合は応募を回避するため、明確かつ詳細な情報提示が必要です。
企業と求職者の認識のズレを防ぎ、ミスマッチを減らせる
「募集職種の詳細」「給与・待遇」「勤務時間」などが具体的に記載されていれば、企業と求職者間の認識のズレを防ぐことができます。
また、応募資格も必須スキルや条件を明確に示すことで、該当しない求職者は応募を控えるため、ミスマッチな採用を減らせるでしょう。
企業の信頼性や透明性を高める材料となる
採用条件や仕事内容を明確に記載した募集要項は、求職者に「誠実で信頼できる企業」という印象を与えます。
また、求職者は限られた情報から企業の姿勢を判断します。このため、給与や勤務条件も含め、曖昧な表記がないオープンな内容は、企業の透明性を高める良い材料となります。
面接前の不安や疑問を解消し、応募数や質の向上につながる
「給与」「勤務地・時間」「休日休暇」「福利厚生」、そして採用要件がきちんと記載されていれば、求職者は自身の希望条件との合致により、不安を解消できます。
また、応募から面接に至るまでの選考フローなどが明記されていれば、迷わず応募しやすくなり、結果として応募数や質の向上につながるでしょう。
採用活動のスムーズな進行や、辞退率・離職率の低下にも寄与する
充実していて正確な募集要項であれば、求職者は採用時の条件や入社後の業務イメージを正しく理解できるため、採用活動が滞りません。
また、募集要項に対する求職者の理解度が高いほど、提示した条件とのギャップが少なくなるため、辞退率や離職率の低下にもつながります。
募集要項と求人票との違い
募集要項と求人票との違いを理解することで、より効果的な採用活動を展開できます。募集要項と求人票は意味合いが似ていますが、以下の6つのポイントで異なります。両者の違いを踏まえた使い分けが、採用成功のカギとなるでしょう。
<募集要項>
・企業が定める「採用条件の内部的な基準」や情報整理ツール
採用活動の透明性・効率性・一貫性に直結します。
・採用部門や人事が社内向けに作成することが多い
社内承認や法令遵守、情報共有を容易にするためです。
・職種、仕事内容、応募資格、待遇などを網羅的に整理
採用活動の効率化や公平性を保ち、求職者とのミスマッチ防止に寄与します。
・求人媒体に出す前の「元データ」のような役割
採用活動に必要な情報を一元管理できるため、求人票作成時の作業が容易になります。
・社内での選考基準や採用計画の共有資料としても使われる
募集要項による選考基準が統一化され、内部チェックや改善の基礎資料になります。
・対外的に公開しない内容(採用人数、選考基準詳細など)を含む場合もある
社内運用や採用活動の効率化および公平性を確保するためです。
<求人票>
・求職者に向けて公開される「正式な募集情報」
求人票は、求職者が応募判断を行う意思決定資料としての役割を持ちます。
・ハローワークや転職サイト、企業HPなどで掲載される
求人媒体に掲載されることで、幅広い求職者との接点を最大化できます。
・募集要項をもとに作成されるが、求職者目線の表現に編集される
編集によって、求職者が理解しやすい平易な表現となり、応募判断がしやすくなります。
・法的に必要な項目(賃金・就業場所・労働時間など)を明記する義務がある
法的に義務付けられた項目を明記し、労働者を保護します。
・過度な抽象表現・誇張・誤記載があると法律違反(職業安定法等)になる可能性もある
求職者に誤解を与える表現や誤記載は、違法の対象となり得ます。
・応募の動機づけや企業理解を促すため、魅力や訴求要素を重視する
他社の求人票と比較した際に、応募者の関心を引きやすくなり、応募意欲に直結します。
募集要項作成のポイント
効果的な募集要項を作成するポイントを押さえることで、応募者の質と量を向上させることができます。募集要項を作成する際には、以下の5点のポイントを意識してまとめましょう。
ターゲット人材に合わせた言葉・情報の出し方を意識する
募集要項には、単なる条件や仕事内容の羅列だけでなく、自社がターゲットとする読み手に響く言葉選びと情報の出し方が求められます。
「年齢層」「経験年数」「スキルセット」など、ターゲット人物像が明確になれば、用いる表現も変わります。経験者向けであれば、専門的な表現や実務経験年数を具体的に記載しましょう。
業務内容は「何を」「なぜ」「どのように」行うかを具体的に書く
業務内容は、下記の3点を具体的に記載すると、応募意欲に直結します。
- 「何を」…担当業務の範囲を明確に記載する
- 「なぜ」…担当業務の目的や意義を示す
- 「どのように」…業務の進め方や用いるツール・手法などを記載する
条件面は曖昧にせず、正確かつ公平に記載する
「給与・待遇」「勤務地・勤務時間」「応募資格」などの条件が曖昧だと、求職者は募集職種と自身がマッチしているか判断できず、応募をためらう原因になります。
また、雇用形態によって勤務条件などが異なる場合は、試用期間なども含めて、正確かつ公平に記載することが求められます。
自社の魅力(社風、はたらき方、成長環境など)を簡潔に盛り込む
給与や待遇だけでなく、自社に入社することで得られるメリットも、求職者にとって重要な判断材料です。
自社カルチャーや成長環境などを簡潔に盛り込むことで、求職者は自身がはたらく姿をイメージしやすくなり、他社との差別化にもつながります。
読みやすさを意識し、見出し・箇条書き・改行を活用する
応募効果を高めるために、自社の魅力やメッセージなどをに盛り込むのは効果的ですが、読みやすさを意識しないと、求職者が途中で離脱する原因にもなるでしょう。
アピールしたい箇所には、見出しや箇条書き、改行などを適宜活用するなどの工夫をこらすことが肝心です。整理された募集要項により、求職者は内容を瞬時に理解できるため、応募意欲につながります。
御社の業務に副業社員を検討してみませんか?
今回は、募集要項の意味や重要性について、求人票との違いや作成のポイントなど、企業が知っておきたい情報をまとめてお届けしました。
募集要項の作成に限らず、御社が業務上で多くの課題を抱えているなら、解決に向けて活躍する副業社員を取り入れるのもおすすめです。
御社が課題解決にふさわしいスキルを持つ人材をお探しなら、副業人材マッチングサービス「lotsful」をぜひご活用ください!
新たな採用チャネルとして効果が期待できる「lotsful」なら、コストや工数の負担を抑えつつ、御社が希望する人材とのマッチングを速やかに実現できます。
1日も早い課題解決に向けて、「lotsful」へお気軽にご相談ください。