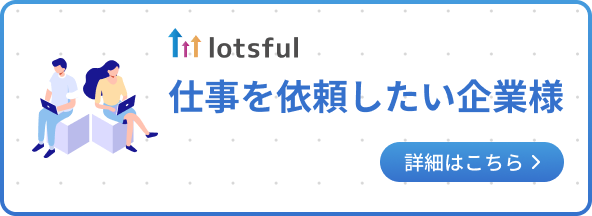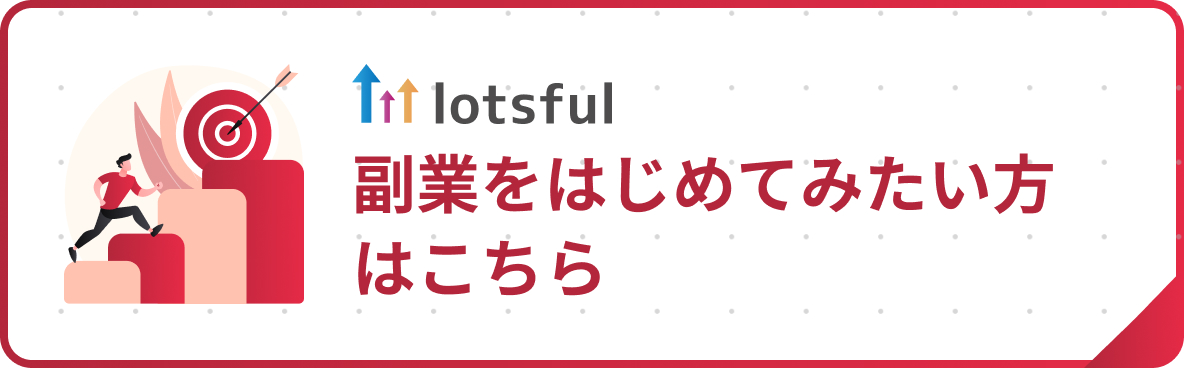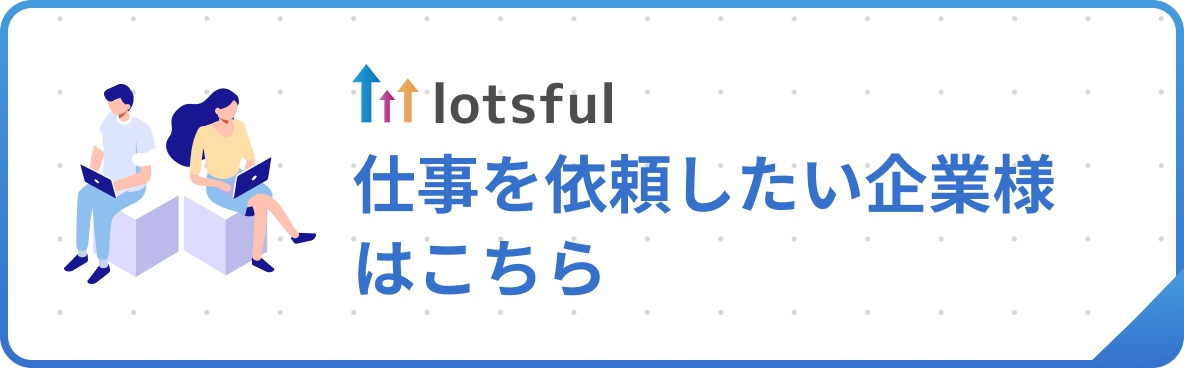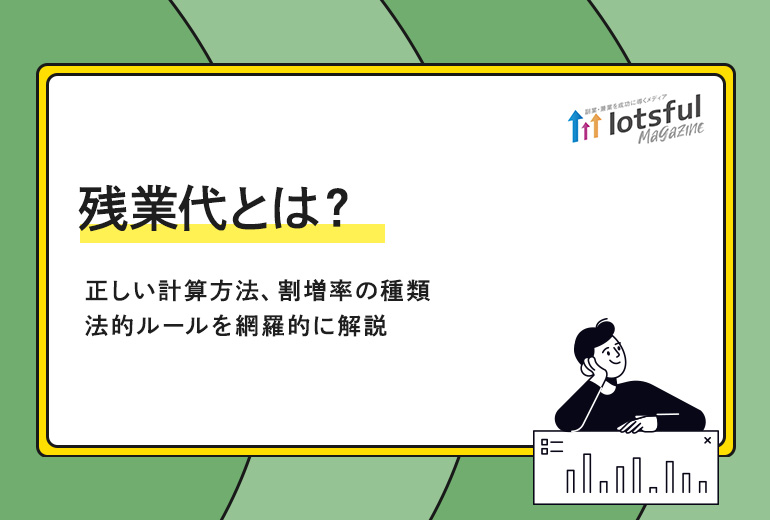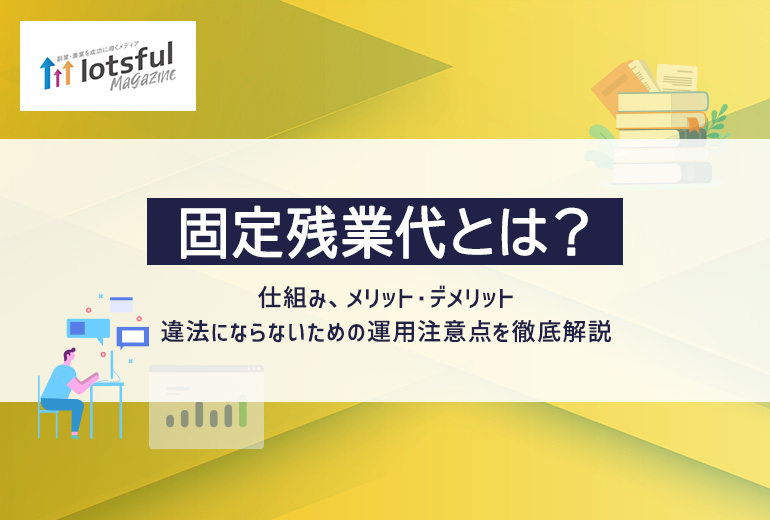求人に応募が来ない原因と対策まとめ
競合が多い業種や職種などでは、求人を出しても応募が来ないケースは珍しくありません。また、正社員のみならず、副業社員の求人において成果が得られない場合、時期的な要因もあるでしょう。
本記事では、求人に応募が来ない原因や時期的な傾向を踏まえながら、効果的な対策について詳しく解説します。
求人に応募が来ない原因とは
求人に応募が来ない原因としては、以下に挙げる8つの状況が影響していると考えられます。
求人票の内容が曖昧・魅力に欠けている
求人票は、企業と求職者における最初の接点です。また、自社および募集職種に関する魅力を伝える、重要な広告としての役割を担っています。
内容が曖昧な求人票では、求職者が具体的なイメージを描くことができません。また、魅力に欠ける内容では、応募意欲を削ぐ結果にもなるでしょう。さらに、ありきたりな求人票は、他社の求人情報に埋もれ、求職者の目に留まらない可能性もあります。
給与や条件が市場相場に比べて見劣りする
求職者は、転職サイトに掲載された複数の求人の中から、給与や条件の良い案件を比較検討したうえで、応募するかどうかを決定します。
同業種や同職種であれば、給与や勤務条件、福利厚生などは客観的に比較しやすい項目です。自社が提示した条件が市場相場より低い場合、候補から外されてしまうでしょう。
勤務地や勤務時間に制約が多い
「勤務地が一拠点のみ」「シフト勤務のみで時間の融通が利かない」といった、勤務地や勤務時間に制約が多い求人では、対象となる求職者層が限られるため、応募効果が低下します。
また、近年の求職者は、ワークライフバランスを重視して職場選びをする傾向があります。リモートワークやフレックスタイム制などを導入し、柔軟性の高い勤務スタイルが可能であることを打ち出しましょう。
ターゲット人材に合った媒体やチャネルを使っていない
求人媒体や採用チャネルには、それぞれ異なるユーザー属性があります。若年層であればSNS、ハイスキル層であれば専門型の転職エージェントやビジネス系SNSを利用して転職活動を行う傾向があるため、自社のターゲット人材に合っていない媒体やチャネルを活用しても、十分な効果にはつながりません。
自社が求める人材にリーチするためには、まず明確なターゲット設計と媒体特性の分析を行い、最も適切な媒体やチャネルを活用することが重要です。それにより、時間とコストの両面における無駄を軽減できるでしょう。
企業の知名度やブランド力が低く、応募動機に結びつかない
知名度やブランド力のある企業は、信頼性や安心感につながります。そのため、求職者の多くは「自分が知っている会社」「メディアなどで評判の高いブランド力のある会社」を基準に応募先を検討する傾向があります。
自社の知名度やブランド力が低い場合、応募の選択肢から外されてしまうことは珍しくありません。求職者の応募動機を高めるためには、SNS運用による認知拡大や採用ブランディングの強化が急務です。
応募からの導線(応募フォーム・ページ)がわかりづらい
自社の求人を掲載しても、応募ページやフォームなどへの導線がわかりづらければ、応募をあきらめてしまう求職者は少なからず存在するでしょう。
特に現在は、スマホから求人を閲覧する求職者が多数を占めています。応募フォームやページの仕様がPC向けであったり、導線が複雑で次のステップに進みにくかったりする場合、求職者の離脱率が高くなってしまいます。
過去の対応が悪く、口コミ・評判が悪化している
昨今の求職者は、転職サイトなどで気になる企業の情報収集を行うだけでなく、SNSや口コミサイトなどもチェックしています。SNSや口コミサイトからは、採用担当者の対応や社内の雰囲気など、企業のリアルな情報を得ることができます。
ただし、面接官の態度や連絡の遅さなど、たとえ過去の対応であっても、悪い口コミや評判は削除されません。ネガティブな情報は、より求職者の印象に残りやすいため、応募意欲を下げてしまう要因となるでしょう。
競合が多く、採用市場が供給不足の状態にある
自社の業種や募集職種によっては、採用市場での競合が多く、人材供給が不足するケースもあるでしょう。募集職種が採用市場で供給不足の状態にある場合、求職者が有利な立場となります。
このため、自社の待遇や勤務条件などが競合他社より劣る場合、求職者はより条件の良い企業へ流れてしまい、自社の求人に応募が来ない大きな原因となります。
求人に応募が来ない場合の対策
自社が出した求人に応募が来ない場合、以下に挙げる8つの対策を実施してみましょう。
求人票の見直し(仕事内容・魅力・条件の書き方を改善)
自社が掲載した求人に応募が来なかった場合、「仕事内容」「自社や仕事の魅力」「勤務条件」などに問題がなかったか、見直してみましょう。
求人票は、単なる条件の羅列だけでは求職者の興味を引きません。自社の魅力をPRする広告として、どのような商品を扱うのかなど、具体的な仕事内容を記載したうえで、やりがいや成長ポイント、社風なども含めて記載しましょう。
給与・待遇・福利厚生の再検討と市場相場との比較
求職者が応募先を決める際、「給与」「待遇」「福利厚生」は主な判断基準となります。特に、同業種や職種、ポジションにおいて他社と比較したうえで、より条件の良い企業が候補となります。
充実した給与や福利厚生は、“従業員を大切にする企業”という印象を求職者に与える要素です。自社の提示する条件が市場相場と比較して下回っている場合は、再検討する必要があるでしょう。
採用ターゲットを再定義し、それに合ったチャネルを選ぶ
自社がどのような人材を求めているのか、採用要件が明確でないと、効果的なチャネルの選択ができません。狙う層によって、使用すべきチャネルは異なります。そのため、採用ターゲットの再定義を行いましょう。
若手層であれば、SNSや未経験・第二新卒向けの転職サイト、専門職などの即戦力層であれば、職種特化型のエージェントやダイレクトリクルーティングなどがおすすめです。
SNSやブログなどで採用広報・企業ブランディングを強化する
採用広報や企業ブランディングの強化には、SNSや自社ブログの活用が効果的です。SNSやブログで、求人票では伝わらない自社の強みや魅力、社内の雰囲気などを求職者に発信しましょう。
SNSやブログで自社の情報を発信し続けることで、求人媒体では出会えない転職潜在層にも認知されるうえ、競合他社との差別化も図ることができます。
応募までのフローを簡潔にし、スマホ対応など利便性を高める
気になる求人があっても、「入力項目が多い」「導線がわかりづらい」など、応募までのフローが複雑だと、求職者が離脱する原因になってしまいます。
また、現在の求職活動はスマホ利用が主流になっています。求職者の利便性を高めるためにも、その場で簡単に応募完了できる仕組みと、スマホ優先型の設計は欠かせません。
求人媒体の変更や掲載タイミングの工夫を行う
求人への応募が来ない原因の一つとして、ターゲット層に合わない求人媒体の選択だけでなく、掲載タイミングも挙げられます。ターゲット層にマッチした求人媒体を選び、求める層が動く時期を狙いましょう。
年度末やボーナス退職後といった最も大きく求職者が動く時期だけでなく、月曜日などの週明けも狙い目といえるでしょう。
ダイレクトリクルーティングやリファラル採用を併用する
求人媒体などは、受け身の採用手法です。そのため、自社の採用活動を求人媒体頼みにしてしまうと、一向に効果が上がらないケースもあります。
企業から積極的に狙う人材にアプローチをかけるダイレクトリクルーティングや、自社従業員の知人や友人を紹介してもらうリファラル採用を併用しましょう。これにより、コストを抑えながらミスマッチの少ない採用が実現しやすくなります。
過去の応募者や辞退者に再アプローチを検討する
労働者人口の不足により、ますます人材獲得が困難になる中、新たな母集団のみに頼るのは限界があります。ぜひ、かつての応募者や内定辞退者のデータベースを活用して、候補者として再度検討しましょう。
タレントプールを形成しておけば、過去の応募者や内定辞退者の採用に至らなかった理由を把握できるため、適切なタイミングで再アプローチすることが可能です。
求人に応募が来にくい時期とは
求人への応募は、時期によっても変動します。応募が来にくい時期は年間を通じていつなのか、具体的な6つの期間について、以下で解説します。
年末年始(12月後半〜1月初旬)
12月後半から1月初旬の年末年始は、求職者だけでなく企業も休暇に入ることがほとんどです。求職者は帰省するなど、一旦転職活動から離れてゆっくり過ごす傾向にあります。
企業も年末年始休暇に入ると、求職者からの問い合わせなどに応じることができません。応募への積極的な動きが弱まるため、この時期の求人はどうしても効果が低くなるでしょう。
ゴールデンウィーク期間
ゴールデンウィーク期間も、年末年始などと同様に、求職者と企業が一斉休暇に入るため、応募への動きが鈍くなります。
しかし、ゴールデンウィーク終了後には、再び求職活動に本腰を入れる人が多くなるため、求人を出稿するなら、休暇明けのタイミングを狙いましょう。この時期は、連休中に転職を検討した人が、実際に行動を起こし始めるタイミングでもあります。
夏期休暇前後(7月後半〜8月中旬)
7月後半から8月中旬の夏期休暇前後は、転職市場全体でも応募数が減少しやすい典型的な時期です。お盆などの休暇を控え、企業の採用担当者や求職者が帰省することも多く、求職活動を控える傾向にあります。
さらに、企業側もこの期間中に交替で夏期休暇を取るため、面接官や現場責任者とのスケジュール調整が難しくなり、選考が停滞するケースも見られます。
大型連休明け直後
大型連休中は、転職を検討する期間ではあるものの、実際に応募などのアクションを取る求職者は少ない傾向にあります。
さらに、在職中の求職者の場合、大型連休明け直後は仕事が立て込むため、すぐに求人に応募する動きは鈍くなります。このため、実際の応募活動が活発化するのは、連休明けから1〜2週間ほど経過してからとなるケースが多いでしょう。
新年度や新学期が始まる直前
新年度や新学期が始まる直前は、求職者個人の生活の変化や予定に伴い、プライベートを優先する傾向があります。
たとえば、引っ越しなど新生活の準備に追われ、求職活動は後回しになりやすいため、この時期の求人への応募は落ち込みやすくなります。それに伴い、転職活動の再開や本格的な求人応募は、新生活が落ち着いた新年度・新学期開始後にずれ込む傾向があります。
ボーナス直後
ボーナス退社という言葉があるように、ボーナス支給後に転職を検討する人は多く存在しています。ただし、この時期は、情報収集段階にとどまるケースが多いでしょう。
また、ボーナス支給直後は経済的な余裕から気持ちが落ち着くほか、上司の引き止めや待遇改善の提示によって、転職を思いとどまるケースもあります。このため、求人を出しても、応募数が期待ほど伸びないかもしれません。
御社の業務に副業社員を検討してみませんか?
今回は、企業の採用活動において大きなダメージとなる、求人への応募数減少について、成果に至らない原因や対策など、あらかじめ認識しておきたい情報をまとめてお届けしました。
採用活動の効果を高めるには、適切な求人媒体や採用チャネルの選択が必須です。また、近年注目を集めつつある副業人材専門のプラットフォーム活用も、賢明な手段でしょう。
そこでおすすめなのが、コストと労力を減らしながらハイスキル層との出会いが実現する、副業人材マッチングサービス「lotsful」です。
「lotsful」のスピーディーなマッチングによる副業人材・副業社員の投入で、御社の業務の質と効率を向上させれば、組織全体のパフォーマンス向上にも貢献します。業務の質と効率に関するさまざまなお悩みを解決したいなら、まず「lotsful」へご相談ください!
関連記事
・採用がうまくいかない24の原因をフェーズごとに解説
・ダイレクトリクルーティングとは?メリットデメリットや費用相場を解説
・リファラル採用とは?メリットデメリットや注意点まとめ